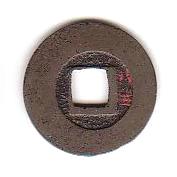|
|
制作作日記
2025年1月~12月31日分まで
|
| 2025年は紅白おめでたいで・・・ |
 |
 |
| 水戸短足寶写 |
長郭手狭足寶大様 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
 |
| 八厘会会場が新しくなりました! |
八厘会(天保仙人様が主催する古銭会)
天保通寶の研究を中心に、各種泉談が満載の会です。
例会日:原則として8月・12月を除く毎月第4土曜日 |
12:00 開場・受付
12:30 『楽笑会』骨董美術何でもオークション
14:00 『八厘会』天保通寶研究など
15:00 盆回し式入札会
16:30 終了(後片付け)
会費:500円(大学生以上の男性のみ。付添者は無料)
電話:090-4173-7728(事務局 日馬) |
地下鉄日比谷線・JR京葉線 八丁堀駅より徒歩3分
地下鉄日比谷線・東西線 茅場町駅より徒歩7分
都営浅草線 宝町駅より徒歩5分
JR 東京駅からあおぎり通りを経由して徒歩13分
※八重洲中央口改札から大通りを渡り、右手へ・・・セブンイレブンで左折しあおぎり通りへ
あとはまっすぐ。八丁堀石川クリニックの隣の庄司ビル3階。その先隣は佐藤調剤薬局。
会場住所:東京都中央区八丁堀2丁目19-7 庄司ビル3貝「セキレイ会議室」
|
 |
|
| |
|
|
| |
 そうだ!「貨幣」を読もう! そうだ!「貨幣」を読もう!
貨幣誌は戦前の東洋貨幣協会時代から続く、現存する最も古く、かつ権威ある貨幣収集愛好家団体です。貨幣収集趣味が衰退している昨今、生で勉強できる貴重な研究会場であるとともに、情報収集することもできる交流の場でもあると思います。かくいう私、会費は払ったものの、例会には参加したこともなく、果たして正式会員であるかどうかも分からない幽霊です。まあ、今でもこの情報誌が送られてくるから会員なんでしょうね。
日本の貨幣収集界が底辺を広げてもっと盛り上がってもらいたいので、その気のある方、私のように地方在住で仕事の関係で参加できない方も、情報収集アイテムとしてご参加・ご活用ください。
入会申し込み先
〒243-0413 神奈川県海老名市国分寺台1-15-14
日本貨幣協会事務局(副会長) 吉田守 ☎090-7839-4437
郵便振替00110-0-8563 日本貨幣協会
※年会費は5000円だったと思います。この記事は勝手な応援広告なので必ずお問い合わせください。
|
|
|
|
| |
【メール直接投稿に関するお願い】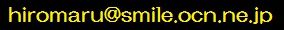
私に直接メールされる場合につきましては
①住所(必須)
②お名前(本名:必須)
③雑銭掲示板のニックネーム(必須)
④電話番号(任意)
⑤プロフィール(任意)
をメールに記載してお送りいただきますようお願い申し上げます。
画像はJPEG・GIF形式でお願いします。大きすぎる画像、大量画像は受けられません。
※大量の鑑定依頼には原則対応致しません。
※翻訳できない言語についても同様です。画像として貼り付けられた文字など処理できません。
身元確認ができないメールは過去に投稿歴があっても削除対象になることがあります。
なお、雑銭掲示板は安全な媒体ですので、個人的な連絡以外は記事投稿はそちらにお願いいたします。 |
| |
 |
文久永寶銭研究資料 編集責任者 坂井博文 文久永宝周遊会
2025年 洋装製本(和風) 82P 320図 販売価格5000円
文久永寶周遊会創立10周年記念大会の研究資料です。間もなく収集誌上に頒布価格等の情報が掲載されると思います。
|
 |
寺社札入門(播磨・その他編)予録・藩札入門「一国一枚」
知命泉譜・伍 日本紙幣の部 編集 鳳凰山 神野良英
2025年 洋装写真製本 128P 販売価格2000円(税別)
鳳凰山師は私が知る限り日本有数のゼネラルコレクターであり、超博識の古銭の伝道師です。これで寺社札編は3冊目、知命泉譜として5冊目というまことに頭の下がる大事業に挑んでおられる。知命とは天命を知る年齢だそうで・・・私のような痴迷人間とはそもそも格が違うようでして・・・。 |
|
| |
| → 2026年の制作日記へ |
| |
12月31日【ゆく年くる年】
あわただしい一年があっと言う間に駆け抜けていった気がします。今年も激動の一年でした。
脱コロナにはじまり交流や行事参加も少しずつ増やしました。
親父様が3月に右肩脱臼。同時期に姉の看取り対応がはじまり、そんなさなか子供が海外旅行中に緊急入院して帰国ができなくなり、さらに帰国後にも駅前で倒れて深夜に都内まで迎えに行く羽目になったことも。(しかも姉の四十九日の前夜。今は元気回復。)
認知症の介護で連続睡眠時間が取れなくなって不眠症のような生活。強いストレスのせいかついに糖尿病と言われて酒抜き・肉抜き・油抜きの節制しています。ね、可愛そうでしょう。
秋に東京湾観音へ親父様を連れて行ったとき、無料で占うからという言葉にのって運勢を見てもらったら、「2年間ぐらい最悪」と言われた。絶対足元を見られた。しきりに祈祷を勧められたが、あの言葉にのっていても多分幸せになれなかったでしょうね。
こんな私を幸せにできるのは、美しい古銭か、素敵な彼女だけです。みなさんもっと協力しなさいよ。
※見よう見まねでスライドショーを作ってみましたが、CPUを結構食うようです。製作中に何度かフリーズしかけました。動かなかったら削除します。でも、この画像・・・見やすいでしょ。 |
| |
| 山口(千葉)の庚申塚 |
 |
江戸期の庚申塚
青面金剛・鶏・猿 |
 |
麻綿原高原への山中
|
工藤師の著作
南部當百銭の謎 |
 |
12月29日【暴々鶏師のこと】
元・雑銭の会会長であった工藤英司師が9月にお亡くなりになられたことは、皆さまもすでにご存じのことと思います。
私は練馬雑銭の会の会員番号13で、工藤師のお誘いを受けて、生まれて初めて古銭会に直接参加しました。練馬雑銭の会のサイトはネットの徘徊をしていて見つけたのですが、その結果として幽霊がはじめて実体を見せることになったのです。当時は机上の知識しかなかったので生の直接情報は新鮮でした。天保仙人様と知り合うことになったのも、そのご縁によるものです。工藤師は早坂昇竜(ノボル)の名で作家活動をされる一方、大学で福祉の教鞭をとられるなど、実に多彩な方でした。歴史や民俗学にも詳しく、庚申信仰のお話などは(私も郷土史をかじっていますので)とても参考になりました。
本日、工藤師のサイト「古貨幣迷宮事件簿」を開こうとしたところ閉鎖されたことに気づき、ひとつの時代が終わったような一抹の寂しさに包まれました。
工藤師は、かつて私の職場に直接取材に来られたこともあり、年齢も近かったことから、さまざまなことを教えていただきました。私が密鋳銭の世界に深くはまったのも、工藤師が作られていたサイトの魅力に引き込まれたからにほかなりません。
そのサイトは、外部からの攻撃によって完全に破壊されてしまいましたが、私はそれを何らかの形で継承・復活させる意味も込めて雑銭掲示板を開設し、今日に至っています。私自身も外部からの侵入や攻撃に長く悩まされてきましたが、続けてきたことで擁護してくださる方も増え、何とか今日まで生き延びることができています。
もっとも、私がこの古銭サイト(新寛永通宝分類譜・雑銭掲示板)をあと何年続けられるかは分かりません。現役として一定の収入が約束される期間も、もうそう長くはありません。人生の次なるステージについて、そろそろ考える時期が近づいているのかもしれませんが、それでも今を生き、今続けることで、自分の存在と古銭趣味の存在を示していきたいと考えています。
工藤師に、心より合掌。
※工藤師のペンネーム「暴々鶏」の読み方と意味、由来を皆様ご存知でしょうか。私はついに聞きそびれてしまいました。
ひょっとして庚申信仰の鶏と関係があるかもしれない・・・。 |
| |
12月28日【修理・再編集ひとまず終了】
12月下旬、今年分の過去記事のほとんどを失ってしまい、その後は不眠不休で修正作業に追われることになりました。その結果、ほぼ満足のいくレベルまで記事を復活させることができました。スキャナ撮影の手法に関する記事や、左の雑談的記事などは復活させていませんが、現状としてはもう十分だと判断しています。
記事が消えたと分かり、パソコン内のデータでは復活が望めないことが判明した時点では、復旧は正直ほぼ諦めていました。しかし、南様が過去記事のデータを発見してくださったことは、非常に大きな助けとなりました。画像データだけはすべて手元に残っていたため、発見された記事データに合わせて手作業で貼り付け直すこと約一週間。完全に喪失した記事については、残っていた写真をもとに新たに文章を書き加え、何とか体裁を整えることができました。
苦労したのは、発見された記事データのサイトがあまりにも重かったこと(これは私のサイト自体が重いのが原因です)。そのため、画像データの抽出と貼り付けが半分ほどしかできず、手元にある画像データと記事データを一つ一つ照合しながら再構築する作業が実に面倒でした。
また、制作日記の一年間分のデータは、このおもちゃのようなHP作成ソフトには処理の荷が重く、編集中にしばしばフリーズを起こします。このソフトはデータを上部(12月分)から順に読み込む癖があるため、記事が下へ行くほど、つまり1月に近い古い記事の読み込みや修正になるほど、時間がかかります。編集には多少のコツがあるのですが、それでもとにかく時間と手間を要しました。
天邪鬼な私は、追い込まれると驚異的な集中力を発揮します。今回は役立ちましたが我ながらすごいと思う反面、呆れてしまうところでもあります。あ~あ、眠い。これでも毎日ちゃんと職場で働いていたんですよ。 |
| |
| 元画像 |
失敗例 |
 |
 |
| ChatGPT作 |
Copilot作 |
 |
 |
12月28日【AI狂騒曲】
AIでしばらく遊んでいたことがありましたが、時間の無駄になると思い中断。同じ指示を出してもなぜか上手くいかないことがある。最初に成功したのがChatGPTだったが、本日Copilotでも成功。どちら差がほとんど同じレベルに仕上げられた。ただし、同じ指示を出しても思い通りにはならないことが多い。補正の指示を出したのに、画像の新規生成されてしまうことがあり、失敗例がその画像。文字にならないこともしばしば。うまく使えるようになるとトリミングと色補正ができるかも。左右の画像の違いほとんど分からないでしょう? |
| |
| 仙台銭 正字手破目寶背濶縁大様銭 |
 |
 |
 外径25.6㎜ 外径25.6㎜
寶貝の二引きの上が切れます。
まるで笑っているみたい。 |
12月28日【仙台大様】
外径25.6㎜のこの輪に大欠けのある仙台正字手は旧貨幣誌に掲載されたものらしいと聞いています。
25.6㎜なら寛文期亀戸線の大ぶり銭レベルの大きさなのですが、古寛永の場合25㎜を超えれば概ね大様といえます。しかもこの銭は背濶縁というおまけつき。破目寶は背濶縁気味のものが多いと古寛永泉志にあるのですが、これはもう蛇の目・・・大濶縁です。 |
| |
| 会津濶縁赤銅質再覆輪 |
 |
 |
 |
長径49.40mm
短径33.00mm
銭文径40.00mm
重量22.2g |
12月28日【会津大濶縁】
いやぁ~これは欲しかった。というより逆転されるとは思わなかった。
会津濶縁の再覆輪ですけど、極印が大きいので石持桐極印につながるもの・・・つまり水戸藩とのつながりを示すものかなと思いました。赤く発色した会津濶縁の再覆輪は恐らく少ないと思います。
会津濶縁は私の大好物のひとつです。昨年、会津大濶縁と思しきものに熱狂し、結果として変造品と分かった超苦い経験があります。そのリベンジのつもりでしたが・・・残念。
制作日記2024/9/26 を参考にしてくださいね。 |
| |
| 安南寛永 元文期和歌山銭 摸鋳 |
 |
 |
12月27日【安南寛永】
昭和の後半、安南寛永はどの古銭店に行ってもたくさんあった時期があります。だれも見向きしない汚い奴。その頃、島銭も大量に入ってきていて、私の関心もそちらに強く向いていた気がします。島銭は安くなったとはいえ高級品でしたから。この見栄えの悪い安南寛永も当時だったら100円程度だったでしょう。ところがその後、安南寛永が消えた。ついでに古銭店そのものも世の中から消えてしまった。
安南寛永は今もほとんど人気がありません。でも、私にとっては金の鉱脈に見えます。おかしいかしら。 |
| |
| ❶水戸力永低寛小頭永俯頭永 |
 |
 |
| ❷水戸星文手 |
 |
 |
| ❸長門裕字 |
 |
 |
| ❹重文古寛永 |
| |
 |
12月27日【古寛永リハビリ中】
古寛永の分類は毎日泉譜を眺めていないと感覚が養えません。というより衰える一方ですね。
私が30歳台のとき、富山古銭研究会の三鍋師のお店がよく東京の交通会館などに出店されていたので、催事があるたびに訪れていました。古寛永泉志を買って、とにかく穴が空くほど眺め続け、基本銭を中心に集めはじめたのはこの頃です。当初は全く歯が立たなかった古寛永の全体像がなんとなくつかめるようになると楽しくなり、類似品を並べては違いを探していました。
寛永通寶・・・とくに古寛永は細かい違いを分類こそするものの、大分類の際はイメージだけでつかむ・・・それをHPに記して遊んでできたのがこのサイトなのです。
とはいえ古寛永はやはり難しい。
ここ10年の私は収集の中心を天保通寶に置いていたのと、50歳を境に視力が落ち始めたこともあり、裸眼で寛永銭を判別することがとても難しくなり、自然と収集を避けるようになってしまいました。
❶の古寛永は平凡な力永低寛の書体ながら、永頭が短く、拡大すると永頭が急角度で俯します。ところがスキャナー画像を見るとたいしたことがない。不思議だ。
❷は細縁と刔輪ぷりがとても可愛く感じて購入してしまった。星文様と星文手の違いが良く分からなくなっていたので当初は分類を間違えていました。恥ずかしい。
❸は誰が何と言っても長門。背が美しい。でも分類を間違えた。星文様として考えていたが間違っていた。記事消失で分類名が再消失。たぶん、裕字背小郭かな。
❹は面側の画像しかありませんが沓谷銭の面重文。乱視の気分です。こんなものも楽しいですね。 |
| ❺長門麗書 |
 |
 |
❺も長門中の長門銭。しかも面の地も波打っているのでたまらない。これも分類を間違えていました。麗書斜王寶だそうです。関東のAさんや南さん、四国のOさんなど鍛えられた目の肥えた人たちはすごいと思う。私・・・?、目下、リハビリ中です。 |
| |
12月27日【あやかしども】
古銭収集を長く続けていると、贋物をつかまされることが実に多くなります。いや、この古銭の世界そのものが、贋物だらけだと言ってもよいのかもしれません。そもそも不知銭などは堂々たる贋金ですし、絵銭に至っては、もはや銭ですらないフェイク品。本物よりも、まがい物の方が喜ばれる世界など他に例がなく、古銭界はやはりどこか異常です。
今日は皆さまを、そんな「あやかしの世界」にご招待します。
❶の古寛永は、ネットで見た際に母銭だと思い、応札しました。地染めが見られない点は気になったものの、くたびれた母銭だろうと判断。しかし後日、某氏から「これは新作だよ」と教えられ、同じコピー品が複数出品されていることも判明。が~ん。
汚し方も自然で、なかなか上手。もっとも、母銭として出品されていたわけではないので文句の言いようもなく、ひとりで勝手に踊っていただけでした。
❷の本座広郭は、文字が細く、いかにも母銭然としたつくり。大きさも十分で、しかも背大肥郭。見つけた瞬間、「やったあ!」と思ったのですが、見つけられたのはほかならぬ私自身。
仙人様によると、これは明治期に元銭座職人が作った戯作品とのこと。おそらくコレクター向けの品でしょうから、やはり贋作ということになります。あいたたた……。
❸は切継銭……というより、銭を割って並べ、再度鋳造しているので「割継銭」と呼ぶべきかもしれません。接着剤や溶接によるものではなく、銭径や内径も通用銭と同じ。母銭から作られたものです。
これは虫吉さんから戯作を承知のうえで1,700円で購入。これくらいなら、贋作でも腹も立ちません。
今、古銭の世界は贋作があふれています。そして、怪しい書体やつくりのものほど私たちは喜ぶ。まったく妙なコレクターだらけです。使えないお金を、使えるお金と両替して喜んでいる・・・そんな私たち自身が、すでに「あやかし」になっているのかもしれません。 |
| ❸戯作寛永 切継銭 |
|
|
| |
12月27日【進二天なの?】
萩藩銭の天保通寶は、縮通類を除けば、いずれも個性の主張が実に強い銭種です。そんな個性派揃いの中にあって、私がいまだ実見したことのない奇観品がいくつか存在します。
❶進二天手鋳浚い母銭は、昭和32年頃、安芸宮島の古道具店において、西吉麗鮮斎氏が発見にしたと云われる品です。異様なほど大きな小判型の銭形に、極端に縮小した文字を備え、書風から見れば方字の改造銭ではないかとも思われます。
萩藩の鋳浚い母銭類については、かつて某美術大学生が関与した贋作が存在するという噂が絶えず、それらと並んで、この進二天手鋳浚い母銭も、いつの間にか泉譜から姿を消したようです。
❷進二天寄書は、いかにも「ありそう」な雰囲気を持つ一品です。ただ、この書体をどう見るかとなると悩ましく、方字ではないのか……いや、方字接郭と考えてもよさそうです。もっとも、珍品であることに変わりはなく、その点では呼称の問題はさほど重要ではないのかもしれません。
ただ、こうして両者を並べてみると、進二天寄書は極端な小郭になっていることが分かります。これは不思議。覆輪銭の水戸揚足寶や遒勁が小郭である例がありますが、あるいはそれに類する変化と考えることもできるかもしれない。この点は、なかなか興味深いところです。 |
❶進二天手鋳浚い母銭
異書(母銭図録より) |
進二天寄書
(類似カタログより) |
方字白銅銭(参考) |
 |
 |
 |
|
| |
| ❶密鋳 細字背元写江刺? |
 |
 |
| ❷寛文期亀戸銭繊字狭文白銅銭 |
 |
 |
| ❸密鋳俯永写し |
 |
 |
| ❹繊字背小文格下げ母銭 |
 |
 |
12月27日【卓上の新寛永】
私の机の上には、撮影を終えた古銭が散乱しています。さすがにむき出しではありませんが、関西のSさんからお借りしている不知天保曳尾天や、明和期俯永面背刔輪といった、とんでもない珍品まで転がっている始末です。年末の大掃除や整理をしたいところなのですが、HPの再構築に追われ、それどころではありません。……というのは言い訳で、実のところ、ここ数年ずっとこの状態が続いています。
加えて、私の仕事は定期的な休みが取りづらい業種です。ブラックだ――と言いたいところですが(職員に対してはそんなことありませんよ)。今日は本来なら休みの日なのですが、朝7時に親父の受診付き添いで病院の予約を入れ、昼からは認知症家族の会の忘年例会。仕事なのか遊びなのか、もはやよく分かりません。まあ、私は親父の接待役でもあるわけで。本来は糖尿病の食事制限中なのですが、今日は昼酒してやるぞ~、と。
❶の細字背元写江刺?は、どこで入手したのか、もはや不明です。江刺風のざらざらした鋳肌。こうした評価や名称付けは所有者の特権ということで……江刺、ということにしておきます。
❷は画像だけは残っているのですが、現物が見当たりません。パソコンの下に潜り込んだのか、ただいま捜索中。そのうち、ひょっこり出てくるでしょう。
❸の密鋳俯永は、穿がべったりヤスリ。赤茶色のざらざらした鋳肌で、よく見かけるタイプです。側面は摩耗していて、よく分かりません。机の上の住人です。
❹は調べたら四国のKさんから頂いた通用銭に格下げされた母銭と判明。たぶん他の古銭と比較するためBookから出されてそのまま放置状態になったものだと思います。実は再撮影によって行方不明になる古銭が一番多い。格下げ母銭は鋳だまりや鋳不足、仕上げの失敗などで母銭になり損ねたんじゃないかな~という推定によるもので、真実かどうかは判らない。❹は穿に通す角棒ずれて面背の輪が偏輪気味になっていますし、小さな鋳だまりもある。細縁銭といっても問題ないものですが、母により近いものです。
|
| |
| 仙台跛寶昴通銀銭 |
 |
| 異寛小通 |
 |
| 寶連輪 |
 |
| 水戸昴通背星無背 |
 |
12月27日【撰銭の達人再び】
古銭収集家の中には、私のようにネットや入札誌、古銭店を通じて主に単品買いをしている人もいれば、雑銭を大量に購入して選り出しを行う人もいます。また、とらさんのように先輩方のもとを巡ってピンポイントで入手するという、最も効率の良い方法を実践されている方や、骨董商巡りそのものを楽しんでいる方もいます。そういう意味では、私の収集方法はおそらく最も効率が悪い部類に入るのだろうと自認しています。
なかでも、ネットで入札しっぱなし……というのが一番よくない、とご忠告を受けたことは何度もあります。それでも、ストレス解消のため、なかなかやめられませんね。
さて、撰銭の達人・Kiraさんから、久々にご投稿をいただきました。(ありがとうございます。)
さすが「綺羅、星のごとく」という言葉がぴったりの内容です。
仙台古寛永の雉狩銀銭は、大永の書体が一般的ですが、「跛寶昴通」は、さすがのKiraさんも初見とのこと。ありがたや~、です。
「異寛小永」「寶連綸」は、古寛永初期不知銭の有名どころ。「異寛小永」はなかなか入手の機会がなく……とはいえ、「志津麿大字」という私一番の古寛永をAさんに譲ってしまった手前、行動が一貫しておらず、さすがに今さら買えない。葛藤です。
もっとも、45㎜台の秋田小様を2回入手して2回とも譲ってしまった経験があるので、私ならあり得る話かもしれません。
「水戸昴通背星無背」は、本来なら「水戸昴通無背」でよさそうなところですが、あえて「背星」の照合を入れたい。これには岡山銭説もあるようで、通の形や尓の形、背の雰囲気からも、たしかに可能性を感じさせます。まさに白眉の品です。
ところで、雑銭の大量買いをされる方の話を聞くと、家に雑銭が溜まりすぎて床が抜けそうになる、なんてこともあるそうですが……Kiraさん宅は大丈夫でしょうか?
|
| |
| 火防基寶 背函館 |
 |
 |
| 松前通用 背政 |
 |
 |
 松前通◯・・・最後の一文字が長らく判読できなかったのですが、用の草書体のようです。「松前通用」・・・よくできた空想貨幣でしょう。 松前通◯・・・最後の一文字が長らく判読できなかったのですが、用の草書体のようです。「松前通用」・・・よくできた空想貨幣でしょう。 |
12月27日【火防基寶】
こんなにきれいな画像の火防基寶は初めて見ました。この絵銭、昭和9年の函館大火の見舞いの答礼として函館消防署が作った絵銭なんだそうです。
制作日記2015/9/24に函館火災について詳しく書いてあります。
火防基寶の姉妹銭に安鎮加寶があるそうです。
松前通用は新作の絵銭でしょうけど良く分からない。江戸期においてこのような通用銭サイズの絵銭は贋造を疑われるのでうかつには作れない。
背の政の文字も不明。あるサイトによると函館通寶の背文字「安」は函館開港の年号安政を意味している。
そのためこの松前通用の「政」は安政の政ではないかとのこと。
少なくともこの時代に銅銭を鋳造する意味はあまりないので、これはその史実を踏まえた上での戯作じゃないかと思う次第。
|
| |
| 24.9㎜ |
覆輪 |
 |
 |
| 24.35㎜ 4.2g |
|
 |
 |
| 24.17㎜ 4.0g |
|
 |
 |
| 24.0㎜ 3.8g |
|
 |
 |
| 23.9㎜ 2.4g |
|
 |
 |
| 23.7㎜ 2.7g |
 |
 |
12月27日【婉文がいっぱい】
婉文とはなよなよした女性的なやさしい文字の意味らしい。岡山銭の婉文は濶縁銭と覆輪銭があり、文字が極端に縮小していて私は大好きな一枚なのです。普通、私は美銭を一枚手に入れてしまえば満足してしまうのですが、この古寛永は目につくと必ず手にいれていまう種類。天保銭でいうと会津濶縁がそれに該当します。
今回は関東のAさんにせがまれて手持ち品をざっと持参した次第。Aさん・・・しきりに私の品を見て一番大きいのが欲しいとおねだりしてきました。いくらなら譲ってくれますかの言葉に、値段を決めてください…と思わず言ってしまいました。
5000円ならどうですか・・・の言葉に、え~と思いながらも「いいです」という言葉が口を突きました。まあ、お世話になってますから・・・
さらに初期不知銭の志津麿大字本体も所望されました。熱愛に負けた私は超お人よしです。
かくしておじさんの愛娘2人はおじさんに嫁入りしています。Aさんお買もの上手です。私の大切な娘ですから大切にしてくださいよ。 |
| |
12月26日【投稿記事・発見を振り返る】
※この記事も11月に掲載し、消失した記事の再構築ですが、内容は新規の物になっています。 |
| ❶長郭手覆輪瘤足寶(覆輪存痕) |
2025/4/25制作日記 |
 |
 |
話題を探しながら手持ち品を眺めていたら、あれ・・・どこかで見たことがある、と閃いた。當百の横引きと寶前足に鋳だまりがあり、寶字は靴を履いたようになっている。鐚銭に草足寶元符というものがありますが、見方によってそう見えなくもない。探してみるとすぐに4枚も見つかった。
①寶貝の二の上横引きが細い ②寶前足が異足寶 ③當冠右側に瑕 ➃百の横引き末尾に瘤 という共通点があります。
関西のTさんならすぐに看破されるところでしょうが私は数年がかりで気が付きました。数は多いと思いますが面白いです。 |
長径49.35㎜ 短径32.4㎜
銭文径41.0㎜ 重量23.4g |
| ❷仙台長足寶大様(未使用色) |
制作日記2025/4/19 |
 |
 |
「松葉でつついたような」地肌とはよく言ったもので、この天保銭は 冷えたばかりの溶岩の肌みたい。未使用で摩耗のない仙台銭はこういう肌なのかもしれません。大様は面左側に雲状の鋳だまりがあるのですが、これにはありませんが、大ぶりです。なお、この品は寶前足先端に陰起と鋳だまりがあり、短く見えますが長足寶です。 冷えたばかりの溶岩の肌みたい。未使用で摩耗のない仙台銭はこういう肌なのかもしれません。大様は面左側に雲状の鋳だまりがあるのですが、これにはありませんが、大ぶりです。なお、この品は寶前足先端に陰起と鋳だまりがあり、短く見えますが長足寶です。 |
長径49.05㎜ 短径33.20㎜
銭文径40.60㎜ 重量17.9g |
関西T氏提供 |
| ❸長郭手覆輪刔輪削字延貝寶異極印 |
制作日記2025/4/13 |
 |
 |
銭文径が本座と変わらない不知銭として関西のTさんからご報告頂いた不知銭。まるで寶貝がズボンを摺り下げたように長い・・・腰パン天保と呼びたいぐらい。しかも側面が滑らかな砥石垂直仕上げ・・・ちょっと近代的かなと画像では思ってしまいますが面背の仕上がりはいたって普通。これ、銭径の縮みをごまかすため意図的に寶を伸ばしたのかも。製作は粗削り。 |
長径49.35㎜ 短径32.95㎜
銭文径41.60㎜ 重量20.9g |
関西T氏提供 |
 |
上下の天保銭のそれぞれの側面。そっくりなので同炉としか思えない。 |
| ❹長郭手刔輪延貝寳手張足寶 |
制作日記2025/4/13 |
 |
 |
地に鋳ざらい痕跡のある覆輪刔輪銭。寶足が伸びて張足寶と宏足寶の中間のような形状。側面製作の画像を見る限りは上と同炉銭。こちらはよく見かけるような不知銭張足寶系の書体。前足が突き出るような張足寶であり、覆輪刔輪銭です。 |
長径48.6mm 短径32.35mm
銭文径41.1mm 重量20.6g |
関西T氏提供 |
| ❺長郭手覆輪強刔輪削字長貝宏足寶異極印 |
制作日記2025/4/13 |
 |
 |
これはもう奇書といっていいほどの |
長径49.6mm 短径33.1mm
銭文径41.2mm 重量20.7g |
関西T氏提供 |
 |
上下の天保銭のそれぞれの側面。アスタリスク型の一部銀型極印。 |
| ❻長郭手強覆輪削字異極印 |
制作日記2025/4/13 |
 |
 |
長径49.5mmの立派過ぎるほどの覆輪銭。極印は見事なアスタリスク型。薄いつくりなので延展のような銭文径は大きくなっていません。見た目は鋳放しの反玉寶も思い浮かびますけど違う雰囲気。本座銭に均等な覆輪をして鋳写しするとこんなものができるという典型かも。状態は良くないけどありそうでない品。上のものと良く似ていますが、製作を見るとちょっと違うような気もします。 |
長径49.5mm 短径33.35mm
銭文径40.6mm 重量18.1g |
関西T氏提供 |
| ※上の2枚も送って頂いて撮影したように思うのですが、現物画像が見つかりませんでした。この頃、姉と子供の体調不良、入院騒ぎが立て続けにあり実はてんやわんやでした。子供は海外の空港で深夜入院騒ぎになり、帰国後も都内で深夜入院騒ぎになり・・・まあ大変。姉は病院で看取ることになりましたが、子供は元気回復。あの一連の騒ぎは何だったんだろう。親父の介護も2年が過ぎ、私はすっかり不眠症。HPが進むのなんの。 |
| ❼長郭手細字長点保長貝寶内反足寳 |
制作日記2025/4/13 |
 |
 |
細字で張点保、異足寶ながら寶貝が細長く変化し、俯二貝寶で寶足が極端に短く見えます。異足寶ながら短足寶にも見えるので内反足(O脚)寶と名付けました。側面はヤスリ目がほぼない感じで異極印。銭径は小さいものの雰囲気的には奇天類に似ていますがどうなんでしょうか? |
長径48.6㎜ 短径32.8㎜
銭文径40.7㎜ 重量20.3g |
四国K氏提供 |
| ❽不知長郭手覆輪強刔輪跛寶(寄郭) |
制作日記2025/1/11 |
 |
 |
名称に迷っていると画像が送られた品。離足寶に似ているとのことですが、似ているのは銭形でしょうけどこっちの方が断然すごい。刔輪が強烈で背が細縁になっています。寶前足は鋳走りで接していて後足が離輪しているので離足寶とは名付けられないので跛寶としましたが、寄郭と称しても良いほど強烈な刔輪。銭文径の縮小は1回写しなのにこんなに銭形が変形している覆輪刔輪銭なんて・・・絶句です。赤黄色の色調もかわいいです。
|
長径49.4㎜ 短径33.1㎜
銭文径41.0㎜ |
侍古銭会タジ氏提供 |
| ❾長郭手覆輪刔輪仰天(玉一天) |
制作日記2025/8/16 |
 |
 |
立派な覆輪の横太り銭形であり、部分的な輪の加刀・小変化が面白い。第36回の銀座コインオークションの出品物と兄弟で楽しい逸品です。天の玉だけでなく、面背の内輪の形状、面左側の地に縦に走る鋳ざらい瑕、面輪左側表面の瑕、大頭通、寶の二引きの削字、當ツの形状、寶下・當上の刔輪、背郭の角の形など特徴をあげたらきりがなさそう。
勝手に源氏名をつけて「玉一天」と称してみました。 |
径48.82mm、短径32.94mm
銭文径40.8mm、重量18.40g |
とら氏提供 |
| ❿長郭手ペン書様 |
制作日記2025/8/16 |
 |
 |
分厚く雄大な銭形の上に、極細の文字が浅く乗っかっている異製作銭。実物はまるで重厚な銅塊そのもの。ペン書手は安南銭では奇怪な記号のような文字の一類なのですが、この天保はボールペンで書いたような太細のない書体という意味では、本家の安南銭より的を射ているかもしれません。とにかく浅字細字厚肉大様なのです。
類似カタログ原品 |
長径49.92mm 短径33.32mm
銭文径41.0mm 重量26.44g |
とら氏提供 |
| ⓫長郭手覆輪強刔輪長尾天反玉寶(曳尾天) |
製作日記2025/7/9 |
 |
 |
・覆輪強刔輪銭 ・削字でやや肥字
・厚肉 ・面背文字横広 ・長尾跛天
・保前点が降る ・小点通 ・反玉寶 ・長足寶 ・大花押
パッと見ただけでこれだけ特徴があります。特に天足が大きく開き末尾が長いのと反玉寶であること、當が背が低く横広で大で花押が大きいのが目に飛び込みます。異書とか蝕字という表現も良いと思うのですが、天尾が長いのが他には見られない特徴なので平凡に『長尾天反玉寶』(曳尾天)としてみました。
|
| 三納天保(退天巨頭通)との書体類似性は感じますが、画像比較でも大きさや鋳肌など製作上の近似性がないので今のところ別種とするのが妥当でしょうね。でもよく似ている。これが現段階の結論。 |
長径49.01㎜ 短径32.89㎜
銭文径40.65㎜ 重量25.11g |
関西S氏提供 |
|
| ※記事再建ももうそろそろ終わりかな。未使用画像を検索すればまだ出てくると思いますが 、体力的にいっぱいいっぱいです。寛永銭類だけ・・・探さなくちゃ。 |
| |
12月25日【2025年を振り返る】
11月にこの総括記事を書いたのに消してしまいました。記事を再構築いたします。ここに載るようなものは来年の制作日記の冒頭を飾る候補になります。 |
| ❶長郭手覆輪強刔輪厚肉 |
制作日記2025/2/4 |
 |
 |
これはS級の天保通寶です。長径が短く、短径はたっぷりある堂々とした横広形が非常に印象的で、何より重量が28gを超えるので手にした瞬間に銘品だと直感できます。また、天上、當上、寶下ともに強い刔輪が見られます。
メモに大橋師の所有が記載されており、調べたところ大橋譜と天保泉譜の原品でもあるようです。保存状態もよく肉厚は3㎜を超えます。
天保泉譜195
大橋譜P182-2 |
長径48.94mm 短径33.1㎜
銭文径40.4㎜ 重量28.3g |
| ❷長郭手覆輪天上強刔輪肥足仰貝寶(肥尾天) |
制作日記2025/2/4 |
 |
 |
写真写りの色が実によろしくびっくりしました。文字の山が丸く全体に肥字気味になっています。真鍮銭のメモが付いていましたが未使用級の青銅銭ですね。
宏足寶の次鋳と見て良いつくりで、寶足は肥足寶気味ですが2018年4月11日の制作日記に登場している肥尾天としたものと同系統でもあるようです。寶の二引きが仰ぎ、寶底が後ろ足の前で切れている特徴も同じです。
状態が良いので昔の鋳肌が残っていますが砂目はあまり感じません。 |
長径48.23mm 短径32.77㎜
銭文径40.1㎜ 重量18.8g |
| ❸長郭手強覆輪刔輪鋭楕円形 |
制作日記2025/2/4 |
 |
 |
どうです、慶長長小判判みたいでいいでしょう?
ヤフオクの画像で妙に細長く見えた品ですけど、届いてみたらやっぱりおかしな形でした。立派な覆輪銭なのですけど、普通はここまでの覆輪ならもっと短径が全体に広がって、いわゆる横広銭形になるはずなのですが、縦長の卵型なのです。計測値的にはわずかな差なので、この縦長の形状に強い違和感を感じるのは私だけ(+古銭病の方々)なのかもしれません。名称は前所有者が鋭楕円形と名付けたものをそのまま頂戴しました。 |
長径49.31mm 短径32.4㎜
銭文径41.1㎜ 重量20.4g |
| ❹細郭手刔輪陰起文 |
制作日記2025/2/4 |
 |
 |
文字が極細に加工された鋳写し系の細郭手。本来は覆輪刔輪銭なのですが、覆輪らしさはほとんどありません。刔輪も寶下にらしき痕跡がある程度です。目の肥えたHさんならBクラス箱に入れられてしまうかもしれませんが、不知銭なら涎がとまらない私にとっては不知銭として判りやすくて見ているだけで思わずニコニコしてしまう一品です。確証はありませんが、一連の落札品は九州のM師の元コレクションではないかの噂です。ほとんどが役物でした。
百田米美
|
長径48.2mm 短径32.15㎜
銭文径41.6㎜ 重量18.5g |
| ❺萩藩銭進二天大ぶり銭 |
制作日記2025/3/3 |
 |
 |
進二天とは良い名称だと思います。天と寶が進み、銭文全体が緩やかな弧を描きます。とても有名品なのですが、数は少ないので美銭の入手にはなかなかてこずります。
さらに掲示の品は進二天にしては肌のざらつきがなくかなり美銭。背の美しさは抜群です。ただし、側面のヤスリ目はものすごく荒々しい。加えてこの進二天、意外に大きい。49㎜を超える進二天って、相当少ないのでは・・・とはたしか関西のT酸のお話。そうなんだ。
|
長径49.26㎜ 短径32.31㎜
銭文径40.86㎜ 重量20.2g |
| ❻本座広郭細縁銭 |
制作日記2025/3/5 |
 |
 |
美しいから乗せちゃうけど本来はそんなに大騒ぎするような品じゃない。でもこの輪の細さ尋常じゃないよ。
ただし、類似カタログ評価は2000円~3000円だって・・・それじゃ可愛そうだよ。もう一声・・・でも4000円止まりだろうなあ。 |
長径48.05㎜ 短径31.6㎜
銭文径41.4㎜ 重量19.2g |
| ❼水戸藩銭正字背異反足寶小様(赤銅) |
制作日記2025/3/13 |
 |
 |
大和文庫の水戸背異反足寶小様を衝動買いしてしまった。水戸背異反足寶が10000円の初値・・・誰がこんな価格の買うの?馬鹿じゃないの、こんな値段で買って・・・と、お思いになられた方・・・私がその馬鹿野郎です。普通は高くても6000円止まりですね。でも、秋田小様にも負けないような実に美しい鮮紅色で、傷も少なく、背の文字抜けも抜群。背異反足寶でこの色で小様なんて皆無なんじゃなかろうか。背から見ると濶気味で・・・いいでしょ? |
長径47.9㎜ 短径31.75㎜
銭文径39.8㎜ 重量20.6g |
| ❽水戸藩銭正字背異反足寶小様(黄銅厚肉大ぶり銭) |
制作日記2025/4/30 |
 |
 |
赤い小様の水戸正字背異反足寶を入手して背異反足寶のマイブームが来た。今度は黄色くて大きいのが欲しいぞ・・・とばかり、ネットで探しまくりました。こいつはその一枚で肉厚ぶりが楽しい。正字背異反足寶は研ぎが強く横から見ると台形形状になるものが多い気がします。この肉厚は立派だと思います。勢陽譜にはやや肉厚のものが多いと書いてある。でも、砥ぎが強いイメージだけ肉厚のイメージなかったなあ。この背を見ていると揚足寶は同じ作りっぽく見えてきます。 |
長径48.8㎜ 短径32.1㎜
銭文径40.35㎜ 重量24.0g |
| ❾中郭手小点尓(尨字系) |
制作日記2025/4/26 |
 |
 |
長径48.7㎜ 短径32.05㎜
銭文径40.8㎜ 重量22.3g |
|
TICC会場の大和文庫で見つけ手にした瞬間ビビッと電撃が走りました。何度もひねくり回し、躊躇と葛藤、でも手からはなせなかった。小点尓寶は塞頭通と同じ尨字の系統とされます。肌色の印象がずいぶん違ったのですが砂目はごく自然。また、緩やかにうねっている。極印もいい。だから購入を決断。仙人様に相談しなくて怒られるかなーと思いながらの購入でした。八厘会で仙人様に恐る恐る差し出すと・・・う~ん、尨字は肌がもっとぬめぬめする感じのはずだよ・・・との精一杯のやさしい声のお言葉。その瞬間、周囲の人々が目を合わせてくれなくなった気がします。やばい、やっちまったか、お先真っ暗、財布は空っぽ。
しか~し、私には大丈夫との思いがまだありました。それが極印。撮影確認して確信に至りました。ライティングを変えてで確認すると地肌も同じ系統に見えてきました。画像の力は大きいなと思います。 |
| 左:塞頭通・右小点尓 |
當田の右肩に穴がある |
 |
 |
| ❿長郭手強刔輪面背細縁直足寶 |
制作日記2025/8/8 |
 |
 |
ヤフオクで落札。届いた品が想像以上に大ぶりだったので見た瞬間、本座のドリル加工変造の記憶が脳裏をよぎり、一瞬ドキッとしましたが・・・大丈夫でした。
出品名は覆輪強刔輪直足寶でしたが、刔輪が強すぎて面背ともに細縁になっているし、寶足先端は鋳走りで曲がっているので曲足寶あるいは宏足寶と言っても良い品ですね。これはHさんが玉一天に夢中になっている間のお目こぼし品。玉一天は献上してしまいましたが・・・心の穴埋めということで。 |
長径49.55㎜ 短径32.5㎜
銭文径41.1㎜ 重量21.4g |
| ⓫長郭手張点保厚肉 |
制作日記2025/9/8 |
 |
 |
張天保は2品目になりますが頗るの美品ということで気合を入れてしまいました。絶対負けない価格のつもりでしたがやりすぎたかも。でも、手にした瞬間異常な重量に驚き、ちょっと安堵しました。元々大ぶりで重いものが多いこの類ですが群を抜いています。入手出来て良かったあ。
私の所蔵品で不知銭としては2番目の重さ。TMI指数(重量長径率:重量÷(長径×長径)×100)だと1.19でやはり2番目です。この大きさでこの数値はやはり異常。やはり名品です。
※天保収集銭史上2番目の出費です! |
長径49.6㎜ 短径33.2㎜
銭文径41.7 重量29.3g |
| ⓬盛岡藩銭小字黄銅質桐極印 |
2025/10(元記事喪失) |
 |
 |
南部藩の天保銭は書体変化がほとんどありません。しかし、藩鋳でも製作や銅質の変化が数多くあり、さらに民間密鋳によって
それこそ星の数ほどの変化が楽しめます。そんな中で優美な書体で絶対数が少ないこの小字、南部藩の正統派エースとして岩手周辺のコレクターにこよなく愛されていると感じます。
ですから美銭はコレクターに納まっていてなかなか出てこない。しかも絶対数が少ないときたもんだ。小字は銅質で2つ、極印で2つの4種類。しかし、この完集は至難です。 |
長径48.5㎜ 短径32.35㎜
銭文径40.2㎜ 重量23.0g |
| ⓭縮通平二天(本体) |
2025/11(元記事喪失) |
 |
 |
この天保通寶が大和文庫に出たとき、千載一遇の大チャンスと決意し、何が何でもの思いで応札しました。病気ですね。本当、背だけ見たら土佐額輪と見分けがつかない。縮通平二天は刔輪されているものが多いのですが、今回の入手品は刔輪がほとんどない。古来、縮通平二天濶縁という稀品が存在するのですが、それは天上の刔輪が強い大様の品。したがってこの品、縮通濶縁とは名乗れないので縮通平二天(本体)としました。
萩藩銭は個性的な書体が多いのですが、この縮通平二天(本体)は個性がほとんどありません。目立たないけど名品だと思います。
|
長径49.2㎜ 短径32.9㎜
銭文径40.35㎜ 重量21.7g |
| ⓮縮通平二天(刔輪) |
制作日記2025/11 (元記事喪失) |
 |
 |
憧れの縮通平二天・・・それも類似カタログの原品が銀座コインオークションに出た訳ですから気合が入らない訳がありません。しかし困ったことに駿河とほぼ同時発表。二兎追う者は一途をも得ず・・・という諺が脳裏よぎりましたが、目をつぶって「えいや」で応札しました。結果は吉と出て一挙両得?の結果に大満足です。私が欲しがっているとご理解をいただいたようで・・ごっつぁんでした。 |
長径49.3㎜ 短径33.25㎜
銭文径40.4㎜ 重量18.7g |
|
| |
| ❶琉球通寶大字宏貝寶 |
 |
 |
長径49.25㎜ 短径33.25㎜
重量18.6g |
| ❷細郭手覆輪刔輪削頭天 |
 |
 |
長径48.6㎜ 短径32.35㎜
銭文径40.7㎜ 重量20.4g |
| ❸萩藩銭方字細字細郭白銅質銭 |
 |
 |
長径48.95㎜ 短径32.1㎜
銭文径40.5㎜ 18.2g |
| ❹盛岡藩銭小字黄銅質桐極印 |
 |
 |
長径48.5㎜ 短径32.35㎜
銭文径40.2㎜ 重量23.0g |
12月24日【新規入手品】
画像データによる再掲載記事です。❶ 琉球通寶大字宏貝寶
やや赤銅質の琉球通寶・大字宏貝寶です。かつては長尾琉(さらに旧称では肥字)と呼ばれ、珍重されてきたものになります。琉球通寶の大字宏貝寶は大ぶりなものが多いのですが、本品は19g未満と比較的軽量です。
入手経路はおそらくヤフオク。青錆をクリーニングすれば、もう少し見栄えは良くなりそうですが、方法が分からないため手を入れず、ありのままの状態としています。極印は一般的なサ極印です。
❷ 不知銭細郭手覆輪刔輪削頭天
こちらも入手経路はヤフオクだったと思います。別名「貼り合わせ手」と呼ばれ、面は細郭、背は長郭という書体構成のものです。この系統は銅色のバリエーションが多いのですが、本品は茶色に発色しています。不知銭細郭手としては数の多い部類で、初めて見かけたときには狂喜乱舞、つい発狂してしまいました。
天の第一画には加刀が見られますが、名称としてはやや分かりにくいかもしれません。背の花押の袋部分のカーブにも、強い加刀が確認できます。
前述のとおり、発色は黄銅色~白銅質~赤褐色~茶褐色~黒褐色までさまざまで、砂目を感じさせない、ぬめぬめした鋳肌が特徴です。存在数の多さから、やや時代が降るのではないかとも感じていますが、あくまで私見にすぎません。
❸ 方字細字細郭白銅質銭
萩藩銭の方字は比較的入手しやすいものの、美銭となるとやや少なくなります。本品は大和文庫で落札したものだったと思うのですが、記録が失われてしまい、はっきりとは覚えていません。
方字は文字変化が少ないため雑銭に近い扱いをされがちですが、次鋳や銅色替わりなども存在しますので、改めて注目してみてほしいところです。なお、私は白銅質の美銭と聞くと、つい反射的に飛びついてしまう性質があります。あはは……。
❹ 盛岡藩銭小字黄銅質桐極印
この銭は盛岡藩天保銭の初出とされ、銭座で製作された正規品(とはいえ密鋳)ではないかと考えられています。桐極印と変形八つ手極印があり、さらに黄銅色と赤銅色の作が存在しますが、いずれも美銭が少なく、地元人気も相まってコレクター垂涎の品です。
八つ手極印という名称は、天保仙人様などが広めたものだそうで、かつては六出星とも呼ばれていたようです。どうやら黄銅色の方が先発とされ、やや少ないとのこと。
本品は今秋、大和文庫に出品されており、出品価格は4万円前後だったと記憶しています。画像を見る限り意外にきれいに見えたため、洒落半分で応札したところ、7万円ほどでの落札となりました。
背輪上部に湯道欠損があり、背側には汚れも見られますが、傷は少なく、今後化ける可能性を感じさせます。
盛岡小字は、銅色と極印の違いで美品を4種揃えるのが夢で、H酸氏のコレクションを拝見しては憧れを募らせています。美品はすでにコレクターの古銭箱に収まっているようで、道のりはなかなか遠そうです。 |
| |
❶縮通平二天(本体)
(濶縁手改め) |
❷縮通平二天(刔輪)
類似カタログ75番原品 |
 |
 |
 |
 |
長径49.2㎜ 短径32.9㎜
銭文径40.35㎜ 重量21.7g |
長径49.3㎜ 短径33.25㎜
銭文径40.4㎜ 重量18.7g |
| ❸縮通平二天濶縁大様 |
類似カタログより借拓 |
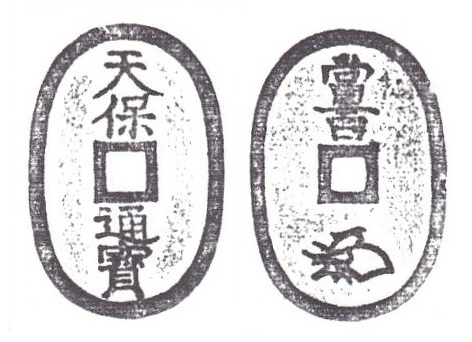 |
 |
 |
| ❹縮通平二天遒勁(平尾天改め) |
 |
 |
長径48.95㎜ 短径32.60㎜
銭文径40.55㎜ 重量18.0g |
| ❺縮通平二天遒勁 |
AI画像 |
 |
 |
| ❻縮通平二天遒勁 |
大和文庫HPより |
 |
 |
12月23日【平二天】
ここからは残された画像をもとにした再生記事です。
萩の縮通平二天は、とても地味な天保銭です。地味なのは見た目だけでなく、書体も寶足以外に目立った特徴がなく、土佐藩の額輪に混じってしまえば紛れてしまうほど平凡です。そのためか、なかなか美品に巡り合えず、未収状態が続いていました。
❶の平二天は『駿河』10月号に出品された逸品です。見た瞬間、その端正な美人顔に惚れ込み、「これは絶対に負けないだろう」と思う入札価格を入れました。ところが、ほぼ同時期に銀座コインオークションにも❷の縮通平二天が出品されていることが判明し、さあ大変。しかもこちらは類似カタログ原品というプレミアム付きです。こちらも目をつぶって高額応札・・・でも、Hさんのお目こぼしで予定価格以下で落札できました。(感謝します。)かくして、私の収集品に2枚の縮通平二天が、ほぼ同時期に収まることになりました。
とはいえ、いくら美品とはいえ、縮通は縮通。実に地味な顔であることに変わりはありません。
ところが、縮通好きで知られる関西のTさんが、この2枚の画像を見てすぐに反応してくれました。曰く、❶の方が刔輪度合いが少ないと。確かにその通りなのですが、正直なところ、そこまで意識していませんでした。❷の方が重量があり、輪の角も立っています。ところが計測してみると、意外なことに銭径は❶の方がわずかに大きいのです。縮通には❸濶縁大様という稀品がありますが、拓本と比較してみると、これは刔輪された上に銭形が縦に長く伸びている上に輪幅が広くなっているものだ、ということが分かります。
なお、縮通平二天には「肥字」とされる亜種が存在します。私も昨年入手できたのですが、収集誌上で用いられている「肥字」という名称に対して、原品を見る限りでは肥字というより削字と呼ぶべきものに感じられます。しかも差異はかなり大きく、花押などはまったく別物です。そのため、平二平尾天や平二天大字など、呼称が迷走していましたが、本日❹縮通平二天遒勁 という名称に改めました。
❹縮通平二天遒勁は瓜生氏の『天保通寶銭分類譜』や❻大和文庫HPにも掲載されており、ある程度は存在しているものと思われますが、そもそも縮通平二天自体が少ないため、縮通平二天遒勁の実見の機会はほとんどありません。
名称変更によって市場が刺激され、類品がぽろっと出てこないものかと、今から手ぐすね引いて待っているところです。
なお、12月に入ってから一時期、AIによる画像修正もかなり試みました。❺平二天遒勁のAI画像は傑作の部類で、非常に見やすくなっています。ただし、AIのコントロールはなかなか難しく、同じ指示でもフェイクのような画像になってしまうことがあり、現在は中断しています。
|
| |
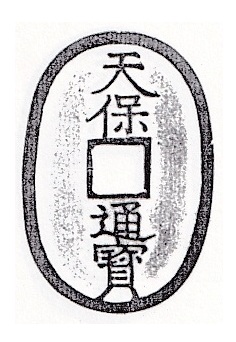 |
 |
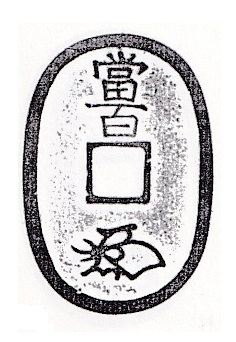 |
 |
 |
| この拓本、左下の刔輪が強いというより、銭の左下が奇妙に膨れている。拓本画像をじっと見ていると分かる。不思議。 |
12月22日【三納天保?】
改めて今度は類似カタログの拓と比較。結論から言うと文字位置が合わなかった。理由は穿の形の違い+銭文径の違い。類似カタログの拓の穿は横長の横穿。三納天保が巨頭通であり得るのは穿が圧縮されていてそのスペースに通頭が収まっているから。寶を合わせると天尾が合わなくなります。
一方、背は當百の位置を合わせると花押の位置がずれてしまう。
縮尺を合わせてしまえばいいのでしょうがそれじゃあねぇ・・・。
筆法だけで見れば良く似ている。天尾、保前点、辵の点と頭、寶珎、當ツなんてそっくりです。一方、保人偏、通頭、百横引、花押はかなり違う。親戚筋ぐらいに該当すると言っても良いのではないかしらと思うのですが方泉處の画像だと鋳肌が実に細かい魚子。一方こちらは穴ぼこだらけ。他人の空似とすべきなのかもしれませんが、捨てがたいなあ。とりあえずは曳尾天のまま皆様のご意見をお待ちしております。
※雑銭掲示板に記したように拓本の長径を3%、短径を1%伸ばしました。
方泉處の写真画像は実物より2割ほど大きく、以前照合したときも銭文径サイズを調整していました。
類似カタログの拓本サイズはほぼ原寸大に近いので、実物も少し小さいのかあるいは拓本が歪んでいたのかのいずれかだろうと思います。本当は長径を2.5%にしたかったんですけど、そこまでの機能がExselになかったので・・・。そうすると拓本文字がほぼ上に乗るだろうことが分かります。郭の下半分が白く出ているので郭はこれでも竹に圧縮されています。また輪の左下が白く出ていて、三納天保の方が刔輪が強いことも判ります。(画像サイズ調整したことはさておいての話。)通頭は上に一画分弱、拓本がはみ出ています。ただ、3%の差ってでかいなあ。4.9㎜の天保通寶で仮に2.5%の差だとしても1.2㎜ほどの縮小。そう考えると2回写し近い差になる。冷静に考えると同じものとは言い難いのですが似ているのは事実ですね~。
|
 |
ヤフオクで落札した古寛永
出品名が勁文垂冠浅冠寶(譜外)でした。
なんだ・・・垂冠ってわかっているじゃないか。確かに寛後足だけ見ると勁文ぽいところあるけど寛冠の大きさや通用が辵から離れる癖、永の食い違いなど、どう見ても奇永。垂冠ならラッキーということで落手。510円なり。ただ、垂冠なのか鋳不足なのかは良く分からないけど・・・損してないよね。
※サイトのデータ復旧をほぼ2日で終えました。南様のお陰で文字情報が拾えたのが大きい。まだ、下の方に作業領域が残っていますが、あとはぼちぼち作業します。
2日間ほとんど寝ていません。仕事もしているしやることはやっています。いや、仕事中に寝ている?・・・ほんと天邪鬼だとつくづく思います。
|
| |
|
|
| |
12月20日【記事消滅事件】
過去最悪級のミスです。最悪級というからにはそれなりのトラブルには何度か遭遇しているのですが、今回はほぼ1年分のデータが復旧できないという点では過去最悪ですね。「1年間の仕事がぱあで~す。」なのです。がっかりです。
サーバーにも上書きしてしまいバックアップも残っていませんでした。昔はGoogleのアーカイブ記事保存機能を使用して復活できたのですが、今その機能はありません。記事保存サイトを探りましたが1年以上前の物しかありませんでした。消失したのは文章データ部分で、画像は全部残っています。私は自分の所蔵品データをHP管理している一面もあるのでとても痛い。「これ、なんだっけ」と、迷子になってしまう。思い出せるほど記憶が鮮明ではないし、それでなくても最近忘れっぽくなった事を自認しています。
まあ、やることが増えたと思い、のんびり記事を書きだしますので、投稿のデータについては改めてお知らせください。完全復活は目指していませんので、私の収集品や珍品投稿を中心に取捨選択をします。
※一週間前のこと・・・仕事をしていて頭が混乱していることに気が付いた。目の前の職員の名前が出てこない、パソコンのパスワードも出てこない。やばい!
記事が消滅する以前に、自分が消滅してしまう恐怖に襲われました。原因は寝不足と血圧・糖尿の薬の飲み忘れ。薬飲んで30分ぐらいしたら治ったけど、この恐怖は親父も味わっているんだろうなあ。記憶も飛んでましたから。やはり寝不足は良くない。最近の連続睡眠時間は2~3時間しかないので死ぬかもしれない。 |
| |
12月19日【鬼が笑うけど夢言実行!】
私の信条は有言実行なのですが、実際にはやりかけのことが実に多くなってきました。古銭の整理をしたいと、もう数年来言い続けていますし、「痩せる」に至っては二十年ぐらい言い続けています。
ずっと成長期だった結果、ついに医者から「病気」を宣告されました。そこで細々と努力を重ね、最盛期から5㎏ほど体重を落としました。しかし、誰も気づいてくれませんし、たしかに見た目もほとんど変わらない。職場の給食は大盛なのでそれを断り、自宅では酒と肉、揚げ物を極力控え、豆腐と枝豆、納豆、サラダ……と、植物性食品のタンパク質で食事を固めてきたのですが、その分、食べる量はぐんと増えた気がします。正直、とんかつとウィンナーが食べたい。
効果といえば、登り坂の歩行速度が少し上がった程度でしょうか。ただ、鋸山の登山道の登りが楽になったのは確かです。体へのダメージが少ない。それに、腹が出すぎると靴ひもを結ぶのもつらい。これはまだつらいので、あと5㎏の減量は必須です。
痩せて素敵な彼女をGETしてやる……のは無理かもしれませんが、痩せたら素敵な古銭をご褒美に(てへへ)というあたりが現実的な落としどころでしょうか。二兎追う者は一兎をも得ず。でも、美人の兎はたくさん欲しい。
さて、私に残された天保銭の目標収集物は以下の通りです。
❶ 萩 進二天強刔輪
❷ 萩 縮通隔輪
❸ 萩 縮通濶縁
※この類は小変化を追い始めると種類が無限大に広がるため、美銭限定で追いかける。
❹ 仙台 広郭
❺ 福岡 離郭濶縁正百
❻ 会津 萎字
※これは最終目標に近い。大広郭などという贅沢は言わないので、美銭が欲しい。
❼ 南部 大字小様
❽ 秋田 色替品(オレンジや黄色)
※面白そうなので欲しいが、なぜか気に入ったものに出会えない。
❾ 南部 小字の美銭
※これは憧れ。
❿ その他 不知の変態的書体のものども……Welcome!
※張天保嵌郭、濶天保、勇文、ペン書様など、挙げればきりがない。
体重が80kgを切ったら自分にご褒美だ。できれば美しく痩せたい。ストレスで痩せる(太る)のはもう嫌だ。昨日は3:30に起こされ、そのまま鋸山まで行って登山。林道口まで歩き、さらに通行止め区間を越えて保田駅まで行った。通算で12㎞くらいは歩いたはずだ。
それでも痩せない……体質なのだろうか。
脳梗塞を起こしそうで、正直ちょっとやばい。
|
| |
長郭手覆輪強刔輪厚肉
天保泉譜195 大橋譜P182-2 |
 |
 |
長径48.94mm 短径33.1㎜
銭文径40.4㎜ 重量28.3g |
| 不知細郭手 鋳写細縁 |
 |
 |
長径48.35㎜ 短径32.3㎜
銭文径40.9㎜ 重量18.7g |
12月18日【朱文字の読解】
この文字は既に解読が済んでいますが、そのことをすっかり忘れて、AIに解読いさせようとちょっと頑張ったのですが・・・まったくだめでした。面側のみ試したのですが、画像の形そのものが新規作成され、文字も鮮やかに「文政」と出てきてしまいます。画像の形は変えないい、色だけ変えると指示を出したのに・・・数回繰り返しましたがだめ。諦めました。ちなみに面右の文字は「長郭手」背は向かって右が「フクリン」左が「ケツリン」です。面左側にも墨で何か書いてあったのかもしれませんが不明。読めた方・・・教えてください。
さて、次なる細郭手鋳写細縁、存在そのものを完全に忘れていました。あはは・・・。雑銭掲示板に10月3日で掲載していたのですが、そのまま行方不明になっていました。そもそも私は今アルバム整理がとん挫しています。収集して撮影して終わりになっている。これではADHD(注意欠陥多動性障害)ではないか?
で・・・ようやく発見しました。原品ならこの朱書文字は「刔輪」と奇麗に読める。画像じゃ無理だな。銭文径はほぼ本座だし、本座にも刔輪はあります。天字が細く加刀されているなど総合的に見て不知としましたがどうかなあ。ちゃんとした収集品だけどB急なのは変わりません。
収集品の整理整頓しなくちゃ。でも寝たいので・・・今は難しい? |
| |
| 不知長郭手張点保・・・極厚肉です。 |
 |
 |
長径49.6㎜ 短径33.2㎜
銭文径41.7 重量29.3g |
9月8日【獅子の目覚め!】
私が張点保を落としたのは皆様ご存知かと思います。2品目なので本当は様子見としたかったのですが、最近あまりに負け続けていたので一発かましたれ・・・とばかり下りる気のない価格を入れておきました。案の定、萎字が買えるトンデモ価格でしたが、どうだ、みんな恐れ入っただろうと吠えてみせましょう。
この手のものはとらさんの好物だと思いますが、相手が下総の虎ならこっちは上総の獅子。たまには目を覚ます姿を天下に示してみたかったのであります。
本日、到着した品を手にしたらあまりの重さにも目が覚めた。なんと29g超え。元々大ぶりのものが多いのは知っていましたがそれにしても規格外です。状態も画像以上によろしい。
ついでに支払金額を改めて確認したときはっと目が覚めたのも言うまでもありません。いや、見なかったことにしておこうっと。銘品ですからね。
※雑銭掲示板の書き込みを見て、とらさんがもっと高く入れようとしていたと知り驚愕。頼むから眠っててくれー。上総の獅子は、呪力を失ってもう腑抜け猫と化してしまった。なお、今月の八厘会は参加が難しいのです。翌日がショッピングモールで大きなイベントの準備もある。私、大喜利担当芸人。外のイベントのお誘いもあって・・・どうにもならない。
|
|
| |
9月4日【九州銭の研究】
関東のA様によると、琉球銭に関する細分類は収集誌上において祥雲斎師が発表されているそうで、調べてみると1994年1月号から1995年8月号まで詳細記事が掲載されているようです。(確認中)
九州銭の研究と称したこの連載は1983年の4月号から連載が始まり、1995年8月号まで中断を含み79回という超ロングラン連載がされたようで、気が付かなかったというか忘れてしまっていてお恥ずかしい限りです。
| 明和期亀戸四年銭小様面背逆製 |
 |
 |
| 張点保(稲陽さんより) |
 |
 |
加治木洪武から豊後元佑、琉球、長崎銭まで網羅しているようで、全く頭が下がります。
なお、この記事はA様の情報と、収集のバックナンバー記事検索をした結果なので、まだ収集誌の中まで確認しておりません。最近は本棚未整理状態に加えまして、本業の宿題も抱えておりまして、さらに職場のコロナ問題、私自身の健康問題、家族介護とてんやわんやの大騒ぎなのです。
もっとも、私自身の健康問題・・・最近は食物アレルギーと蕁麻疹、胆石問題ですけど、食に気を使っていたら全く症状が現れなくなりました。そのかわり、酒断ち、油断ち、肉断ちで全く食事が楽しくない。専ら白米・豆腐・素麺・納豆・枝豆・サラダ生活。ビーガンはこんな生活をして楽しいのかと思う。とはいえ今日は帰宅前にスーパーのパック寿司とカツオの刺身を買ってしまった。どちらも売れ残りの50%引きなので、カロリーも50%OFFということで、お目こぼしを・・・だから痩せないのかしら。胆石が原因でダイエットをはじめ、3日で4㌔ぐらい痩せたのでこりゃ簡単だと思ったら、ピタッと止まった。それどころか、少しだがリバウンドもした。油断ち、肉断ちのせいか生まれて初めて毎朝が便秘気味だ。前途多難です。
ネットでずっとおとなしくしていましたが張点保は暴発してしまいました。さんざんお世話になった稲陽さんの品だから食らいついたのですけどさすがに調子に乗りすぎました。でも、まあいいか。
|
| |
9月3日【南さんの古寛永談義】
最近雑銭掲示板への投稿が増えてきています。それに対する四国のO様をはじめ、四国のK様、笑門泉様、七時雨山様、とらさんなど掲示板の鑑定陣たちの解説が素晴らしい。先日も古寛永LOVEの南様の投稿がきっかけで、解説陣営が躍動しましたね。四国のO様の解説など、もはや目が節と化した私には最高難度レベルの学術論文です。芸術だあ。
南様の投稿画像の中で、なんじゃこりゃと目を疑った画像が2つ。
力永でこんなに細字、仰フ永なものは知らなかった。私のポンコツ頭にはこの書風で仰フ永は放永というDNAが刷り込まれており、ついで何となく仙台?という感覚に囚われてしまって迷宮に入ってしまいました。
2枚目は四国のO様も確定できなかった品。パッと見た印象。
管足の分岐が退き、方尾寛気味。この印象は水戸の宏足寛系。岡山もそうだな。破見寛はどうなんだろう。
永は良く分からない。こんな細字の永は・・・う~ん。。水戸っぽくはないですね。
通はずいぶんいびつ。通頭が進み、辵頭の位置が高く、尾が急傾斜?通が猫背に見えてしまう。なんだろう。水戸、長門勁文、ひょっとして岡山にあったか?
寶はまた強烈な印象。狭玉寶(瑕寶)、小尓。前足短く、無爪貝寶。陰起文かな。イメージは岡山、次いで水戸。
全体に文字は大きくなく印象は岡山、水戸だなあ。
通のイメージを採るか、寶のイメージを採るか・・・う~ん、難しい。岡山に見えてきた、こんなものあるのか?短尾寛に近い気もするが短尾寛になってないし、俯永小頭通瑕寶にも似ているけどちょっと違う。寶が頭でっかちなのは水戸っぽい、。お手上げだ!もう少し時間ください。
寛寶は岡山の俯頭永か俯永小尓・・・その削字ってありえるかな。通の形がねえ・・・一致しないんですよ。岡山俯永小頭通小尓瑕寶なんて分類ないかしら。やっぱ勁永かなあ。 |
| |
| 欠頭通跳尾大 |
 |
 |
| 比較用の大世 |
跳尾大欠頭通 |
 |
| 仮称)跳大縮世 |
 |
 |
9月2日【欠頭通跳尾大の大世3枚】
鉄人から画像を頂戴しました。しかも分類的には欠頭通の類であり、欠頭通跳尾大とすべきもの。しかも3枚も。欠頭通にならなくて跳大になるものは別種で存在します。昨年の6月10日の制作日記にも書きましたが、大世の良い参考文献はほとんどありません。方泉處2号と中世銭史、本邦鐚銭図譜ぐらいかしら。これらにかかわった増尾富房師は金銭問題でなにかと物議を醸した人物ですが、古銭を愛し銭譜を残してくれたという点では古銭界にとってはかなりの偉人だと思います。大世という琉球銭はそもそも存在が少なく、沖縄での出例が皆無であることから、貿易銭、見せ金、安南鋳等様々な夢を掻き立ててくれます。私も集めてはいましたがせいぜい仰大まで。がむしゃらに集めるようなことはしていませんでした。
土台は永楽通寶で、そこに大世の文字を嵌め込むという他にあまり類のないつくり。寛永銭でいえば元和手や永楽手のようなつくりのであり、本当に古い時代の物。それもそのはずで大世王は1454年から1461年の7年間の治世であり、寛永通寶が世に出る170年以上の古銭(鐚銭)なのです。余談ですが明の永楽通寶は中国でほとんど見つからないという謎があります。紙幣流通に切り替わっていたとか、日本等の貿易決済専用貨だとか諸説あるのですが、まだ良く分かっていないようです。
なお、大世には「大観手」「大定手」という絶対的な珍品もあります。大観通寶と大定通寶に大世の文字を嵌め込んだものですけど、私は実物を見たことがありません。その他にも退大とか仰大異書などの珍品もあるようですが、そもそも大世が少ないのでじっくり吟味したこともない。
鉄人も仮称「跳大縮世」という手替わりを発見されたようですが、類品をお持ちの方はいらっしゃるでしょうか。大世の手替わりはまだまだ出てきそうですね。
ヤフオクで寛永の面白そうなものに値を入れていたらまさかの大負け。岡山の長嘯手本体は欲しかったけど、市場価格の倍以上で負けた。
やけっぱちで四年銭小字の面背逆製に高額を入れたらさんざん吊り上げられて下りられた。なんて日だ。頭にきたがしかたない。かかってきなさい・・・と言いたいのですけど・・・でも、少しは忖度してください。見逃してくれー。 |
|
| |
8月24日【古寛永銭は◯◯を見るべし!】
雑銭掲示板に最近古寛永をよく書き込んでくださる方が増えましたね。私はというと終活を考え寛永はしばらく遠ざかっていたこともありすっかり見る目を失っています。古寛永は微妙な文字位置や変化を見つめる力が必要で、四国のO様や関東のA様など超人的眼力を維持されている方々のご意見には感心するやら冷や汗をかくやら。
やはり泉譜と現物を毎日見ていないといけない・・・退化しちゃう、古寛永泉志等の資料は毎日見返す必要があると反省しております。(実行できるかは別ですが・・・。)古寛永はそれだけ難しいのです。
さて、私が古寛永泉志が擦り切れるほど眺めていたころに心がけていたことがいくつかあります。
1.寶足を見るべし!
新寛永はハ貝寶、古寛永はス貝寶とは初心の頃によく言われたものです。例外はありますがこれはすぐにわかりますね。古寛永の存在数は新寛永の10分の1以下だと思いますよ。今は人気はいまいちでも存在数的にはかなり価値があるんですけどね。
2.大きさを見るべし!
斜寶・建仁寺・沓谷を除き古寛永で直径25㎜を超えるものは滅多にありません。水戸銭の一部や高田銭のなかには比較的見つかると言われておりますが、それとて少ない。大きさだけで拾っといて損はありません。
3.背と材質を見るべし!
古寛永の中には特徴的な背を持つものが少なくありません。例外はありますが、頭に叩き込んでおいて損はない。また、吉田銭の背旋辺とか仙台の背濶縁とか珍銭を拾い出すきっかけにもなります。ついでに材質も覚えておけば、長門銭が見つけられます。
| 御蔵銭 |
長門銭 |
高田銭 |
井之宮銭 |
 |
 |
 |
 |
| 極細郭 |
含円郭 |
美制細縁 |
反郭 |
4.文字の配置を見るべし!
水戸銭系は文字が郭側に寄っているか、離郭しているかを見極める。これは星文手系の流れをくむのか、正字系なのかを感じ取る訓練です。寶珎の歪みも見ましょう。これには慣れが必要です。
5.各書体の特徴を探して、泉譜との合致点を見るべし!
|
| |
長郭手覆輪存痕・天上刔輪・仰天・削貝宝
勝手に命名! 玉一天 |
 |
 |
径48.82mm、短径32.94mm
銭文径40.8mm、重量18.40g |
長郭手 覆輪刔輪仰天(覆輪痕跡有り)
|
 |
 |
長径49.33mm 短径33.04mm
銭文径40.8mm 量目18.91g
第36回銀座コインオークション出品
(青寶樓旧蔵品:とら師蔵)
|
不知天保通寶分類譜下巻P16-9
短二天小字 長径47.6㎜ 短径31.55㎜ |
 |
 |
不知天保通寶分類譜下巻P62-37
平玉寶 長径48.55㎜ 短径31.75㎜ |
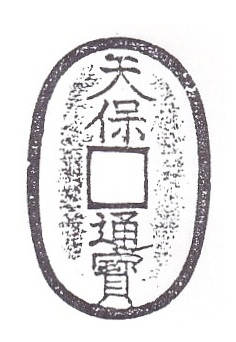 |
 |
8月16日【とらさんの兄弟銭】
お盆期間に入りようやく自分の時間が持てるようになってきました。と言っても今も深夜の活動です。親父様の不調もあり今月は5回も病院通いして休日がぱあ。転倒のけが治療と脱水の発熱・帯状疱疹予防接種、定期健診でしたけど、まあ疲れました。山歩きも休止。この暑さですからね。ここのところ入手品はほぼなし。しかし生活のための出費は痛いほどある。貧乏暇なしを否応なしに満喫しています。
てなわけで「とらさんの入手品」を鑑賞させていただきます。
ネットでも目立っていたので当然ながら追いかけたのですが、私は早々に戦意喪失して、蚊帳の外にありました。おかげさまでお目こぼしにあずかれて・・・。しかし、なかなか立派な覆輪の横太り銭形であり、部分的な輪の加刀・小変化が面白い。逃した魚は大きいものです。とらさんのおっしゃる通り第36回の銀座コインオークションの出品物と兄弟ですね。オークションも初値が8万円でしたので私ははなから不参加でしたが、こうして並べられると立派な覆輪銭でなかなか楽しい逸品です。天の玉だけでなく、面背の内輪の形状、面左側の地に縦に走る鋳ざらい瑕、面輪左側表面の瑕、大頭通、寶の二引きの削字、當ツの形状、寶下・當上の刔輪、背郭の角の形など上げたらきりがなさそう。
勝手に源氏名をつけて「玉一天」と称してみました・・・いいなあ、これ欲しいぞ!
かなり磨輪されていますが不知天保通寶にも類品拓本がありました。ただし、この2つ拓本は同一品の拓の使いまわしかも知れません。拓本に見える磨輪の形、星の位置や外輪の小欠損、文字の傷等に一致点が多いのです。それにしても47㎜台は小さい。本当かしら。上図拓本もたしかに小さいです。次鋳かしら・・・。
掲示板はTさん、とらさん等の投稿でにぎわってます。お題は細郭手の連玉寶。これは奥が深い。連玉寶は古くは肥字とも称されて、覆輪刔輪の横広銭形で黄銅色のもの。異極印は多いけど実際はいろいろ混じっていると思います。もう一度検証するのもいいのですが、私の場合机の上が片付かない。子供の部屋は1日以上かけて片づけたくせに・・・自分のことができない。気力がなあ・・・。
実は昨日林道を13㌔ぐらい歩いた。そこで出会ったバイカーの人。恐ろしく地理に詳しく、道にある変なものみんな知っていました。私が廃道だと探査をあきらめた先まで知っていて、そこに隠れキリシタンの集落がまだ残されていることも教えてくれました。伊藤大山なんて超変な名の山の先の道なき道の存在も教えてくれた。上には上がいるもんだ。
|
| |
古寛永 太細低足寛肥字大様? じゃないね。
仙台大永大様だあ・・・25㎜超だからいいか。 |
 |
 |
| 直径25.25×25.29㎜ 4.5g |
| 秋田広長郭銅替(黄色系) |
 |
 |
長径49.3㎜ 短径32.57㎜
銭文径42.2㎜ 重量18.7g |
| 長郭手 刔輪陰起寶 |
 |
 |
長径48.75㎜ 短径32.25㎜
銭文径41.3㎜ 重量20.1g |
| 不知長郭手 強刔輪面背細縁直足寶 |
 |
 |
長径49.55㎜ 短径32.5㎜
銭文径41.1㎜ 重量21.4g |
8月8日【お目こぼし】
何となく忙しくなり、白内障なのか目も悪くなったな・・・とつくづく思います。
1枚目は古寛永にしては大ぶりの1枚です。平成古寛永銭譜のNo1463該当の太細低足寛肥字という名前で出ていましたがこいつはおおよそ太細に見えない。はじめは岡山の短尾寛風に見えたのですけど、水戸広永風でもありだんだん仙台の大永でもあるような気がしてきました。最近古寛永分類は全く自信がない。誰か教えてください。
秋田の広長郭はほとんどが赤く、たまに茶色があるイメージ。こいつは茶色い中でも黄色に近い品。広長郭は純黄色だったら大珍品で、オレンジ色やピンク色なんてものも探せばきっとあると思います。ただし色は保存で大分変るし、こいつもスキャナで撮ると見た目より赤色が強く出るので正しくは赤味残る黄色もしくは白味の強い茶色とすべきかもしれません。保存が悪いと赤く発色しそうで怖いですね。もし純黄色の秋田広長郭を見つけたら・・・狂喜乱舞ものですよ。
次は浅字で地肌が鋳浚われて砂目がほぼなくぬめついた不知銭。これが出品画像では魅力的に見えました。しかし、輪際がぐりぐり刔輪されているものの、他に特徴があるようで全然見当たらないのです。したがって陰起寶の名称は苦し紛れです。出品名は覆輪刔輪削字寶でしたが意図的な削字はなさそう。輪に向かって傾斜がありぬめっとした地肌、穿内のべたヤスリなど、不知銭と判断できる材料は多いのですが、みんなインパクトがありません。よってBクラスの鋳写し系不知銭ですね。これはヤフオクに出ていたもので、とらさん等のありがたいお目こぼしによってありついた久々の獲物です。ありがたく拝領・・・でも、う~ん、高い買い物だったかなあ。
最後の一枚は大きくて立派な長郭手でした。想像以上に大ぶりだったので届いた品を手にして見た瞬間、本座のドリル加工変造の記憶が脳裏をよぎり、一瞬ドキッとしましたが・・・大丈夫でした。
出品名は覆輪強刔輪直足寶でしたが、刔輪が強すぎて面背ともに細縁になっているし、寶足先端は鋳走りで曲がっているので曲足寶あるいは宏足寶と言っても良い品ですね。
とらさんのご配慮で今回は少し楽しめましたが、さすがにとらさんの落とされた品は違うなあ…と感心します。覆輪は画像以上に良かったですね。また、細郭の面背逆性は気が付かなかった。拝見したいものです。と、云うわけで今夜も夜更かし。
実は親父様が発熱して午後からおかしいので明日は緊急の受診予定。発熱外来の順番取りで早起きしなくちゃ。風邪やコロナじゃなさそうだけど、朦朧としていうわ言しゃべってます。大丈夫かしら。
|
| |
| ❶会津濶縁離足寶 |
 |
 |
長径49.1㎜ 短径32.8㎜
銭文径40.05㎜ 重量19.9g |
| ❷長郭手 鋳写異極印 |
 |
 |
長径49.15㎜ 短径32.45㎜
銭文径41.25㎜ 重量24.3g |
| ❸長郭手鋳写(郭内異仕上げ) |
 |
 |
長径49.1㎜ 短径32.4㎜
銭文径41.35㎜ 重量21.9g |
| ❹琉球通寶小字長足寶(サ極印) |
 |
 |
| 長径49.3㎜ 短径32.95㎜ 重量25.2g |
7月10日【B級の森迷走中】
とらさんや四国のKさん、関西のSさん、侍古銭会のタジさんの収集快走が続く中、私はネットオークション連敗街道を爆走中です。まあ、彼らの品の3分の2ぐらいは私の手中にあったと思えば良いのですが、一つぐらいこっちに運が回ってこないものでしょうか?皆さん病気ですから競り合ったらただじゃすまないし・・・う~ん。
と、いうわけで机に溜まった雑銭?を撮影して憂さを晴らします。
❶会津濶縁離足寶
とらさんと四国のKさんが大物を釣り上げている最中、唯一落せたもの。立派な濶縁ですけど何せ私はこいつは好きすぎてたくさん持ちすぎています。青さびクリーニングすれば見栄えがもう少し良くなるかしら。32枚ロットでこのほかに会津短貝寶や水戸大字、接郭強刔輪などがゴロゴロあって17000円ならけっして損してないんですけどねえ・・・。これをBクラスと云ったらばちが当たる?
お決まりの場所に瑕があり離足寶なんですけど、鋳走っていてらしく見えない。
❷長郭手 鋳写異極印
収集誌で長郭手覆輪の名称で出ていました。状態は美制で好けど覆輪としてはいまいち。王が離貝するけどこれもいまいち。縦長の異極印。手に取ってみると花押の加刀が強く残って鮮やかに出ています。それとちょっと重めですね。Bくらすだけど、不知銭としては分かりやすいほうかな。
❸長郭手鋳写(郭内異仕上げ)
最初の計測で銭文径が41.5㎜前後でてしまい、こりゃ本座銭じゃないかと迷ってしまいました。通尾が短く跳ねるのと離貝寶気味ながらはっきりしない・・・どいつもこいつもパッとしないです。
不知銭判断の決め手は郭内の仕上げ…べったりヤスリです。それだけの品。文句なしのB級不知銭。本座だと言っても通ってしまうと思う。
❹琉球通寶小字(サ極印)
ヤフオクで思いもかけずに落札。2万円しなかった。
発色は今一つに見えますがつくりそのものは肉厚で結構しっかりしています。これもB級といったら申し訳ない品ですけど、手元に複数枚ありますので・・・。こいつはサ極印ですけど、琉球小字長足寶の桐極印は見事な純黄色になる者が多いので探してみてください。25g超過はなかなか立派で、手にずっしりきます。
|
| |
|
7月9日【仮称:不知長郭手長尾天反玉寶】
更新を1ヶ月さぼってしまった。忙しかったからね~。その間、入手はほぼないし、研修担当もフルでやってたし決算作業も大変でした。そんなこんなで寝不足の元凶のHP更新も控えめにしていました。ダイエットのための山歩きもやめられないんです。体いじめてるなあ。
数か月前から蕁麻疹が出るようになって気になっていたのですが、先日ついに顔面が腫れあがってしまいアナフィラキシーショックかもしれない(写真見せたら医師にはそうだと言われました)・・・という体験もしました。幸い、軽症で呼吸困難にならなかったのですが、桃と人工甘味料の一部の品はしばらく食べられなさそうです。
さて、関西のSさんから頂戴した画像です。この品は私も応札していましたが軽く吹っ飛ばされました。ちょっと本気だったんですけどね。そんなわけで画像をおねだりしました。(ありがとうございます。)
| 長郭手 覆輪強刔輪長尾天反玉寶(曳尾天) |
 |
 |
| 長径49.01㎜ 短径32.89㎜ 銭文径40.65㎜ 重量25.11g |
特徴がものすごいのですけど類品は見当たらないですね。
・覆輪強刔輪銭
・削字でやや肥字
・厚肉
・長尾天、跛天
・保前点が降る
・小点通
・反玉寶・長足寶
・面背文字横広
・大花押
パッと見ただけでこれだけ特徴があります。覆輪刔輪で特に天足が大きく開き末尾が長いのと反玉寶であること、當が背が低く横広で大で花押が大きいのが目に飛び込みます。異書とか蝕字という表現も良いと思うのですが、天尾が長いのが他には見られない特徴なので平凡に『長尾天反玉寶』としてみましたがいかがでしょうか。掲示板で仮称しましたがあるいは個性的に『曳尾天』でも良いと思います。(命名権は関西のSさんにありますので仮称です。)泉譜を眺めているのですが、素朴でどこかにありそうな風貌ながら本当の初見品。脱帽です。
※残念ながらCCFに行けないことが確定してしまった。当日は夏祭り。私は主催者です。台風で2回流れ、コロナで5年中断してしまったので準備が大変。8年ぶりなんですけどスタッフ以外の運営協力ボランティアだけで100人以上は来るだろうし、お客さんも1000人以上来る事は間違いないと思う。 |
| |
| 6月8日【最近の獲物】 |
安南寛永 濶縁長通二水永
安南寛永の中ではかなり少ない類です。月刊収集の誌上入札にて入手。直径22.8㎜ほど、重量2.2gの青銅質の安南銭。何の手類になるかは不明。収集1992年4月号42番に類品あり。安南寛永は最後の鉱脈だと思っていますが、おおよそ見栄えがしない。昔はどこの古銭屋にも転がっていたのに・・・。
|
|
|
| 長郭手覆輪刔輪 美制 |
 |
 |
長径49.15㎜ 短径32.55㎜
銭文径40.9㎜ 重量22.5g |
収集6月号落札品。寶前足がやや長いが張足寶とか宏足寶とは言えないかなあ。見た目は本座そっくりで全く普通ですけど、面は輪向かって右側に深い加刀溝が半周走ります。また、文字の周囲と字画の間に丁寧に加刀がされています。
また、極印の主要脈は奇麗な半円を描き、花序は上部に平に並ぶ独特の形です。 |
| 長郭手覆輪 鋳不足蝕輪 |
 |
 |
長径49.40㎜ 短径32.25㎜
銭文径41.20㎜ 重量21.9g |
ヤフオクのフリマで初めて落としてみた品。どきどきでしたが、荷物が届いてよかった。関西のTさんの出品物でした。
面側向かって左と背側向かって右側に油圧不足からくる大きな鋳不足があり、景色になっています。これを景色トピ鋳切れる私は病気かなあ。はっきりした覆輪銭形ながらやや縦長でスリムな銭形。
寶足も直線的で長く変化していますが刔輪というほどではありません。穿内はべったりヤスリです。 |
TICC会場限定抽選販売 中華人民共和国10元龍銀貨
TICC会場で入場待ちの間のアンケートで「抽選で当たる」と書かれていたので運試しで応募したら図らずも当選してしまったコイン。地金型タイプで昨日の銀相場(184.69円/g)だと5744円ぐらいになる。
東京オリンピック1000円銀貨(1964年)は銀地金18.5gなので3416円、2020年の1000円は31.1gなので5744円ほど。つまりこの銀貨、2020年の東京五輪記念銀貨に合わせてつくられている日本仕様です。 |
 |
 |
|
|
| 水戸長永背反郭白銅銭 |
 |
 |
| 加護山銭猿江銭小字写(拝借画像) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
6月3日【反郭と含円郭】
天保通寶に面反郭、背含円郭というものがあり、私の類似カタログ価格は30000~35000円になっているけど絶対誤植だと思っています。古寛永では長門の背含円郭、井之宮の背反郭が有名で、天保通寶は仙台銭や会津濶縁が反郭気味、離郭や秋田小様が含円郭気味になっているものが多いと思います。母銭からそうであるものもあると思いますが、多くは覆輪や砥ぎの工程などで生じたものと私は考えています。
2枚の寛永銭を掲示しましたがじっと見ていると郭の変化の理由が見えてきませんか。
反郭側は凹面、含円郭側は凸面なんですね。長永背反郭白銅銭がこうなった理由は強烈な谷部分の鋳ざらいにあると思われます。その結果、背側が凹面反郭となり、砥ぎの工程で郭の角が強調された形に・・・。
加護山銭は鋳ばりを面から背側に押し出すように折り取る工程があり、背側が凸面になる傾向にあります。同じ癖は秋田小様にもあり、私は寛永の加護山銭と秋田小様には共通性を感じるのです。
長門銭の場合、背の鋳浚いも強いけど面の加刀圧力も強い。
一方、天保通寶の仙台長足寶や会津濶縁の反郭癖は覆輪変形によるものじゃないかしら。外側からの収縮圧力で最も弱い郭の辺の中央部が湾曲変形したのではないかと。ちなみに会津濶縁という名称が確定する前は水戸正字反郭とされていたってご存知でしたか?
福岡離郭は元々中高の肉厚の物が多いので含円郭になりやすい。
まあ、ここに書いたことはあくまでも私個人の仮説。古銭収集者特有の妄想ですから笑って読み流してくださいね。反郭は意図的な加工の可能性はあるけど、含円郭側は銭体の変形による偶然の産物。でも、銭の製造工程を物語る大事な証拠だと思います。
さて、最後の天保銭。怪しいの覚悟で落した品。1500円。贋作なら実によくできているが良く分からない。(他の品はダメだと判断)白い部分はセメントのように固まっていて煮沸しても除光液を使っても落ちません。表面は磨かれてしまっていますが側面は非常に荒々しい和やすり風。穿内も新しいやすり目っぽいけど一応ルールは守っています。極印は桐っぽい陰影ですけど葉脈は不明。
長径49.4㎜ 短径32.8㎜ 銭文径41.23㎜ 重量25.3g
製作は本座異制。肉厚は3.05~3.10㎜と異常。金質が少し硬く、肉厚のわりに重さを感じない。磨かれて角が立っている。側面ヤスリはこんなもの?古いんだか新しいんだか不明。そんなに悪い気はしないが、ごつい。全体になんか違和感があるけど判らないや。
|
| |
5月25日【盛岡藩鋳天保銭考】
八厘会における勉強会の補足です。
大字(初鋳)
初期の大字はあまり製作がよろしくありません。初期は出来上がった銭を火にあぶって鋳砂の除去を試みたようで、焼きが入っている雰囲気があります。砂目は美しくありません。
鋳砂の調合などが上手くゆかなかったのか、型抜けが悪く試行錯誤を繰り返したようです。一方で彫りは面背ともに深くくっきりしています。銅色の発色はいろいろありますが、金質は固く感じます。書体変化はほぼなく、銭文径の変化も比較的幅が小さい気がします。
大字濶縁広郭
鋳造の向上を目指し、職人が栗林座に学んだ結果、安定した品質の銭の生産が可能になりました。これはその直後にできたものと推定しています。赤茶色の銅色で砂目が細かく、外輪のテーパーがややきつくなり台形になって背が浅くなっています。このつくりは四文銅銭にも通じる作りで、文字抜けも良くなっています。関東のAさんが採寸すると50.06㎜あるとのこと。(ちょっと嬉しい。)この製作とよく似たものが銅山手にもあります。
しかし、安定した生産がようやく軌道に乗った頃、山内の密鋳所は手入れを受けて母銭や鋳銭道具を失うことになります。ただし、人的処罰は形式的でしたので、手入れは幕府の手前厳しく行ったものに過ぎないようです。この結果、大字母銭は銭径、銭文径の縮小した小型のものが急遽つくられたようです。
【銅山手について】
盛岡銅山銭の百文“通”用の通の文字と通の文字がそっくり。この点は土佐通寶の当二百の通と平通の通の書体がそっくり・・・と同じなんですけど、後者は萩藩に移籍されてしまった。嗚呼~。
地元では中字と呼ばれています。とにかくバラエティに富んだ天保通寶で25gを超える肉厚のものから15gを切る白銅質末鋳様のものまで様々。銭文径の変化も激しく、これらの件から私は大字より後に短期間で大量生産されたものではないかと考えています。
深字で比較的軽量なものが多い大字に比べて、銅山手は浅字で大小重軽も様々。存在数もまあまあ多いので集めやすいのですが鋳だまりが多く美銭が圧倒的に少ないのです。
銅山手(初鋳大様)
山内の初期銭とされるものは肉厚で銭径、銭文径も大きめ。ただし、テーパーが強く砂目もきちんとあるものが多いので、素朴ながら技術的には初鋳の大字よりもかなり進化しているように感じます。
銅山手 細字(濶縁縮字)
非常に美しい銅山手で、暴々鶏師はこれを栗林座の産で小字に近いものではないかとの仮説を立てておられました。八ツ出極印を長らく探されていたようにも聞きましたが、そもそもこのタイプの銅山手は少なく、新発見に至っておりません。
なお、原品は長径が48㎜を切り、銭文径も最小クラスなので、栗林座で技術を学んだあと・・・手入れ後につくられた・・・と素直に考える方が良い気がします。
銅山手広穿薄肉(称反玉手)
銭径、重量とも最小の銅山手。銅色はかなり白いです。暴々鶏師に対し地元の先輩のK師はこれは「反玉手」だと教えたとか。ありあわせの材料で作った密鋳銭で銭座の技術ではあるものの、浄法寺でもなく、山内とかをも超えた存在なんじゃないかなと思ってしまいます。
恐ろしいほどの磨輪広穿。しかし銭文径が意外にに大きいのが実に不思議です。そういえば反玉寶の室場は山内(浄法寺地区)とは違うけど何に該当するんだろう。同じような民間委託?それとも完全密鋳?
【本炉 山内 浄法寺】
東京の古泉収集家は盛岡藩の天保通寶をこの3つで呼び分けすることが多い・・・と暴々鶏師は苦笑していました。師に言わせれば天保通寶はみんな密鋳で藩が関わっていて本炉も山内もないし、浄法寺も山内そのもの。ただ、浄法寺と呼ばれる一群には得体のしれない怪しいものがいっぱい含まれているとのこと。
本炉は藩が正式に貨幣鋳造を行った場所とするなら、背盛寛永などを公式鋳造した場所ということになるのでしょうが、盛岡藩は幕府に天保通寶はもちろん、銅銭の公鋳造は認められていません。つまり銅銭はみんな密鋳になります。
諸説ありますが、盛岡藩が天保通寶を藩をあげて密鋳した可能性がある地が(山内を除くと)「梁川」と「栗林」。(室場は謎。)
梁川は新渡戸仙岳が濶字退寶と短足寶の拓本(似せ絵?)をその解説文に張り付けてあったようなので、何らかのアクションがあったのは事実だと思います。
私の持論ですけど古泉家は憶測や空想を書くけど、足で稼いで調べる新渡戸のような郷土史家は見聞きしたことをまとめるだけで、たいした脚色はできない。だって古銭の世界のことは知らないから。脚色するのは話し手のほうで、聞き手はせいぜい誇張するだけなんです。
栗林座はのちに山内から技術見学にくることなどからかんがみて本炉とみてよさそうなのですが、天保銭の鋳造は(銅山手と)小字というのが諸説ありますがとりあえず有力そう。
密鋳はみんな山内で浄法寺も山内の一つといいますか、同じ場所。山内は藩の上役が黙認して(実は加担して)密鋳させた場所であり、いざというときはトカゲのしっぽ切りで幕府追求から逃げる算段だったようです。手入れも行われ、鋳銭道具の破却も行われましたが、人に対しては形式的処罰でほとぼりが冷めたら再開という茶番劇が行われました。
収集界で浄法寺という名称の古銭は、藩の黙許とは別に明治時代以降に行われた私鋳であり、流通以外の目的で作られた絵銭、贋造、新作も多々含まれていますので、手を出す場合には覚悟が必要です。
【新渡戸仙岳について】
教育者にして郷土史家であり、古銭については素人で収集家ではなかったようです。彼の著作が地元はもちろん、中央の古泉界でも数々無断引用・論評されているものの、情報の真贋に関する噂が流されては一方的に非難を受けており気の毒です。少なくとも彼には古銭収集家をだまして大きな収益をあげようとする気は毛頭なく、レプリカの記念品(おみやげ)をつくり販売する程度の考えだったと思われます。
東京に彼が作ったレプリカの陶笵銭などを持ち込んだのは地元古銭家のO氏やM氏であり、新渡戸はそれに対してきちんとした対価を受け取っていたわけでもありません。
新渡戸がレプリカの製造を依頼し、見学した岩手県立勧業試験場では南部鉄瓶鋳造のために試験的に鋳造を行っていたらしく、その中に贋作の黒幕のⅠ氏、M氏がいたようです。M氏は後に新聞などにも新渡戸師が贋作者であると直接語っていますのでかなり怪しい中心人物の一人です。
新渡戸は聞き取りした情報に基づいて、岩手県立勧業試験場で盛岡銅山の母銭のレプリカを作成を依頼しその様子も見学したようなのですが、それが『岩手県立勧業試験場での鋳造実験を史実として発表するなど歴史を捏造し、贋作を作って世に広め私利私欲をむさぼった』・・・とされたようなのです。(私の推定。)
かくして郷土史家新渡戸仙岳は古銭界のどろどろした欲望の渦に巻き込まれました。
これらの件は暴々鶏師こと雑銭の会の元会長K氏が詳しくHPに書かれています。中には当時の複数の古銭家(重鎮)が贋作を作っていたという衝撃的なお話も掲載されています。詳しくは 古貨幣迷宮事件簿(書庫2)をお読みください。
暴々鶏師は実際に存命だった新渡戸師の遺族に直接取材を行っていますので、他の方々の証言や憶測記事とは別の側面から見た情報も含まれるので、より高い信憑性があります。
新渡戸師の不幸は複数の地元古銭関係者が口裏を合わせるように彼に罪を負わせたことで、地元古銭家の言葉を信じた古銭収集家の間で、今見てきたようなフェイク話が出来上がっていったこと。古泉用語を知らない点が追及されて、記録そのものに信用が置けないと批判を浴びてしまったことなどです。
コロナ禍のマスク警察よろしく、一方的な正義感に駆り立てられた中央泉界のT氏が詰問に押しかけるなど、いい迷惑ですね。新渡戸は収集界に身を置いていなかったため、守ってくれる人がほとんどなく、歯止めが利かなかったと考えています。
地元に古銭界おいても近年まで憶測的噂が伝わり続けられため、新渡戸師は依然として評価が復権されていません。これはSNSの一方的な拡散のようなもので、小さな噂話が人から人へ伝わる過程で、重大な真実となってゆくようなものだったと思っています。
ただ、近年新渡戸の研究についてはやはり正しかったという評価もちらほら・・・。人物評価も早く復活してあげたいですね。冷静に考えれば古泉家は彼を非難できないとすぐにわかると思うのですけどね。みんな欲目に支配されているから・・・。古泉家と郷土史家はそもそも考え方、価値観が違うから・・・。
暴々鶏師のHP記事内容は(原則転載不可なのですけど、)今のうちに内容を保存しておくことをお勧めします。
また、めんどう師のブログにも新渡戸に関する記述がたくさん資料として掲載されています。とくに2024年11月と9月のお話はHOTですからご一読ください。
南部盛岡藩が天保通寶の密鋳に走らざるを得なかった理由が、❶製造法革新で爆発的に生産の増えた領内の産銅の消費のため、❷銅の需要が頭打ちで幕府のお買い上げが期待できなくなったため、なんてくだりは実に面白いです。
【泉談と展示品】
・新渡戸仙岳が盛岡銅山の贋作販売に関わっていない(意図していない)ことは仙人様も触れていました。つまり彼は被害者。
・盛岡小字の八ツ手極印は仙人様の命名であること。(地元では六出星極印と呼ばれている。)
・盛岡の地はその昔、不来方(こづかた)と呼ばれていて不吉なので改名されたこと。ちなみに「こづかた」は小塚方が語源で、刑場や墓場があった場所。有名なところでは小塚原刑場なんかがあり、骨ヶ原とも揶揄されたそうで・・・。
・日比谷の語源はノリの養殖に使う海苔篊(のりひび)から。海苔篊は昔は竹だったけど今は網。千葉県は黒鯛の食害で最近大変なことになっています。私の実家近辺は昔は海が近くて簀立(すだて)漁や海苔養殖が盛んでしたので何となく言葉は知っていました。実家の隣は海苔問屋さんでした。
・江戸を開拓した鳥越一族のお話・・・後の浅草弾座衛門一派につながるお話ですね。このお話は吉原にもつながり、NHK大河ドラマの「べらぼう」にもつながる。ドラマの中で亡くなって今後の出番はありませんが、伊藤淳史が好演した「かぼちゃの旦那」こと大文字屋市兵衛は、古銭収集家としてとても有名な人。本名は村田元成。初代市兵衛は肥満体で大頭。福助人形のモデルと言われます。2代目はけっして大頭でなかったのですが、自らかぼちゃ頭と喧伝してはやり歌を広めた策略家。交流関係(お客様とパトロン)には福知山藩主の朽木公や古銭大名の姫路藩主酒井公の叔父の日本画家酒井抱一などがいたという超大物です。
・とらさんの南部藩銭のアラカルト(大字・銅山手・小字:反玉寶)はすごい!のひとこと。あんなにきれいな小字はみたことがない。とらさん曰く、小字には赤い色のものと黄色いものがあり、赤いものは八ツ手極印が多く黄色いものは桐極印ばかり。数的には圧倒的に赤いものが多いそうで、鋳造地や時期が違うんじゃないかと・・・。私も色違い、極印違いで小字4種集めたいなあ。夢のまた夢ですけど。
・来月は仙台がお題だそうで・・・う~ん、ほぼもっていませんね。私。
以上。記憶だけを頼りにほとんど書いていますので間違いがありましたらごめんなさい。
|
| |
5月24日【八厘会に出席】
ここのところ忙しく全く休みが取れていなかったので、久々に自由時間。運動不足で体が重い。そもそも全く睡眠がとれていないのが問題です。階段を上ると膝が痛い。
さて、本日のお題は盛岡藩。以下が私の展示品と配布資料です。
| 大字(初鋳) |
大字濶縁広郭(最大様) |
大字(背錫痕?) |
長径49.1㎜ 短径32.3㎜
銭文径41.6㎜ 重量17.6g |
長径49.9㎜ 短径33.6㎜
銭文径41.2㎜ 重量21.3g |
長径48.8㎜ 短径32.45㎜
銭文径41.4㎜ 重量17.7g |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
暴々鶏師がこれが盛岡大字の初鋳品だよと譲ってくださった品。山内銭の初期は、試行錯誤の過程で銭を焼いて喰いこんだ鋳砂を払ったそうで、銭に焼きが入っている(大ぶり)銭だとのことです。これは赤く発色していますが、他の泉書によると初鋳は紫褐色なんて記述もあります。
通常は初鋳の方が大きくて美しいのですが南部藩銭は該当しないようです。 |
自称、日本で一番大きくて美しい盛岡大字。初めて見たときは感動してふるえましたね。
大字ははじめ鋳造が上手くゆかず、栗林座に行って技術を学んだあとに鋳造が軌道に乗ったとの記録があります。これはおそらくその初期の品だと思っています。山内銭の最大様で手本銭もしくは母銭クラス。七時雨山師が絶賛してくれた自慢の品です。 |
赤銅の普通サイズの南部大字。背部に鍍銀のように灰銀色が見えます。南部藩は錫母の技術があると聞きますが実物は見たことがない。ひょっとしたらこれがその痕跡だったりして・・・大字は比較的銭文径にばらつきが少ないので錫母がありそうなのですけどどうかしら。
山内座は鋳造技術が確立した後に手入れを受け、母銭、鋳銭道具がすべて廃棄されます。そのため、通用母による次鋳もあるようです。
|
|
| 銅山手(初鋳大様) |
銅山手(細字 濶縁縮字) |
銅山手広穿薄肉(称反玉手) |
長径49.35㎜ 短径33.1㎜
銭文径41.4㎜ 重量24.0g |
長径47.9㎜ 短径31.8㎜
銭文径40.4㎜ 重量19.8g |
長径47.3㎜ 短径31.1㎜
銭文径40.9㎜ 重量11.7g |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
中京のY師から購入。暴々鶏師にこれは本炉銭ですかと聞くと、東京の人たちは南部を本炉、山内、浄法寺と分けるけどあまり意味がない、堂々とした山内の初鋳だよと答えられたと思います。七時雨山師もいわく本炉銭は小字のみ。あとはみんな山内。浄法寺も山内だけど怪しいのもたくさんあるそうで・・・。
銅山手には上記の大字大様と同じ銅質、製作のものも存在します。 |
|
こちらも暴々鶏師からの購入。師はこの色(黄色と仰る)とつくりを栗林座鋳造ではないか(八つ手極印がありそうだ)と推測しましたが、七時雨山師は栗林座では小字しか鋳造していないとの立場です。
栗林座だとしたら初鋳品なのですが、濶縁で銭径、銭文径が通常みられる銅山手に比べかなり小さいことから、栗林座の指導を受けた後に山内で鋳造されたものではないかと私は思っています。 |
|
暴々鶏師がその著作の中にも掲載していた特異な品。銅山手としては末鋳クラスで背盛寛永にも似た銅質鋳肌のものがあり、暴々鶏師はK先輩から反玉手だと教わったそうです。薄く重量はわずか11.7gしかないのですが深彫で極印もあります。
暴々鶏師は民間の密鋳品ではないかと推定。技術的には銭座職人が作ったものでしょうけど、藩が鋳造に関わっているかは不明。 |
|
|
|
| |
5月10日【水戸なんだか久留米なんだか・・・再考】
天保銭収集家は正字・正字背異・正字背異替の取り扱いにみんな悩んでいると思います。原因は旧水戸銭正字の名称が一定しないこと。はたして水戸藩銭なんだか久留米藩銭なんだかあるいは石持桐極印銭とすべきなのかが実に悩ましいのです。かくいう私もHPの中で全く一定していないのです。
と、言うわけで頭の整理をはじめました。
|
【小川譜以降に水戸正字から除外されたものたち】
旧水戸正字類(現本座異制 秋田本座写)
旧譜には水戸正字背反郭等と呼ばれ掲載されていました。黄銅質で本座とほぼ同規格、製作(砂目と砂磨きの跡)が粗いもの。現在は本座異制とされています。
会津濶縁 会津濶縁離足寶など
かつては水戸正字背異濶縁の中にありました。黄銅質が多く背異替の書体。現在は会津濶縁の類です。 |
❶背異替 → 久留米
昭和40年頃に九州出身の高木氏の報告を受けて小川師、瓜生師が調査を行った結果、九州地区に背異替が多数存在することなどが確認されて久留米藩説が浮上したそうです。 |
| 分類の要因 |
銭種 |
石持桐 |
普通桐 |
赤銅質 |
背異替(花押)
九州に多く存在 |
正字背異替 |
◯ |
◎ |
あり |
| 正字背異替濶縁 |
◯ |
◎ |
あり |
|
❷正字 正字濶縁 → 久留米
背異替には石持桐極印銭が見られるため、石持桐刻印=正字=久留米藩説が確立しました。本座をベースに覆輪写しをしたもの。
|
| 分類の要因 |
銭種 |
石持桐 |
普通桐 |
赤銅質 |
| 石持桐極印 |
正字 |
◎ |
◯ |
あり |
| 正字濶縁 |
◎ |
◯ |
多い |
|
❸深字 → 水戸?
石持桐極印ですけど極印形状が異なる。全くの新規母銭銭からの鋳造。祝鋳かもしれない大型銭が存在する。大型銭の存在もありこの銭は江戸で作られたのではないかとの予感がある? |
| 分類の要因 |
銭種 |
石持桐 |
普通桐 |
赤銅質 |
| 石持桐極印 |
深字 |
◎ |
◯ |
多い |
|
❹正字背異 繊字 → 水戸
花押の形状、製作から同炉であろうと推定されました。
また、天保仙人様が大川天顕堂師から譲り受けた恩賜手天保は背異でした。つまり背異は異替とは別系統であり、恩賜であれば親藩の出自は必須。水戸藩の可能性が高まりました。
ただし、背異には銅質製作が正字に近似するものが多数あり、いろいろまざっている可能性があります。 |
| 分類の要因 |
銭種 |
石持桐 |
普通桐 |
赤銅質 |
背異(花押)
黄銅質
恩賜手の存在 |
正字背異(黄銅質) |
未見 |
◎ |
ー |
| 繊字 |
未見 |
◎ |
? |
|
❺正字背異濶縁反足寶 揚足寶 → 久留米
背異の花押形状ですけど、極印の形状や銅質・製作から見て石持桐極印に合流させても良いと思います。この類はいろいろ混じっているかもしれません。 |
| 分類の要因 |
銭種 |
石持桐 |
普通桐 |
赤銅質 |
製作・極印形状
背濶縁の形状 |
正字背異濶縁反足寶 |
未見 |
◎ |
あり |
| 揚足寶 |
未見 |
◎ |
あり |
|
❻正字背異(黄銅質以外) → 久留米
❷の正字との製作類似性は確かにあり、同炉銭とする方が自然だと考えます。
|
| 分類の要因 |
銭種 |
石持桐 |
普通桐 |
赤銅質 |
| 背異(花押) |
正字背異(黄銅質) |
未見 |
◎ |
あり |
|
と、ここまで考えながら書いてみてあまりの論理の破綻に眩暈を覚え思考を止めました。結論から言うと久留米と水戸を両方立てて分類をするのは無理で、一度原点に戻り水戸藩で統一する、もしくは石持桐銭と石持桐手に分けて考える・・・それしかない。久留米藩説については現物が見つかったとはいえ、お金は流通するものだから必ずしも大量にあるから鋳地とは言えないのではないかと結論付けようと思ったのですが・・・。とらさんから衝撃的なメールを頂戴しました。から |
(略)久留米の天保銭は、青寶楼先生が思い付きで言い出し、瓜生氏がのっかったようですが、結局新しい発見など全く出ず、うやむやになり消え去ったものと理解していました。(略)
瓜生氏も平成7年9月25日発行の天保通寳銭の研究第8回配本306ページでギブアップしています。
まず、禁門の変前に久留米領での鋳造など不可能であの書付は偽書若しくは、単なる願いに無責任で何の力もない公家連中が権限もないのに許可したものではないでしょうか。脅されるか、金さえもらえば何でも書いた連中ですから。大体、同年8月の政変で長州が都落ちする前のめちゃくちゃやってた時で、孤立した長州と福岡、久留米が組むなんておかしな話です。
正字・正字濶縁の鉛を多く含んだ質の悪い銅。天狗党と諸生党の内乱などで廃棄された銅の大砲や焼き討ちで灰燼と帰した堂宇、梵鐘などに鉛を加えて質の悪い天保銭を鋳造したとの記録にも合致します。何よりも久留米でない証拠は石持極印では無いでしょうか。同じ銭に石持極印と桐極印があるという事は2件の請負があった証拠です。
会津と水戸両家で請け負っていた釜屋、水戸家のみの川崎家、そこから想像すると、桐極印が釜屋、石持が川崎家となります。水戸、会津、秋田、盛岡、仙台、薩摩、福岡、土佐、大なり小なり伝承や資料などが残っています。庶民の口に門は立てられません。何十年も探しても久留米には鋳銭の痕跡は見つかりませんでした。それが答えだと思います。
九州で石持極印が多数あったというのも眉唾のようだし、現に九州地方の雑銭を購入しても石持極印などありません。また、あの怪しい書付があった禁門の変の前の時代、水戸家は佐幕派の諸生党が力を持っていたはずです。(略)理路整然とした板井氏は早い段階で見切り、深くかかわった瓜生氏もギブアップ(略)
水戸で石持極印を鋳造していたとされる元になった枝銭の拓本、銭文径が41.3mmある、桐極印の正字濶縁の母銭のおまけの板井氏の手紙など添付します。(略)
|
いや~、全くもって恥ずかしいのですが初めて(改めて?)知る内容ばかり。天保通寶銭の研究をよく読んでなかったこと(流し読み?物忘れ?)に尽きます。私は小川青寶樓師の主張・・・「昭和40年頃に九州出身の高木氏の報告を受けて小川師、瓜生師が調査を行った結果、九州地区に背異替が多数存在することが確認されたという記述を信じ切っていました。九州に石持桐系の天保銭が多いという話は天保仙人様からもかつて聞いておりましたのでもう疑う余地がなかったです。
しかし・・・書体や製作に従って水戸藩と久留米藩を割り当てようとするとどうしてもどこかに矛盾が生まれてしまう。深字大様の出現経緯等を調べると深字は江戸の匂いがプンプンしてくるのに石持桐だし、銅質が異なりすぎる繊字と背異の類似性もしかり。恩賜手に繊字が含まれるなら繊字は江戸にするのが自然だし、しかし背異の銅質があまりにも繊字と違い過ぎる。これらを全部他人の空似だと片付けてゆくことには無理がある。つまり、根底になった仮定に無理があったわけで、私は30年間以上も振り回されて悩んでいたわけでして・・・。青寶樓師が新訂天保銭図譜を発表されたとき、あまりに大胆な銭籍の異動についてゆけなかったのも事実。この点については泉界でも賛否両論、喧々囂々、侃々諤々だったようですが、石持桐の下りだけは天保泉譜にも別項仕立てであったので最新の研究かと鵜呑みにしていました。幽霊の正体見たり枯尾花。
こうなると水戸正字類に亜鉛が大量に含まれていたとする瓜生氏の資料も嘘っぽく思えてきた。
とら様ありがとうございました。30年間以上の頭の中のもやもや・悩みが解消しました |
|
| |
5月7日【贋作母銭が怖い】
某国発の贋作母銭が今、大量流入してきている。鉄銭母もそうだが琉球や天保通寶も多い。糸を引いているのは多分日本人なのでたちが悪い。その昔は泉譜をそのままコピーして来たような幼稚な作だったんですけど、進化してます。最近目に付くのが天保通寶の本座母銭のコピー品。理由はおそらく数多く残されていて入手も楽だし、古色もあまりなくやすりの仕上げがほとんどないので、真似しやすいのです。先日、肥郭の母銭にひっかかったからなおさらに怖くなってきました。私は本座中郭はもちろん、長郭の母も細郭の母も持っていません。ですから私のこれから書くことはもやもやした妄想(疑問)だと思ってくださいね。
❶天保通寶の母銭は中見切りで作られたはずじゃないの?
天保通寶の母銭は中見切り鋳造でなければおかしい。と、すると化粧砂は面背に使われる。となると、面背ともきめ細かい肌になるはずなんだけど・・・最近荒い肌の未使用銭がやたら多くなった気がする。怖いなあ。
❷やすり掛けの後に砥ぎ工程があるんじゃないの?
砥ぎは一番大変な工程で時間も労力もかかったそうです。砥ぎは銭を平らに並べて砥石で表面を研ぐ平砥と、鉄串に挿した銭の側面を砥ぐ丸目がありました。穿内も小さな砥石で砥がれたらしい。鋳張りはこの工程で除去され鋳肌も整えられるはず。なのでごつごつ感のある未使用肌の母銭には違和感を感じてしまう。
しかし・・・砥ぎが強いと文字がつぶれて母銭として役に立たなくなるからもしかすると母銭は強い平砥ぎ工程はなかったのかもしれない。そうなると荒々しい肌の母銭や鋳張りが外に飛び出たようなものもありえるかも。なお、本座広郭末期は平砥工程が省略された結果、荒戸石の条痕(砂磨き?)が残る天保銭が量産されたようです。でもこれはあくまでも広郭の話。よく良く分からないから母銭は怖い。
❸磨きの工程は?
最終工程にはわら摺りがありました。木炭の粉をまぶし筵(むしろ)の上でこすり上げると見事な黄金色になるとのこと。ただし、鋳銭図解を見る限り他の工程で見られる筵より小ぎれいで整っていますし、小さい。これは私の想像ですが・・・木賊(とくさ)を乾燥させたものは古くから研磨剤として使用された歴史があり、錫母の研磨にも使われたらしいので、これはほぼ木賊に間違いないと考えています。いくらなんでも磨きぐらいは母銭にあっても良い気がするんですけどね。どうなんでしょう。何を基準に選んだらいいのか。やっぱわからん、だから怖~い。みんな贋作に見えてきた。
と、言うわけで臆病な私は今は手ずれ感のある本座母銭しか手を出せない。いや、それも失敗したばかりだから無理かも。そもそも水戸もの風の未使用肌にはできるだけ手を出さないようにしている小心者。
本座長郭・中郭・細郭の母銭の仕上げ工程と間違いない母銭の選び方について詳しくご存知の方・・・教えて下さい。
なお、今ネットに出ている色の黒っぽい寛永通寶の母銭・・・みんな怪しいです。そのうち色を進化させてくると思うけど・・・こちらも怖い。
※関東のHさんの中郭・細郭母銭のコレクションすごいです。墨書も多彩。おそらく先輩収集かからの譲渡品だろうなあ。あの文字が細く、肌の未使用に近い母銭、もう一度拝見したいものです。
四国のKさんの天保通寶は中郭手でしょうかね。印象ですけどどっちでも良い感じ。
※中郭母銭の贋作(変造)の有名なものにU師の中郭母があります。本座広郭の郭内を中郭サイズに削ったもので、作ったのはU師ではないのですが、それを大量に掴まされたM師から買い入れ転売したことから大事件になりました。母銭の郭内は普通は砥石仕上げなので、強い条痕が残っていたら怪しいと思ってください。なお、本座中郭通用銭や秋田細郭通用銭の郭内には必ず鋳造時の鋳肌が残っています。全くないのは怪しい。
※余談になりますが、このページの冒頭を飾る不知狭足寶の白銅銭は私には母銭にしか見えないのです。文字は繊細で銭文径も大きく、銅質も異なる。次鋳母で良いんじゃないのかなと思うのですが、背郭が甘いのかなあ。この母銭、見たことないから判らない。仙人様、今度本座の真贋の味方と合わせて教えて下さい。
|
| |
5月6日【文銭に母銭あり】※数年前全く同じような記事を書いてた、恥ずかしい。
関東のAさんに古寛永を判定して頂くと、母銭にしか見えない大型美銭の多くが初鋳大様の通用銭と判定されます。それだけ母銭の判定はシビアなんですけど、私はそれで良いと思います。正直言うと新寛永の文銭は市場に多すぎます。つまり、判定がかなり「あま~い(推奨:井戸田潤風)」のです。
穿内が整っていないのは論外ながら、みんな穿内仕上げがあるから、ときにはきれいだからだけで判断するから自称母銭が量産されてしまう。
私は市場に出ている文銭の母銭の半分以上は母銭ではないと感じています。では何かというと、少しきれいな通用銭がほとんどだと思っています。もちろん、これは私の見方であって、絶対に正しいとは言えません。そもそも私は母銭鑑定の自信がないのです。
金属は鋳写すと縮みます。鋳写で作られた密鋳天保通寶は0.6㎜ほど銭文径が縮みます。したがって天保通寶の半分ほどの大きさである寛永通寶の母銭の内径は通用銭より0.4~0.2㎜ほど大きいはずです。
しかし、それだけでは母銭であるとの判断はできません。それには文銭ならではの事情があります。
文銭は日本のすべての鋳造通貨の中でも、最も均質で出来の良い通貨です。一般的に母銭は通用銭より出来が良いはずなのですが、その差が少ないことがひとつ。それに加えて文銭には外径・内径の異なる母銭、通用銭が多段階にわたって存在するのです。
古寛永の時代、母銭は通用銭の出来の良い大きくてきれいなものを加工して鋳写していました。実は文銭もそれに近く、原母から複数段階にわたって写された母銭を駆使して大量生産されたものだと思われます。
母銭の他に母銭の2サイズの上の母の母の母銭とか、母の母銭、母銭サイズの通用銭、それらを磨輪した細縁銭、さらには手本銭としか思えないものとか、使い古した母銭が再利用されないように傷つけた廃棄母銭とか、出来が悪くて母銭として採用されなかった格下げ通用銭(母銭)など・・・まあ悩ましいこと。
鑑定が難しく、あまりに誤りが多いことから「文銭に母銭なし」とは、良く言ったものです。
でも、鋳物ですから中には間違いない母銭も存在するのです。 |
| ❶正字背文鋳浚母銭 |
平成17年銀座コインオークションより |
 |
 |
私が初めて間違いない文銭の母銭だと感じた品。仕上げが違うし、金味も違う。文字もとても繊細。これを見てしまうと一般に母銭とされているものは、おもちゃのように見えてしまう。大分の坂井師によるとこれは母の母の母銭ではないかとのこと。もちろん、私のものではございません。 |
| ❷細字背文鋳浚母銭 |
外径25.22㎜ 内径20.80㎜ |
 |
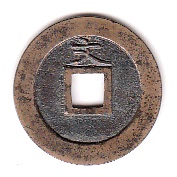 |
非常な繊細な文字で各所に鋳浚いや加刀の痕跡が残る間違いのない母銭。繊字と見まごうほどの細い文字にも勢いがあります。銅質も練れが良く、文字の大きさなど通用銭とは一味違います。背の濶縁ぷりも見事でしょう?
|
| ❸中字背文純白銅母銭 |
外径25.3㎜ 内径20.6㎜ 重量4.2g |
 |
 |
2021年の駿河に出品された純白の文銭。母銭は通用銭と銅質が異なるものが散見されるのですが、あるという噂は聞いていたものの、この純白の色の母銭は初見でした。地染めもしっかりしていて、特別な母銭に思えます。ここまでは絶対母銭文句なし。 |
| ❹中字背文大型母銭 |
外径25.65㎜ 内径20.6㎜ 重量4.1g |
 |
 |
母銭とはいえ25.5㎜を超えるものは珍しく、25.6㎜を超えるこの品は大型母銭と言えます。重量も4.1gとなかなか立派。全体的に黒く発色していますが、文字の際に地金の銅色が残っています。数値的に母銭に間違いないと思うけどいまいち美しさに欠ける気もする。 |
| ❺繊字背狭文白銅大型母銭 |
外径25.65㎜ 内径20.4㎜ |
 |
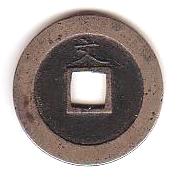 |
収集の誌上入札に思わず応札してしまったもの。初値が高かった(26000円)ので、さぞかし白いのだろうと興味津々でしたが、到着した品はさほどでもない。しかし、計測したら外径が25.65㎜もある大型母銭でした。ただし穿内の仕上げは雑です。これで本当に母銭なの? |
| ❻繊字背小文母銭格下げ通用銭(面偏輪) |
内径20.2㎜ |
 |
 |
つくりは母銭、彫りも深い。。母銭として作られながら、背文字の鋳出し不良のため、通用銭に格下げ磨輪されたものではないかと推定。面側が偏輪してしまっている。あるいはこれが原因か。
母銭のなりそこない通用銭。でも母銭として使用された可能性も完全否定できません・・・。
|
|
❶は完全無欠の堂々たる母銭。 ❷も風格がある。 ❸は加刀痕跡こそないけど材質の違う特別な母銭。 ❹は別格に大きいもの。ただし、内径は❸と同じ。 ❺も繊字としては巨大。でも製作はやや雑。
❻はできの悪い母銭のなれの果て。母銭としては使われなかったと思いますが確証なし。これで母銭と言われても困るかもしれないけど、母銭のつくりには違いないと思います。
以下の特徴のいずれか2つ以上あれば母銭かもしれません。
1)内径が大きい。一般的な同じ種類の通用銭サイズより0.2㎜以上大きいこと。
2)背の彫が深く郭がきれいな方形であること。
3)文字が繊細で鋳だまりなどの欠点がほぼなく、ときには加刀が複数見られること。
4)材質の練れがよく、肌のきめが細かいこと。
5)郭内に仕上げがあること。
6)銅質が違う、肉厚で重い、径が特に大きかったりと他にない特徴が複数あること。
文銭には錫母銭がないと・・・錫母の存在を否定される方が多いと思います。一方で文銭の錫母は確実にあると考えている収集家や実物とされるものを保有している収集家もいらっしゃいます。見たことも聞いたこともない、いやあったはずだ・本物だ、贋物だ・・・と、この件は収集誌上でも大炎上したことがありました。私には真偽・真贋は分かりませんが、古寛永の末期には錫母の技術が確立していたいたと思われること、文銭の規格の均一性、内径格差の刻みが0.2㎜程度ととても細かいところなどからみて早い段階で複数回の錫写しがあってもおかしくないのではないかと考えています。でも、真相はわかりません。
※母銭と通用銭は作り方が違います!
母銭は中見切り(鋳型の合わせ目が厚みの中央)で表裏ともに化粧砂を使います。一方、通用銭は片見切りで化粧砂は表側だけ。鋳型の合わせ目は背側に偏ります。中見切り+両面化粧砂使用で作る母銭は面背とも文字くっきりで繊細。肌もきれい。一方片見切りは背がぼやけるし、ずれやすい。ただし、鋳張りが背側に薄く偏るからやすり修正は簡単。(背ずれになります)一方、中見切りは鋳型合わせのずれが致命傷になりやすい。厚みの中央部でずれるわけだから郭内にも周縁にも銭の厚みの半分の段差ができてしまうため、大きく磨輪するしかありません。面背のどちらかが大きく偏輪するし、母銭としては小さくなるから格下げして通用銭にするしかない。❻の面ズレはその結果のエラー。だから廃棄母も出やすかったんじゃないかしら。 |
|
| |
 5月4日【銀座は錫母の技術を知っていた!】 5月4日【銀座は錫母の技術を知っていた!】
これまで錫母の技術は金座のみが独占し、銀座はその技術を知らなかった・・・と、散々書いてきましたが、どうも雲行きが怪しくなってきました。いえ、間違いだと判明しました。
銭座はもともと金座の管轄。幕末において金座は天保銭と文久の草文・玉寶を所轄し、銀座は四文真鍮銭と真文を管轄しました。文久の真文は御蔵銭のような鋳座頼変化が多く錫母の存在が確認されていないこと、金座と銀座がライバル関係にあったことなどから、「銀座は錫母の技術を知らされていない」という俗説が生まれたのでしょうか?私はその話を信じておりました。しかし、「天顕堂大川鐵雄氏遺稿 銀座工夫人・勝間孝之助書留」(三貨堂 小林茂之著)を拝読するにあたり、少なくとも明和期6年銭において錫母が使用されていたのは文献資料、並びに現物資料からもほぼ確実なようです。大川氏遺稿以外の実物資料として、2024年7/3に病人のひとり言と称し、錫ペストの事を記していましたが、文政期正字(銀座所轄)の表面のぶつぶつが錫母銭の腐食によるものと自ら書いているのに、何にも疑問に感じていなかったのは、お恥ずかしい限りです。
文久の深字と直永が浅草橋場の銭座らしいことが記されているので、技術の継承がされていなかったのは銀座所轄のうちこれらごく一部の銭座だったのかもしれません。
※あれ・・・天保泉譜には本座広郭は橋場銭座だって書いてある・・・迷走してます。
私の似非知識
鋳物師は渡来系の技術集団でその統括は京都の下級公家真継家(忌部氏→齋部氏)が統括したといわれます。渡来人の勢力拡大を恐れた幕府は身分を低く抑える代わりに職の独占特権を与え、移動の自由も認めたものと思われます。そのため鋳銭事業などは全国各地に派遣が行われ、藩は違うのにそっくりな銭が出来上がることになったようです。密鋳もあったのでもちろん秘密絶対厳守でした。ところで江戸においては真継家と異なる鋳物師集団が生まれました。それが矢野(浅草)弾座衛門。身分が低かった彼らの居住区域は農耕に不向きな浜辺に追いやられていましたが、それが火を扱う鋳物師には好立地。弾座衛門は鋳物以外に皮革加工、芸人、遊女等を統括したとか。同じ身分階級にされたとはいえ公家系列の真継家とは出自が全く異なるため、水と油。技術交流はおそらくなかったでしょうね。以上知ったかぶりです。
|
| |
5月1日【ノギス反省記】
ノギスの使用は寛永通寶の内形計測が私のはじまり。新寛永通宝図会で細縁銭の存在が発表されたとき、実家の近くの金物屋でノギスを購入しました。長さは20cmほどで金属製、メーカーはミツトヨ。4000円ぐらいしたような気がします。目盛りは0.05㎜刻み。これでずいぶん練習しました。不思議なもので毎日のように計測していると0.2㎜ぐらいの差が見えてくる。幻覚か?あの頃は目が良かった。
ただこのノギスには欠点がありました。少々長く重いのと、金属製の刃先が太く丸く文字にかかりにくく、銭文径計測にはむいていない。その結果、何度もはかり直すことになるので古銭に小さな傷をつけてしまうのです。
2代目は八厘会の席で購入したプラスチックデジタルノギスPC-15JN、ミツトヨ製。長さは20cmほどですが目盛りは15cmまで。古銭を測るのには十分過ぎる長さ。軽くて扱いやすく、古銭も傷つかない。最小表示は0.1㎜。金属製の初代より刃先が少し長いので銭文径もまあまあ測りやすい。省電力機能もあり、時間が経つと電源が切れるので電池切れの心配もない。これは便利でした。欠点は目盛りが大雑把なのと刃先が摩耗しやすく、柔らかく、長く使っているうちに誤差が出始めました。周囲の人が0.01㎜刻みなのに私は0.1㎜刻み・・・しかも誤差含み。うーん・・・というわけでネットで3代目格安海外製無名デジタルノギスを購入。金属製で0.01㎜刻みで値段は2000円しなかったのですが・・・これはすぐにお蔵入り。刃先の動きが軽すぎて表示が安定しないのです。以前の金属製ノギスは目盛りが測定位置で固定できたのにこれはゆるゆる動いちゃう欠陥品。外径計測は問題ないけど銭文径は揺らぎが激しく参考値にしかなりませんでした。何せ0.01㎜刻みなんで測っているそばから目盛りが動んじゃ使い物にならない。
日本のノギスシェアは世界の3割を占めているそうで圧倒的みたいシンワ、ミツトヨ、新潟精機のシェアが高いとかつて聞きました。ですから買うなら日本製ということで、4代目はまたミツトヨのデジタルノギス100㎜ホールド機能付き商品番号19974・・・うーん、今廃盤なのかも。
ノギスはカーボン(プラスチック)と金属製(ステンレス)があり、精密測定なら金属、古銭を傷つけたくなかったらカーボン。ただし、カーボンは0.1㎜刻みが最小単位。
長さは古銭なら100㎜あれば十分。表示形式はアナログ、ダイヤル、デジタルの3つ。アナログは目視、ダイヤルは極小単位はメーターで読める・・・ただし高価、デジタルは便利だけど電池消耗あり。でもデジタル推しですね。本音を言うと0.01㎜はいらない。でも0.1㎜より精度は欲しい。カーボン式100㎜で0.05㎜単位があれば即買います。それと、デジタル買うならオートオフ機能が絶対ついていた方が良い。と、いうのも私のノギスにはそれがなく、電源を切ったつもりが上に物を置いたりして電源が入ってしまうことがしょっちゅうある。電池が切れかけてくると測定値が狂うのです。精密機器なので専用ケースに常時しまえばいいんですけど・・・ぱなし君なので、私。電池切れると頭に来ちゃう。自分が悪いんだけど。
刃先は細い方がいい。だから小型ノギスの方が良い場合が多いのです。刃先が平行に近い丸っこい奴はやっぱだめです。私の手動ノギスは輪と文字の間に刃先が垂直に入らないことが多いので・・・誤差が出ます。したがって私の測定値のうち、銭文径はあてになりません。ところでショッピングを検索するとお世話になっているミツトヨがほとんど出てこない。安い海外粗悪品に押されちゃったのかな。余計なことだが心配になります。以上、ひとりごとです。 |
|
| |
4月30日【今、背異反足寶が面白いぞ】
 一応水戸藩銭としていますが背異反足寶は間違いなく石持桐極印の系統だと思われます。それは極印の形状(右)を見れば合点がいきます。右の極印は❶の極印。頭が大きくて石持の玉が見えてきそうじゃないですか?すべての背異反足寶がこうだとは言えませんが、これは大きな証拠になります。 一応水戸藩銭としていますが背異反足寶は間違いなく石持桐極印の系統だと思われます。それは極印の形状(右)を見れば合点がいきます。右の極印は❶の極印。頭が大きくて石持の玉が見えてきそうじゃないですか?すべての背異反足寶がこうだとは言えませんが、これは大きな証拠になります。
問題は背異と繊字。繊字は黄銅質。背異は黄色いものも多いけど、赤黒いものも散見されます。繊字はもちろん、正字背異と背異濶縁(反足寶)には石持桐極印は未発見とされているのですが、先に申し上げたように背異反足寶は石持桐極印だろうなあと思う次第。正直言ってこの類、私はほとんど注目してなく・・・と、いうより無視してました。赤い正字濶縁は大好きなのに、この待遇差は何なんだろう。偏食?
それが❸を入手して考えが変わった。小さくて実にかわいい。秋田小様みたい。こんな発色があるんだ。45㎜台の秋田小様はMさんに乞われて譲ってしまったけど、こいつは譲れない。市場価値は45㎜の秋田小様の10分の1ほどなんですけどね。勢陽譜(天保泉譜)では正字背異濶縁が5位、正字背異反足寶が7位、正字背異反足寶濶縁が4位だって!小様は類似カタログに載ってた・・・8000円~10000円、結構評価高いんだあ。でもそれにしても❸はいいでしょ。
※今朝は4時過ぎから活動している。7時には家を飛び出し快晴の山へ。15㎞ほど散策して2時に帰宅、そして庭の草刈作業・・・そして古銭で遊んでいる。死ぬかもしれない。でも楽しい。
キョンは大繁殖している。今日は2回出会った。以前はとても臆病だったのに昼間にも堂々と歩いている。藤も大繁殖してるなあ。こんなに山藤って多かったっけ。奇麗だけどつる性の植物だからそれだけ山があれているんだ。市原市の花はコスモスだけど、あれは人工的なものだから・・・。最近の異常気象で道路があちこち崩落。私は徒歩専門だから問題ないけど…市原市や観光協会はやる気ないなあ。
|
| ❶正字背異反足寶濶縁厚肉 |
|
 |
 |
| 長 径 |
48.8㎜ |
短 径 |
32.1㎜ |
| 銭文径 |
40.35㎜ |
重 量 |
24.0g |
肉厚ぶりが楽しい。正字背異反足寶は研ぎが強く台形の形状になるものが多い気がしますけど、この肉厚は立派だと思います。この類、やや肉厚のものが多いと勢陽譜には書いてある。でも、そんなイメージなかった。この背を見ていると揚足寶は同じ作りっぽく見えてきます。 |
| ❷正字背異反足寶濶縁(赤銅質) |
|
 |
 |
| 長 径 |
48.5㎜ |
短 径 |
32.4㎜ |
| 銭文径 |
40.25㎜ |
重 量 |
20.9g |
赤銅質というより焦げ茶色。台形の形状がかなり強い。やはり砥ぎが強いように感じます。極印は小さい普通桐。石持桐にはとても見えない。
この手のもっと赤い奴はないのかなあ。でもって重いのが欲しい。誰か譲ってください。 |
| ❸正字背異反足寶小様(赤銅) |
|
 |
 |
| 長 径 |
47.9㎜ |
短 径 |
31.75㎜ |
| 銭文径 |
39.8㎜ |
重 量 |
20.6g |
今、私が夢中な一枚。真っ赤で秋田小様の中に入ると分からなくなる。かわいいでしょ。もしかすると密鋳?でもこれより小さな背鋳反足寶があるんです。 |
| ❹正字背異反足寶小様(赤銅) |
Kinn氏蔵 |
 |
 |
| 長 径 |
47.57㎜ |
短 径 |
31.88㎜ |
| 銭文径 |
39.92㎜ |
重 量 |
20.26g |
2024/8/28 雑銭掲示板にKinnさんが投稿した画像。秋田小様並みに小さな反足寶は見たことがなかった。
とらさんも長径47.67mm 短径31.63mm 銭文径39.9mm 重量18.61gの個体を掲示板に投稿されてます。 |
|
|
| |
4月28日【尨字小点尓】
雑銭掲示板での関東のHさんの博識がすごい。Hさんは現物をたくさん集めて、人に会いに行き、また最近は泉譜もよく読まれているし、数値測定もしている。あとは経験値だけじゃないのかな。現物は一番見ている人になってきたし・・・パワフルで脱帽です。
一方、私の知識は子供のころか泉譜で学んだ知識と大人になってから見聞きした数少ない情報。歴史マニア的なところもあるので、それに経済学的なことやらも加えて「えせ学説」を考察披露します。したがいまして実に浅く広い。嘘にも流されやすい。「えせ」とは「似非」・・・似て非なるもので本物じゃない知識ですね。みなさん、だまされてますよ。
 さて、本日のお題の小点尓寶・・・これを初めて意識したのは方泉處11号秋、1995年8月号の天保通寶マニアックワールドを読んでからなんですね。この誌上ではじめて天保通寶四天王として仙人様の若かりしお姿を拝見したわけです。ちなみに天保通寶四天王とは秋田の村上師、青森の板井師、愛知の三納師、そして我らが天保仙人師のオールスター陣営です。控えおろう、頭が高い。 さて、本日のお題の小点尓寶・・・これを初めて意識したのは方泉處11号秋、1995年8月号の天保通寶マニアックワールドを読んでからなんですね。この誌上ではじめて天保通寶四天王として仙人様の若かりしお姿を拝見したわけです。ちなみに天保通寶四天王とは秋田の村上師、青森の板井師、愛知の三納師、そして我らが天保仙人師のオールスター陣営です。控えおろう、頭が高い。
それぞれが自慢の品を3枚ずつ誌上に披露していて、村上師が長郭手異當百異貝寶母銭、細郭手削貝寶(瑕寶)、長郭手奇天手。板井師が水戸正字背異替原母銭、水戸正字異替錫母銭、会津長貝寶母銭。三納師が仙台大濶縁、琉球通寶大字(小足寶狭冠寶)、三納天保(退天巨頭通)。そして仙人様が縮字宏足寶、奇書、そして中郭手小点尓。
インタビューで仙人様は一番のお気に入りとしてこの小点尓をあげていますし、入手のエピソードも尨字の類だということもさらりと語られています。縮字宏足寶や奇書を押しのけての力説なんで、よほど入手が嬉しかったんだろうなと感じます。(注:銭の名称は誌上掲載のものを優先しました。私も小点尓寶から小点尓に名称変更しました。)
 |
天保仙人蔵 小点尓 方泉處1995年8月号より
肌の雰囲気が良く分かる写真 |
この小点尓は天保仙人様の入手品が当時3品目の出現でした。その後、4品目が出現したらしいことも方泉處に記されていますが、私は直接手にして見たことがありませんでした。
書体の特徴は 保の人偏の筆初めの爪が少し大きく、左点が長め、通頭が丸く盛り上がり口が開き、通用は下窄みで通全体の背が低い平通、俯頭辵。通尾がゆるやかに弧を描くように見えるのは通の背が低いのでそう見えるのかも。また、極端な斜冠寶で寶貝が仰ぎ気味で前足が浮き気味に見える。名称のもとになった尓の前点は小さくアンバランス。背側は當冠のツの爪が大きく、ツ点の隙間が大きい。とらさんによると當田の右肩に穴のような瑕があるものが多い(画像左上)。百の横引きの前方、背の上部左輪際などにも共通の凹みがあるみたいです。
尨字という名称はこの書体の方が似合うんじゃないのかなあ。脱力感溢れる長閑な書体。緊張感、力感がないので今一つ風格がないかもしれない。名称としては 尨字小点尓 が一番通りが良いかも。
Hさんの協力もあって、雰囲気は異なるものの今回の入手品がどうやら小点尓に間違いなく該当しそうだという方向です。この品の前の持ち主はいったい誰なのかがわからない、なぜ今姿を現したのか。珍しい品なのでどこかの泉譜に載っていてもおかしくないのですが特徴が少なくて・・・未発見です。
なお、お断りしておきますが、天保仙人様は誤った判断をされた訳ではありません。そもそも中郭手小点尓そのものが国内にほとんどないのです。そして尨字塞頭通の天保銭が「ぬめぬめとした肌」の雰囲気で、それは私も同じ印象。私は小点尓の実物を手に取って見たことがほぼなかったので、この印象と今回の天保銭を結びつける事が出来なかった。仙人様は経験があったから、過去に見た尨字系のつくりではないと伝えてくれたからに過ぎないと思っています。つまりある意味正しいのです。
真贋の判断は相手を傷つけるのことがあるのでみんななかなかはっきり言ってくれない、言えないことが多いのです。それを教えてくれる方はとても貴重。判断の基準や経験を教えてくださっているのです。もちろん、品物を褒められれば素直にうれしいのですけど・・・。
私が❶の小点尓を悪いものではないと判断したのは、銭としての作りにいやらしさを感じなかったのと、とらさんが少し前に公開してくれた小点尓の画像のおかげ。私自身も久しぶりに尨字塞頭通を引っ張り出して極印を確認していたので、記憶がかすかに残っていたから。ですからたまたまなんですよね。今回は運がよかっただけ。どっちにころんでもおかしく無かった。本座広郭肥郭背狭穿は残念だったけどこれで五分に戻せた・・・いや、まだ会津大濶縁のつけが残されているかあ。
ちなみに本座広郭肥郭背狭穿もまだ100%ダメだとは思っていません。だって銭座の職人が作った古くて本格的なものなんでしょう。不自然なところがあるけど変造じゃないからまだ違う意見が出てくるかもしれない。だからそれまでは貴重な参考品にして私の宝物。
一方、会津大濶縁は・・・今や私が判断しても絶対ダメなところがあります。(書けないけど)あれは芸術的な変造品。美術品です。昔のコレクターも騙されたぐらいの品。でも、だめなものはだめ、
変造や贋作は私も自分で判断し、問われれば意見を言うことはありますがどこが悪いかの公開は極力しないようにしている。贋作師に応用されちゃうからです。判らない場合は好きか嫌いかを言います。自信もないし。天保仙人様はそれを正直に教え伝えてくださっている心やさしい指導者なんです。
※とらさんの画像とこの画像の銭文径はぴったり重なりました。私の銭文径の計測、自信ありません。ノギスの歯先が太いので表面に近い浅いところしか計測できません。
|
| ❶中郭手 尨字小点尓 |
|
浩泉丸蔵 |
 |
 |
| 長 径 |
48.7㎜ |
短 径 |
32.05㎜ |
| 銭文径 |
40.8㎜ |
重 量 |
22.3g |
この個体はひとめ普通の天保通寶のつくりで矛盾を感じない。書体は癖が強いわりに一画一画にメリハリや抑揚のない脱力した筆づかい。それに比べれば背はまともですね。
尨字の類にしては地肌の着色感がなく砂目もきちんとある。地肌は谷の中央部が凹みやや不規則にうねります。 |
| ❷中郭手 尨字小点尓 |
|
関東H氏蔵 |
 |
 |
| 長 径 |
48.74㎜ |
短 径 |
32.1㎜ |
| 銭文径 |
40.8㎜ |
重 量 |
21.91g |
この色のイメージは尨字のイメージなんだろうなあ。着色によって本来の地色が・・・黄褐色のイメージが見えなくなっています。これは塞頭通の類に良く見られるような気がします。背の田の右肩に丸い穴があり、地肌はぬめぬめしてうねる感じです。まさに尨字。 |
| ❸中郭手 尨字小点尓 |
|
関東H氏蔵 |
 |
 |
| 長 径 |
48.59㎜ |
短 径 |
32.06㎜ |
| 銭文径 |
40.8㎜ |
重 量 |
21.47g |
未使用色の残る尨字小点尓。このキラキラ色のイメージは虚を突かれます。着色感がありません。そのため小点尓の書体のイメージがすぐに湧いてきませんね。一方、谷の中央部の不規則な凹みやうねりはしっかり観察できます。 |
| ❹中郭手 尨字小点尓広郭 |
|
関東H氏蔵 |
 |
 |
| 長 径 |
48.87㎜ |
短 径 |
32.42㎜ |
| 銭文径 |
40.8㎜ |
重 量 |
23.06g |
あえて中郭手小点尓広郭としてみました。中郭手でなく細郭手でもいいなと思います。真っ黒で多少火が入ったのかなあ、文字や輪がだれた風もありますが小点尓。真っ黒な塞頭通は時々見かけますけど、ここまでだと着色なんだか煤けているんだか良く分からない。肌もあれているように感じてしまう。大きさのわりに濶縁に見えますが銭文径は同じ。輪が横に伸びている。延展? |
|
| |
4月26日【TICC最高!八厘会も楽しみました。】
2ヶ月ぶりに東京へ。天気もいいし、本当は山へ行きたかったんだけど、Tさんの預かり品に対する意見を仙人様に聞きたくて若干後ろ髪をひかれながらも上京。朝4時起きですから、それなりにうきうきしてます。昨夜は親父様が寝てくれなくて4時半に朝ごはん。脱臼から2ヶ月、ようやく傷も癒え、自立度が戻りましたものですから。
おかげで9時すぎには水天宮についてしまったのですけど、受付はもう始まってました。
しかし・・・セレモニーが長~い!コイン収集家は高齢者が多いのに1時間以上立ちんぼはつらいぞ。トイレにも行けない。主催者さん、工夫してほしい。あと照明がくらい。老眼のせい???
長蛇の列の中の若いコレクターはみんな中国語(そう聞こえる)を話していましたね。あっちの人は勢いがあります。それと会場には圧倒的に女性(店員を除く)がいない。これはもう絶望的だあ。古銭で女性との出会いはないね。うん。期待しちゃだめだ。
さて、本日の目標は大和文庫さん、38万円の不知小字大様が見たかった。買えないけど。
ところがまあ、それ以外もすごい品が出るわ出るわで目が釘付け。本当は寛永通寶も見たかったけど押すな押すなの大盛況なので天保通寶に絞って観察。大和文庫以外では某店で琉球の大字宏足寶の恐ろしいほどの美銭を拝見。35000円。また、U店で20000円の不知細郭手強刔輪・・・超お買い得品もあったけど、他にお金使ってしまったのでPass・・・嗚呼、見逃したのは惜しかった。
会場では関東のA さんにもお会いしました。彼は坂本高頭通濶縁を狙っていたらしいのですが、売り切れ。実は私もその古寛永は気になっていました。
八厘会に出席するため結局、TICC会場には1時間半ぐらいしかいられませんでした。残念。
八厘会の今月のテーマは秋田。Hさんは秋田広郭の母銭を展示。Aさんは加護山銭あれこれ。Oさんは秋田銀判の極印エラー・・・これは職人がわざと作成したもので大珍品らしい。もうひとりOさんは秋田銀判の真贋を並べていたけど見分けがつかない。銀物は難しすぎます。福西、加賀千代のせいです。Mさんは私が分譲した秋田小様最小様を含む、厚肉、薄肉、大様の展示。48㎜越えの大様は滅多にないし、1.8㎜の薄肉もいいなあ。元私の秋田小様最小様が笑っていた。
さて、Tさんの品について仙人様に寸評をいただきました。
今回持参したのは❹称:南部接郭(延展)❺不知広郭手異制大様❼広郭手異制(無極印)❽仙台長足寶大様❿広郭手異制(無極印)⓭薩摩広郭浅字美制大様の6枚。❶不知長郭手削貝寶(刔輪延貝寶)❷不知長郭手刔輪長足寶も持参しましたがタイムアウトでお見せできませんでした。
仙人様は私ほど銭文径は気にされません。そのかわり製作、金質については確かな経験の目をお持ちですが見ていた時間が短いため意見は絶対ではありません。あくまでも印象意見だと思ってください。最終的な真贋までの突っ込んだお話はなしということ、そして私の意見解釈・周囲のコメントも含めて記します。
❹称:南部接郭(延展) は真贋はともかく鋳造後に人の手(火?)が入っているという意見でした。つまり加工は間違いないのですが、写しかどうか、時代がいつかまでは言及されませんでした。どうしてそんなことが必要かという点については少々怪しいなあという雰囲気は出されていましたが・・・。
❺不知広郭手異制大様は上下に叩きが入っているのは間違いないものの、重くて肉厚だし周囲のやすりの仕上げは本座じゃないから不知広郭手として間違いないとのこと。とても良い品です。
❼と❿の広郭手異制(無極印)はきっぱり不知広郭手ですという見解。本座の極印落ちは流通させない、本座の極印打ち職人はそれだけ地位が高く、2つ打ちや逆打ちはあっても漏れはないとのこと。まあ、これは私も同意見。
❽仙台長足寶は大丈夫です。ただし仙人様の見解としては鋳だまりがないので大様とまでは認定しなかった。目の前で計測したわけではないので・・・私の意見ですがこの点は実測値重視で私はいいと思います。なお、金貨や銀貨は色上げができるそうですけど銅貨の色上げは技術的に不可能だそうですのでこの色は問題なしのようです。
⓭薩摩広郭浅字美制大様は手にされて「自然であり、こんなものがあっても良い」とのはっきりした意見。密鋳銭ですからいろんなところで分散して作ったので例外だってあるとのこと。2枚目の出現が待たれます。
さて、私のハイライトは2つ。
ひとつは①本座広郭母銭の極端な狭穿のもの。本来母銭は収集対象外なんですけどこれだけは気持ちを抑えられなかった。昨年入札で入手したものなんですけどこのような事例は見たことがなかったので仙人様に見て頂きたかった。
盛んに首をかしげる仙人様。私は内心ドキドキ・・・で、結論は「本座の職人が作った明治期の贋作」が~ん。嵌郭の痕跡がいやらしく感じるのと穿内の仕上げが気に入らないそうで・・・たしかに仕上があるようでない。まあ、ここまでの贋作ならば本物みたいなもの。昨年の会津大濶縁に続くショックですけど、大丈夫だ、傷はまだ浅いぞ!しかし、これは見抜けなかった。郭内仕上げ以外のつくりは本物そのものだから。
本日のメインディッシュは大和文庫で見つけた②中郭手小点尓。これは手にした瞬間ビビッと電撃が走りました。何度もひねくり回し、躊躇と葛藤、でも手からはなせなかった。即売品リストにもない品なのでうかうかしてると他の人に買われちゃう。小点尓寶は塞頭通と同じ尨字の系統とされます。肌と色の印象がずいぶん違ったのですが砂目は自然。極印もいい。だから購入を決断。仙人様に相談しなくて怒られるかなーと思いながらの購入でした。ですから本日の八厘会は金欠で・・・なんも買えねー(北島康介風でご発音ください)状態でした。
で・・・②中郭手小点尓を仙人様に恐る恐る差し出すと・・・う~ん、尨字じゃあないね。尨字は肌がもっとぬめぬめする感じのはずだよ・・・とのお言葉。精一杯のやさしい声で・・・その瞬間、周囲の人々が目を合わせてくれなくなった気がします。やば、やっちまったか、まさかの連敗。お先真っ暗、財布は空っぽ。( ;∀;)
しかし、私には大丈夫かもしれないとの思いがまだありました。それが極印。それは自宅で撮影確認して確信に至りました。ライティングで確認すると地肌も同じ系統に見えてきました。画像撮影の力は大きいなと思います。こうして古銭中毒の人間はさらに病を深くして行くのだと思います。
※大和文庫さん、きょうはコレクターの放出品を頼まれてまとめて持って来ていたみたい。即売リストに入っていないものがたくさんありました。私が小点尓を購入決断したのもそれが大きい。絶対とは言えないけれど昔のコレクターの収集品は確かです。
※午前2時、親父様が起きてきた。大音量でTVを見はじめ暖房付けて・・・私は日曜日も仕事なのに、4時のごはん所望かな。脱臼なおったら行動が激しくなった。記憶と体内時計が壊れてます。食欲もすごい。寝ないからお腹が減るようで・・・来月の八厘会のテーマは南部藩だそうです。勉強になるものをご出品くださいとのことです。
|
| ①本座広郭肥郭背狭穿 |
→ 明治期の贋作の可能性 |
 |
 |
| 長 径 |
50.10㎜ |
短 径 |
33.40㎜ |
| 銭文径 |
41.65㎜ |
重 量 |
22.1g |
銅質、製作、規格とも本座そのもの。ただ、郭が極端に広く、とくに背狭穿になっているもの。その穿の内部仕上の磨き仕上がないのが気に入らない要素。他が完璧なので私の眼には分かりませんでした。鋳銭道具が残されていたので、それで本座の職人が作成した明治期の贋作ではないかとのこと。そんなものあるんだあ。ほぼ本物です。 |
|
| ②不知中郭手小点尓(尨字系) |
 |
 |
| 長 径 |
48.7㎜ |
短 径 |
32.05㎜ |
| 銭文径 |
40.8㎜ |
重 量 |
22.3g |
製作に問題なく、砂目ははっきりしていますが極印は尨字そのもの。肌も波打つ癖が残っています。 |
|
| 比較用)不知長郭手尨字塞頭通 |
|
 |
 |
| 長 径 |
49.10㎜ |
短 径 |
32.30㎜ |
| 銭文径 |
40.90㎜ |
重 量 |
20.6g |
大分違うように見えますが天保や當冠の筆法は同じですね。誰が同炉だときがついたのかな。極印も同じ。上の極印は右が小点尓寶で左が塞頭通。ヤスリも同じような雰囲気ですけどこれは断定できない。砂目もそんなに差がないけど、地の墨入れが尨の方が強い。地にあいた穴ぼこが真っ黒に染まっています。 |
|
| |
4月23日【薩摩広郭大様】
ようやく13枚の天保銭を見終わりましたが、ひとつも結論が出ていない情けない結果になってしまいました。本日の薩摩広郭大様もしかり。薄いのは確かですけど焼け伸びや延展には見えない。そもそもそんな加工をする意義なんかはあるのか?
仙台長足寶大様も悪いものには見えないのですけど鋳肌や色が不思議。こちらは薬品洗浄はあるかもしれません。
接郭写しはあると思う。不知で良いと思いますけど延展なのかは不明。
これらの共通点は大きさのわりに薄っぺらいこと。だから誤解を受けやすい気がします。
異制の無極印には参りました。これはもう不知として良い気がします。本座の職人がその道具を使って作ったのかも知れませんが、本座で極印を打ち落とすことはもう、本座の統制下ではあり得ないと思います。あっちゃいけないものが世の中に出てきているんです。
そもそも異制というものが考えられたのは、幕末期の金座から明治期の貨幣司に至るまでの混乱期において鋳造され続けたものではないかとの考察。幕末の混乱期は房総半島からの鋳砂の調達が難しくなり、弘化年間以降には仕上げ工程を省略した(やや品質の劣る)天保通寶が大量に世に出たという記録は確かに残されています。さらに大阪難波においても1865年から3年間鋳造。貨幣界では難波大阪の新銭座の天保通寶は中郭ではないかと言われていますが、この混乱期にきれいな中郭が作られたとはちょっと考え難く、異制を含む広郭銭が大量に作られたのではと私は邪推してしまいます。天保通寶は明治政府に引き継がれた後も数年間鋳造が続いています。
明治政府が天保通寶の鋳造を早期にやめて、密鋳を厳しく取り締まったのは、密鋳によって新しい勢力が台頭するのを恐れたためだと思います。明治維新が天保通寶などの貨幣密鋳によって成し遂げられたことは政府の中でも認識していたと思います。だからこそ、新しい貨幣の発行を急いだものと思うのです。 |
| ⑫薩摩広郭浅字美制大様 |
|
判定:薩摩広郭 |
 |
 |
| 長 径 |
49.55㎜ |
短 径 |
32.56㎜ |
| 銭文径 |
42.20㎜ |
重 量 |
18.8g |
真っ黒で薄く軽い。中央に鋳割れの筋がうっすらと残り、いかにも末鋳の天保通寶です。銭文径が大きいとのことで確認すると・・・あれれ、41.8㎜しか出ない。通常ノギスをデジタルノギスに替えて測ると・・・42.2㎜はある。原因は天の横引きの上の穴ぼこと鋳だまりとノギスの先端の形状みたいです。穴ぼこにノギスの歯が深く入ると銭文径が大きく出ます。私のデジタルノギスの先端は尖っている。 |
 |
だから垂直に歯が入るのですが、これだと穴ぼこの斜めの壁を測ってしまうようです。私の通常ノギスの先は鋭くないので、ノギスを銭面に平行に近く倒して銭の凸部の浅いところを測ることになります。結果的にこの方が数値は正確。デジタルノギスで同様に測ってもほぼ同じに出ました。計測に自信はありませんが、びっくりするようなものではありません。鋳造中に鋳型にひびが入ったことも多少影響があるかもしれません。
と・・・結論付けようとしたのですが・・・ |
|
| ⑬薩摩広郭浅字美制大様 |
|
判定:薩摩広郭浅字美制大様(謎!) |
 |
 |
| 長 径 |
49.90㎜ |
短 径 |
33.05㎜ |
| 銭文径 |
42.20㎜ |
重 量 |
17.8g |
こいつは・・・説明がつかない!やや白っぽい銅質ですけど普通の薩摩広郭。郭の形も前の品のように縦長ではないし、長径も大きい。気になるとすれば薄っぺらいこと。でも焼け延びや延展には見えない。大きいのに薄いし軽い。ここが気になるところ。 |
| 比較用:薩摩広郭白銅質 |
|
 |
 |
| 長 径 |
49.30㎜ |
短 径 |
32.55㎜ |
| 銭文径 |
41.45㎜ |
重 量 |
24.3g |
白銅質としてはまあまあ白い方。純白のものもある。何せ私は白好きです。薩摩広郭白銅収集は私の黒歴史ですから。この広郭もいつの間にかアルバムの中にいたぐらい。薩摩広郭白銅はなぜか輪や郭が虫食い状に欠けているものが多いと思う。音も少し高く響きが良いので錫比率が高い気がする。純白に見えても撮影すると黄色く映るものが多いです。 |
|
 半切り画像を重ねてみると確かに文字の太さ一画分ずれます。でも違和感がないのです。銭文径の実差は推定で0.5~7㎜ほどでしょう。焼け延びには見えないと書いたのですけど・・・とはいえ、可能性として0ではない。と、いうのは背に緑青がうっすら吹いている。緑青は罹災した天保銭に良く見られるのです。可能性はあるけど断定はできません。どなたか銭文径42㎜超過の薩摩広郭お持ちではないですか? 半切り画像を重ねてみると確かに文字の太さ一画分ずれます。でも違和感がないのです。銭文径の実差は推定で0.5~7㎜ほどでしょう。焼け延びには見えないと書いたのですけど・・・とはいえ、可能性として0ではない。と、いうのは背に緑青がうっすら吹いている。緑青は罹災した天保銭に良く見られるのです。可能性はあるけど断定はできません。どなたか銭文径42㎜超過の薩摩広郭お持ちではないですか?
と、思ったら2024/7/28の制作日記に私自身が書いている。ただし、これは薄肉の末炉銭。焼け延びの可能性が高い。 |
|
| |
4月22日【本座異制を定義する】
本座異制という言葉を意識させられたのは私の場合天保通寶と類似カタログが最初で、類似カタログにおいては本座の項目に「広郭異制」として掲載されていますのでこれが正式名称なのでしょう。私は広郭を省略して本座異制と普段呼称しています。類似カタログにはこうあります・・・「旧譜では秋田本座写しとしていた。面背の肌が荒く、銅色も異なる。この異制にも痩通寶がある。」ただし、この記述は少々舌足らずでして、秋田本座写しは白銅質の物だったことがかつてあり、その青寶樓譜の秋田本座写は「本座広郭をそのまま写したもので銅色が黒褐色(黒?!)で側面の桐極印が深く打ってある」と記してあります。
このように変遷した広郭異制の候補はいくつかあります。
❶称:旧秋田本座写(白銅質以外)
明治期に秋田の古銭研究家、布川新栄堂氏の発見経路から確定された経緯があります。秋田領内には良質な砥石がなく、また鋳砂の調達も難しかったため、粗いやすり目とざらついた肌が特色で、ほかに極印は小さめで深く打たれているのが特徴とされました。銅色は白銅質のものが該当させられていましたが、やがて白味のある黄銅質に置き換わってゆくことになります。
❷称:旧佐渡本座写(白銅質)
秋田で天然の白銅が採れ、秋田天保の母銭に白銅のものが見られたことから、一時期白銅質の天保(薩摩広郭白銅と本座白銅質など)が片っ端から秋田に編入された時期があります。それらのうち、本座と同じ書体を佐渡天保としたのは小川青寶樓師。曳尾が佐渡ではないと萩に移籍されたのを機に、秋田籍であった広郭白銅質を佐渡に割り当て直したもの。ただし根拠は薄い。類似カタログでは佐渡籍から広郭白銅質とされました。こちらも銭径、銭文径の縮小は見られません。
❸明治貨幣司吹の天保通寶
明治政府になってからも天保通寶の鋳造は続けられていましたが、佐幕派の不満分子がが房総半島に集結していたため、化粧砂の白土の入手が難しくなっていました。そのため王子産の鋳砂に切り替え、いくつかの製造工程を省略した粗造の天保通寶が生まれたと言います。本座異制がそのひとつだと言われています。次の恩賜手に重なるものでもあり、明確な区別は難しいと思います。本座なので銅色は当然ながら黄銅質ながら表面がざらつくため肉眼では白っぽく見えます。銭径、銭文径の縮小は見られませんが、砂目が粗く砂磨きのきついものが充てられています。
❹恩賜手(明治期吹増)
明治天皇は維新後全国を行幸されています。その時の費用を賄うため吹き増しされたのが恩賜手と呼ばれる寛永通寶や天保通寶で、粗い砂磨きの天保通寶(寛永銭は文政期のつくりで側面が強い縦ヤスリ)が該当するとされました。この説は三上香哉が唱え、大川天顕堂も資料を作成していますが、現在は否定的な意見が貨幣界にはあります。ただし、それらしき現物は確かにあるので・・・。銅色は黄銅質のものが多い。銭径、銭文径の縮小は見られませんが❸以上に砂磨きの条痕のきついものが充てられます。
❹称:水戸正字の類
その昔、本座広郭と同じ書体で制作のやや粗いものは「水戸正字」とされていました。銅色は黄銅質。水戸正字背反郭と称された時代もありますが、青寶樓譜で水戸正字はいきなり姿を消し、私は衝撃を受けました。今でも時々見かける水戸正字母銭は本座の未使用母銭であり、本座広郭母銭は使用済み母銭であると良く言われています。 銭径、銭文径の縮小は見られません。本座のようなきっちりした砥石仕上げがなく、❸と同じものだと思われます。つまり、同一です。黄銅質であっても砥石仕上げが不十分なため白っぽく見えます。
❻称:旧岡藩肥天痩通の類
九州貨幣学会の橋詰武彦氏により、昭和46年に日本古泉研究会の「古泉」誌上などに発表されたもの。後に豊後国岡藩貨幣の歴史にも詳しく発表されています。昭和46年、岡藩勘定方の足軽、工藤重左エ門の墓所で日記とともに12枚の未使用の天保通寶が入っている朽ち果てた木箱が発見されました。慶応2年3月15日、豊後岡藩において天保通寶が密鋳されたらしき事が記されており、書体は肥天痩通の類であったようです。銅色は白っぽい黄銅質。銭径、銭文径の縮小は見られないものが中心ですが、小様銭も発表されました。日本古泉研究会は小川青寶樓が立ち上げたものでしたから新訂天保銭図譜にも掲載されています。
❼広郭異制
類似カタログには「旧譜では秋田本座写しとしていた。面背の肌が荒く、銅色も異なる。この異制にも痩せ通寶が存在する。」困った・・・色調が違うと言っている。銭径、銭文径の縮小は見られません。
さあ、困りましたね。ほぼ同じ規格のものでよくわからないものを、微妙な制作の違いで呼称を変えてきたものだと言えます。本来は❼が多くの受け入れ先になるはずなんですが銅色がね~。
というわけで浩泉丸は・・・
❽広郭異制
本座広郭と同じ書体、銭文径で、製作、砂目、ヤスリ目が粗く異なるもの。銅色や重量が異なるものも含みます。覆輪が著しいものや明らかな無極印、はっきりとした異極印は不知広郭手とすべき。銅色は特定しません。と考えます。
参考にしてください(制作日記)
2007/11/8
2010/5/15
2014/8/23
2015/12/22
2019/1/2
2018/11/24
2020/4/26
|
| |
| 4月21日【13枚の天保銭・・・あと一息】 |
| ⑨曳尾 |
判定:曳尾背広郭 |
 |
 |
| 長 径 |
49.90㎜ |
短 径 |
32.85㎜ |
| 銭文径 |
41.40㎜ |
重 量 |
22.3g |
私のノギスだと長径は50㎜になる。あくまでも計測値はTさんの値優先。ただし、短径が31.85㎜とありましたが、これは誤記と判断しました。なんで曳尾・・・と思いましたが⑤の異制大様とよく似た作りとのこと。う~ん、さすがに無理があるけど、そういった目は大切にしたいですね。横ヤスリが荒々しいです。 |
| ⑩広郭手異制 |
判定:不知広郭手異制無極印 |
 |
 |
| 長 径 |
48.80㎜ |
短 径 |
32.45㎜ |
| 銭文径 |
41.45㎜ |
重 量 |
22.4g |
参りました。2枚目の異制無極印。そして考えを変えた。前の1枚も含めて不知銭にすることにした。私にとっては衝撃的。砂目も側面ヤスリも荒い。極印は見当たらないし、かけららしきものもない。昔だったら岡藩なのかなあ。それとも南部民鋳? |
| 天側 |
 |
右側面 |
| 天側 |
 |
左側面 |
|
|
| ⑪広郭手異制 |
判定:広郭手異制 |
 |
 |
| 長 径 |
49.25㎜ |
短 径 |
32.65㎜ |
| 銭文径 |
41.65㎜ |
重 量 |
22.6g |
これは計測誤差で銭文径は41.35㎜前後だと思います。画像を重ねてもほぼ本座ですから本座異制だと思います。しかし面から見ると実に土佐っぽい雰囲気です。そういう意味では違和感がまだ残ります。 |
|
| |
 4月19日【仙台長足寶大様】 4月19日【仙台長足寶大様】
13枚の天保の8枚目まで来ました。私は仙台長足寶は2枚しか所持したことがなく、全く語る資格がないのですけど・・・。
 旧家の屋根裏から見つかったようなすすけた風貌ながら、未使用肌の天保銭で地肌にはぼこぼこに小穴が開いています。ただし、手が切れるような切り立つ感じでありません。赤い色合いのせいか鋳ざらいの痕跡はあまり目立たなく、さらに寶前足が陰起し先端部の輪に鋳だまりがあり、後足も離輪して寶両足ともあまり長く見えないのです。本当に長足寶?と言われそう。 旧家の屋根裏から見つかったようなすすけた風貌ながら、未使用肌の天保銭で地肌にはぼこぼこに小穴が開いています。ただし、手が切れるような切り立つ感じでありません。赤い色合いのせいか鋳ざらいの痕跡はあまり目立たなく、さらに寶前足が陰起し先端部の輪に鋳だまりがあり、後足も離輪して寶両足ともあまり長く見えないのです。本当に長足寶?と言われそう。
大様の特徴である銭面左の突起はないし・・・色は違うし、意外に軽いし・・・と不安がよぎりますが、極印は仙台だと思う。頭部がツンツン鋭い。でも、大様だけど母銭じゃあない。背のつくりも甘いですね。確かに面左側に大様のお約束の突起がないから次鋳の母銭にはなりえそうですけど、さすがに製作も文字抜けも今一つすぎますので・・・夢見ちゃいましたね。
仙台天保は青味がかった淡黒褐色が多いので、未使用の赤い肌色、穴ぼこの多い地肌、薄くて寶足も短く見えてしまうなどちょっと不思議な感覚に襲われてしまうのです。審美眼的には違和感を禁じえませんが、総合的に見て悪いものではないと思います。これが贋造、変造の類だとしたら、私はもう天保銭に手が出せなくなります。
※撮影したスキャナーの機種、撮影方向で画像の歪みが違うので・・・もう一度検証してみます。 |
| ⑧仙台長足寶大様磨輪(格下げ母銭?) |
判定:仙台長足寶大様 通用銭 |
 |
 |
| 長 径 |
49.05㎜ |
短 径 |
33.20㎜ |
| 銭文径 |
40.60㎜ |
重 量 |
17.9g |
仙台銭を称して「松葉でつついたような」地肌とはよく言ったもので、この天保銭は本当にその肌をしています。まるで泡立つようなのです。彫金細工のような地肌のものを見かけた事もあるのですが、こちらは冷えたての溶岩の肌。美しくはないのですけど未使用で摩耗のない仙台銭はこういう肌なのかもしれません。ただし、母銭のつくりではなく格下げ母ではないと思います。寶前足先端に鋳だまりがあり、短く見えます。 |
| 比較用:仙台長足寶小様 |
|
 |
 |
| 長 径 |
48.5㎜ |
短 径 |
32.5㎜ |
| 銭文径 |
39.9㎜ |
重 量 |
17.9g |
今、私の手元にある仙台天保はこれ1枚のみ。偶然同じ重さ。サイズ的には初鋳に対しての次鋳の関係で、大様サイズの母銭の存在がうかがえます。地肌はむしろこちらの方がきめ細かくてきれい。類似カタログには地肌は母銭に施された細工とありますが、上の大様を拝見する限りは細工ではなく自然発生的なものに見えますが、果たしてどうか。。 |
 |
 |
合成画像。郭の位置で合わせました。光源位置を下からにかえてみました。寶前足が陰で強調されましたね。銭文径は案外微差なんだなあ。こうしてみると悪いものには見えない。でも、薬品洗浄はあり得るかもしれない。 |
|
| |
4月17日【受診と測定の日々】
本日も受診日。外国人職員の付き添いです。来週も。週3日も付き添うと仕事もプライベートもないなあ。微妙な自己表現の苦手な外国人は病院に行っても本当のことを上手に伝えられない。お金がかかると判るとギリギリまで我慢してしまう。ヘルニアなど致命的なけがを負ってしまうこと・・・。車の免許がないので遠くの医療機関には送迎も必要です。そこに親父様が加わり病院三昧です。
さて・・・ |
| ⑥不知広郭手異制大様(面背覆輪跡) |
判定:本座異制 覆輪は? |
 |
 |
| 長 径 |
49.60㎜ |
短 径 |
33.15㎜ |
| 銭文径 |
41.45㎜ |
重 量 |
24.9g |
赤黒く重い大ぶりな天保銭。微妙な歪みがあり机の上に置くとガタつきます。保の人偏の筆掛にあるまん丸鋳だまりが可愛い。砂磨きは強くないのであまり異制っぽくないのですが拡大してみると異制の顔です。長径が長いのは湯道が寶下にあるからです。覆輪跡とありますが確認できない。縁が多少めくれ上がるような仕上の癖があり、それを見誤ったのでは?ちょっとだけ火中品ぽいです。 |
| ⑦広郭手異制 |
判定:不知広郭手異制無極印 |
 |
 |
| 長 径 |
49.20㎜ |
短 径 |
32.65㎜ |
| 銭文径 |
41.40㎜ |
重 量 |
20.6g |
きれいに赤茶色に発色した広郭。私のノギス計測では銭文径は41.2㎜前後なので本座とされても仕方がない品。異制と言えば異制、本座でもどちらでもいい。ところがいくら目を凝らして見ても側面の極印がない。打ち損じでもなく、削られた痕跡もない。こいつは参った。Tさん、気が付いていましたか?無極印は不知銭でも滅多にないのです。ひょっとしてエラー銭か?
あるべきものがあれば大騒ぎするものじゃないです。私は初見です。
|
|
| 天側 |
 |
右側面 |
| 天側 |
 |
左側面 |
|
| |
4月16日【受診日和】
休日です。しかし、親父様の受診のため自由行動ができません。右肩鎖骨の脱臼以来、デイケアが増え、姉の見舞いと葬儀もあり、てんてこ舞いでした。親父様、調子が悪くて夜間行動がしばらく影を潜めていたのですが、回復するに合わせて活動が復活。一昨日は午前4時に朝食です。昨日もほぼ寝ていない。鉄人。
今日は歯医者、来週は内科。肩の通院はようやく終了。整復はできないので保存療法ですけどひとつ通院が減った。予約日はあるのですが時間が定められてなく、朝7時に順番取り。受付開始と予診が8時半で9時過ぎにようやく受診開始。会計して薬をもらうまで午前中いっぱいかかります。身内なんですけどもう少し何とかならないのかなあ。デイケアはデイサービスより迎えが遅く、帰りが早い。だから本人大混乱。
親父様は診療結果を記憶できないし、次回予約も忘れちゃうので・・・愚痴です。
午後から海鮮丼食べに館山まで行くぞ!親父様のおごりだぁ!
と、いうわけで13枚の天保銭の続きです。今回の品、期待が高かったんです。
|
| ⑤不知広郭手異制大様 |
判定:不知銭。ただし本座異制も可。 |
 |
 |
| 長 径 |
50.20㎜ |
短 径 |
33.00㎜ |
| 銭文径 |
41.85㎜ |
重 量 |
25.4g |
第一印象は額輪系しかし、子細に観察すると天の上部の輪が明らかに幅広く側面の一部の際が盛り上がっていますのでこれは強い力がかかっています。湯口部分が盛り上がっていたので修正したのかも。覆輪とまでは言えないかもしれないがわからない。輪際のつくりは額輪と同じ額輪厚肉というものがあれば入れたいぐらい。雑銭掲示板に拡大画像を載せました。文字位置は一般的な天保通寶と同じなのです。旧秋田本座写しとは雰囲気が違う。不知広郭手としておいて後考を待つのが妥当でしょう。 |
| 比較用:本座異制もしくは不知広郭手 |
|
 |
 |
| 長 径 |
49.05㎜ |
短 径 |
32.80㎜ |
| 銭文径 |
41.05㎜ |
重 量 |
22.4g |
発色もあってひとめ土佐額輪短尾通っぽい雰囲気。縦方向の粗い砂磨きがある。面背とも肥郭肥字気味で斜穿になっていますし、やや濶縁気味で銭文径も幾分小さい。ただし、計測に自信なし。鋳詰まりも多いしたしかに異制です。 |
| 比較用:本座異制(旧:秋田本座写) |
| 長 径 |
49.50㎜ |
短 径 |
32.85㎜ |
| 銭文径 |
41.35㎜ |
重 量 |
23.4g |
初めて通販で購入した天保通寶。手が切れるように角が立ち、ざらざら肌。 触れた感じはまるで紙やすりみたい。この手は恩賜手というのかも。極印は小さく深く打たれています。秋田本座写しは現在は否定されていますが、面倒なのでHPにはまだ残しています。計測したら思った以上に大きくて重かった。本座異制にはいろいろ混じっていると思う。 触れた感じはまるで紙やすりみたい。この手は恩賜手というのかも。極印は小さく深く打たれています。秋田本座写しは現在は否定されていますが、面倒なのでHPにはまだ残しています。計測したら思った以上に大きくて重かった。本座異制にはいろいろ混じっていると思う。 |
 |
 |
| 参考品:本座白銅質(旧:秋田本座写→佐渡本座写→本座白銅質) |
 |
 |
| 長 径 |
49.35㎜ |
短 径 |
32.85㎜ |
| 銭文径 |
41.1㎜ |
重 量 |
21.0g |
これも異制の一種のようなもの。類似貨幣カタログの評価では4~5000円。ところが異制の評価は15000~20000円。これだけ白いのは滅多にないですけどね。秋田天保に天然の白銅母銭が見つかったことから、一時期薩摩広郭の白銅質まで秋田とされた時代があります。曳尾が佐渡から萩に異動した空白をこの銭が埋めていますが、廃物棄却で鋳潰した仏像で作られたのではないかという憶測だけで明白な根拠はありません。 |
|
| |
4月13日【13枚の天保銭】
関西のTさんからレターパックが届きました。私に見て意見を聞きたいとのこと。お~ずっしり、責任重大です。とはいえ、私の錆びついた目ではいまいち信頼がないのですけど・・・臆せず意見を言わせていただきます。
ただ、いきなりすべてを画像化するのは大変なので、小出しにしてゆきます事をお許しください。
|
| ①不知長郭手削貝寶(刔輪延貝寶) |
|
 |
 |
| 長 径 |
49.35㎜ |
短 径 |
32.95㎜ |
| 銭文径 |
41.60㎜ |
重 量 |
20.9g |
Tさんの所蔵品としてHPにも掲載させていただいています。名称も勝手に代えてますが、これは文句ない不知銭ですね。銭の下半分の輪に沿って刔輪がなされそれに寶貝が伸びています。当然覆輪もされています。やや白銅質で素朴なつくり。寶貝に鋳だまりができたので修正して偶然こうなった?そのため銭文径が大きい。ほとんど類例をみない稀有な事例です。 |
| ②不知長郭手刔輪長足寶 |
|
 |
 |
| 長 径 |
48.60㎜ |
短 径 |
32.35㎜ |
| 銭文径 |
41.10㎜ |
重 量 |
20.6g |
これしか見たことがないので断定はしづらいけど上のものとよく似た作り。極印も破損しているけど形状は同じか?T産の眼は確かです。張足寶と宏足寶の進化過程で長足寶の方がいいかもしれない。製作は素朴で銭の下半分を覆輪刔輪で加工しています。心なしか下部の磨きが強い気がするのもそのためでしょうか。面に比べて鋳造がきれいなのは上と同じですね。穿内べったりヤスリです。 |
|
| ③不知長郭手異制弱刔輪 |
判定:本座長郭 |
 |
 |
| 長 径 |
48.95㎜ |
短 径 |
32.10㎜ |
| 銭文径 |
41.50㎜ |
重 量 |
18.8g |
赤く発色していますが、これは軽く火を被り、還元焼成されています。極印は破損野中打ち損じなのか良く分かりませんが、異極印というほどでもありません。大頭通にも見えなくもないのですが、ほかに見どころがなく本座と見るべきでしょう。穿内も異常とは言えません。なお、本座でも刔輪的な内輪の修正はあります。 |
| ④南部接郭(延展写) |
判定:接郭写かなあ? |
 |
 |
| 長 径 |
49.50㎜ |
短 径 |
32.90㎜ |
| 銭文径 |
40.50㎜ |
重 量 |
19.0g |
はじめて画像を見たときは火中品だと思った。手にした瞬間もそう感じた。しかし、良く見れば鋳肌も地の色も接郭とは違う。湯圧不足での花押の大きな欠損や鋳不足状のヒビ、地染めの墨使い・・・水戸藩じゃないなあ。ただし、私自身が延展変造で痛い目に遭っているので何とも言えない。これは仙台銭のように天の第一画が太くなっています。他の人の意見も聞いてくださいね。 |
| 比較用:接郭強刔輪やや大ぶり銭異製作 |
|
 |
 |
| 長 径 |
49.30㎜ |
短 径 |
33.00㎜ |
| 銭文径 |
39.7㎜ |
重 量 |
18.4g |
私が違和感を感じて拾っていたもの。理由は地にわずかに墨科漆が入っているのと赤味が強いこと。接郭は墨入れを普通していないと思う。刔輪のぐりぐりが強調されている。やや赤みの強い品。 |
 |
 左は合成画像。内径は少し小さいが銭文径は大きい。寶冠と寶貝上辺、保と天の第2画の位置はそろっているけど銭文径は大きい。これは天上、寶貝が伸びている。内径の差は書体の差なので、これは長径の上下で叩かれているのは間違いない。そう考えて上部を見ると天上が盛り上がり歪んでいる上、強い砂磨きが入っています。側面のやすりは東北独特のものではないし。 左は合成画像。内径は少し小さいが銭文径は大きい。寶冠と寶貝上辺、保と天の第2画の位置はそろっているけど銭文径は大きい。これは天上、寶貝が伸びている。内径の差は書体の差なので、これは長径の上下で叩かれているのは間違いない。そう考えて上部を見ると天上が盛り上がり歪んでいる上、強い砂磨きが入っています。側面のやすりは東北独特のものではないし。
冷静に考えるとこれって文字の太い部分を除けば、接郭そのものじゃないかなあ。通や保の位置は一緒だし。だとしたら火中品か?
謎は地の染めと肌の鋳不足的な亀裂と凹み。これを考えると接郭の粗造写しは十分にありえる。延展による銭文径拡大はおまけ。実際はそんなに伸びていない。現段階ではここまでしか言えない。 |
|
| |
4月12日【楽しい錯笵】
錯笵に真贋なし・・・とは言い過ぎですが、絵銭のようなものと考えた方が良いと思います。刻印銭よりまだましな世界ですけど、贋作・戯作のオンパレードには変わりない。高く売らんがための悪意ある贋作は古くは加賀千代の方字が有名でしたね。かくいう私、錯笵銭も大好物でして、HPに掲載されていない品々も多数。屑と宝は紙一重なんですけど…将来はゴミくずかなあ。
多くの錯笵は鋳造過程の失敗で、実際に元文期山城寛永座の鋳造の成功率は500枚鋳造して400枚(80%)程度、とかなり低かったと翁草に記録されています。だから出来損ないはたくさんできる。検品で世に出されないだけなのです。
また、「完璧なものには魔がすぐに宿る」という思想が古来からあり、フイゴ祭り(11月8日)のときなどにわざと不完全なものを作ったとか。錯笵銭はその時の記念銭、魔除けのお守りとして配布された可能性があります。以前も書きましたが、古銭大名の朽木公の収集品の中は立派な御用銭コレクションばかりでなく、錯笵銭がたくさん含まれていました。大名に普段の失敗作を献上するはずもなく、縁起ものとして集められたものとは考えられないでしょうか?
なお、長崎銭や文久銭の背多重輪は、実際の背ズレも多いのですけど、銭の方向がまちまちすぎたり、間隔が狭すぎて湯道を切ることができないようなもの、くっついてしまい使い物ににならないものも多い。これはもう錯笵を目指して最初から作成したものだと言われてもおかしくないのですが、流通銭の中の派手な錯笵も時々見つかるからややこしい。真贋入り乱れの玉石混交の世界です。ですから真贋に目くじらを立てず、肩の力を抜いてご覧ください。
|
 |
| 母銭の重なり? |
|
 |
明和期の新寛永
意図的な背ズレ |
|
 加賀千代の錯笵天保 加賀千代の錯笵天保
非常に美しいつくり。萩の方字の銅質とは異なるが製作は本格的。もはや芸術作品である。 |
|
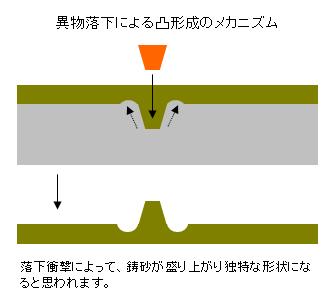 |
 |
背側の砂笵ずれの古寛永
製作に矛盾はなく、古い収集家の朱書きもある。錯笵銭としてはごく自然。古寛永の錯笵は銭座職人が関与していて素材的には自然なつくりが多い。数は少ないと思う。 |
|
 |
 母銭の落下痕跡 母銭の落下痕跡
左は鋳棹の落下による錯笵と推定。反動で凹部ができます。 |
|
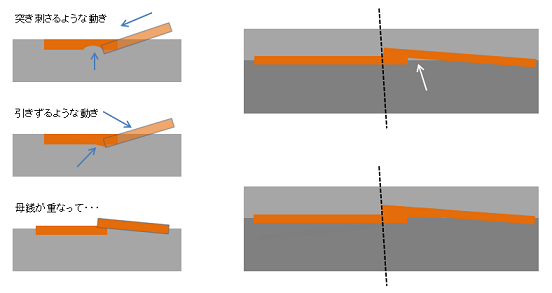 |
1)押し付け
2)引き押し
3)母銭の重なり
による鋳造の結果形状の変化の予測。
1)は鋳砂の盛り上がりから凹みができる。
2)は傾斜のある凸ができる。
3)はかなり厚みのある段差ができるが白矢印の部分に空間ができるので傾斜部もできる。一番薄い点線部で切断。 |
|
明和長崎銭類の錯笵
明和期以降は比較的背ズレや背多重輪の錯笵が多くみられます。なかでも長崎銭の類は新寛永の中でも、戯作・贋作を含み錯笵・面背逆製は最多の部類です。 |
 |
| 強烈な母銭の押し付け 反作用で凹みがある。これは自然な錯笵現象。戯作か。 |
|
 |
| 背長が消えているので母銭の後押し付けによるものか。戯作の類。 |
|
 |
| きれいな砂笵ずれの背ズレ。戯作あるいは近代の贋作の可能性が高い。 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
古寛永 母銭の押し付け
私の錯笵銭収集第一号。 |
|
古寛永 母銭の押し付け
たしか青寶樓の愛蔵品だったと思う。 |
|
新寛永 落下・置き直しによるうっすら景色。上部は落下物。複合的で戯作の類だろうか。 |
|
新寛永 輪の重なりの矛盾が多く、かなり意図的。自然なものではない。 |
|
 |
|
 |
|
 |
明和期 置き直しの典型例
。母銭を落した後に拾って置き直したのではないか。 |
|
文政期 戯作か贋作
銭間隔が近すぎ、鋳造の湯道が切れないので自然の錯笵ではない |
|
文久永寶 引き押しもしくは母銭の重なり
これは自然な錯笵の可能性あり |
|
 |
| |
 |
 |
| |
文久永寶 母銭間隔が狭すぎるし、配置の方向がバラバラで妖しい。ただ、文久のこの手の錯笵は非常に多い。銭座職人がかかわり意図的に作った企画ものと考えられないことはない。実際に流通した錯笵銭も多い。 |
|
文久永寶
砂笵のズレ 戯作・贋作の両方の可能性がある |
|
|
| |
4月11日【多重輪錯笵銭のおさらい】
錯笵の中でもっとも派手なのが多重輪の錯笵。これができるまでには原因によっていくつかのパターンがあります。複合的な多重輪の場合は、自然にできたとは考え難いものが多いです。鋳造によって凸と凹は反転します。これを考えることは頭の良いトレーニングになりますが・・・実にややこしい。以下にいくつかのパターンを示します。
❶鋳造の際、面側と背側の笵が何らかの原因により大きくずれてしまう。
意図的なもの、事故を含めて型〆の作業もしくは鋳込みの作業中に生じます。通常は型の浅い背側の位置がずれます。背側は型どりが浅いためずれた場合、鋳張りのような薄片になり切断がしやすいのです。輪や銭文の重なりは生じないのですが、ずれ方により複数多重輪はよく生じます。文久永寶に多く見られます。
❷母銭を置きなおした結果のもの。
母銭は手作業で面を上にして砂笵に並べます。湯道を切る関係や、面背を逆置きしてしまったため置きなおす場合があり、最初に置いた母銭の跡が地の部分にうっすら残る場合があります。デザインの重なりは生じますが、普通はあとからつけられた正規のデザインの方が強くなります。
置きなおす前に整地をする事を省略した場合、置きなおす前の母銭の押し付けが思いのほか強かった場合、派手な錯笵になります。
❸砂笵を表裏分離したあとから再び母銭を押し付けてしまったもの。
これが一番多いと思います。砂笵の上下分離後に砂笵に母銭を落下させたり、落した母銭を拾う際に強く砂笵に押しつけた場合は、反作用として落下・押し付けした周囲の砂が盛り上がります。その結果、落した母銭の周囲に鋳造後に凹みができます。ただし、母銭を引きずるように斜めに押し付けると砂笵が削られて凸になる場合もあります。意図的に押し付けた事例も多く見られるため、見た目に美しいものも多く、目立ちます。元のデザインの上に押し付けられるため、後から押し付けた本来ではない「ずれたデザイン」の方も明瞭になります。なお、このケースは重なりによって本来のデザインの一部が消えることになります。
❹砂笵を踏み固める作業の中で母銭が外れて2枚が重なって象られたもの。初めから意図して作ることはあっても、通常の錯笵としては発生の可能性はありますが、あっても流通するのは稀でしょう。このケースは重なった部分が極肉厚で超立体的な錯笵になると思われます。また、母銭が重なった輪の際先の部分は砂笵の空洞が生じやすく、輪の外側が凸に盛り上がり、上になった母銭のデザインがよく鋳だされなくなるはずです。
錯笵の法則として、
①あとからつけれたデザインはその前のデザインに上書きすることになるので、少なくとも凸部は途切れることはありません。輪が不自然に途切れたりする場合は意図的な加工が入っている可能性が大きい。
②あとからつけられたデザインでも凹部分(銭の地の部分)には前に押されたデザインが残りやすい。逆説的に言うと凹部分が外周にまで及んでいる場合は相当強く押し付けられたか、前のデザイン(輪など)を意図的に壊したものと考えられます。
③反作用で砂笵が盛り上がった部分は鋳造では凹の溝になる。鋳造によって凸凹は反転するので良く考えること。
上記条件を考慮して雑銭掲示板の錯笵古寛永をもう一度考察しなおします。
右側
❶ずれた寛永の地(凹)が外周まで浸食して達している。このことからずれた寛永が一番最後に押し付けられた事が分かります。凹(地)の部分に輪の痕跡はありません。掻き壊された可能性があります。
❷輪がうっすらあるようなないような。
❸ずれた寛永の輪の外側が埋まっている。(本来は凹)意図適か?鋳砂を彫って整地して元の外輪とつなげたのか?
※地味ながら意図的っぽいですね。全体の型ずれの可能性も0ではない。
左側
❹輪がずれた寛永のデザインを途切れさせている。つまりこの部分(輪)が最後に押し付けられたことになる。
❺穿も輪によって途切れている。ここまでは矛盾はない。
❻❼外周輪が途切れ、ここではずれた寛永の方が後押しになって逆転している。大きな矛盾。ずれた寛永のデザインの地の部分も外周に達している。つまり、元の輪部より後に押されたことになる。本来あるはずの輪(砂笵では凹)に余剰の砂を埋めて❻を平な台地に成型したのではないか?
❽凹部。落下の反作用によってできたもの。砂笵では盛り上がりになっていたはず。
※色々矛盾点があるので、意図的に作られた可能性大。ずれた寛永を押し付けた後、❹の輪の部分の一部を意図的に押した・・・斜めに母銭を傾けて❻の部分を壊さないように押した、あるいは❻の部分は押した後で成型しなおしたのかもしれません。それとも❹❺の部分は最後に手彫り成型したのかも。とにかく作為的です。
|
 |
| |
| 4月10日【他人の空似か兄弟か? 瘤足寶の類】 |
❶長郭手鋳写細縁小様純赤銅銭
→ 長郭手瘤足寶 磨輪赤銅質小様
中見切り風でやや深背?
2017/8/15制作日記 |
 |
 |
長径48.0㎜ 短径31.5㎜
銭文径40.9㎜ 重量19.6g |
❷長郭手覆輪 → 長郭手覆輪瘤足寶
左極印は逆打ち 右極印は破損
2024/5/11制作日記 |
 |
 |
長径49.35㎜ 短径32.2㎜
銭文径41.1㎜ 重量21.9g |
 |
 |
❸長郭手覆輪存痕
→ 長郭手覆輪瘤足寶(覆輪存痕)
2012/3/7制作日記 |
 |
 |
長径49.35㎜ 短径32.4㎜
銭文径41.0㎜ 重量23.4g |
❹長郭手覆輪 → 長郭手覆輪瘤足寶
制作日記未載? |
 |
 |
長径49.25㎜ 短径31.0㎜
銭文径41.0㎜ 重量19.4g |
机の上が片付かない。購入したコインの整理が追い付かない。というより、撮影したあとに放置しています。ラベルもつけず、むき出しも多いので、もはや収拾困難・・・でも収集やめられない?嗚呼~
さて、身内に早すぎる不幸があって2日ほど仕事を休みました。本日ようやくひと段落が付きましたが、明日はまた親父様の受診・・・自由時間がない。
で、ぼんやりと古い収集品を見ていたら脳裏にひらめくものが・・・デジャブ?
でもって❶と❷を並べてみた。
結論から言うとかなりの確率で元になった母銭は同系統だと思います。
ほとんど加刀のない書体で、銅質も製作も全然違う。極印は似ている所もあるものの同一とは断定できません。
しかし、寶貝上横引きが細くなる癖、寶前足の形状(異足寶)、當冠右側の瑕、背百の第一画の横引き末尾の爪など、癖が同じなのです。これはシークレットマーク的なものかもしれません。
記事を書き終えたと思いながらHPを眺めていたらありゃま、同じものがまだある・・・さらにその現物を探していたらHP未掲載の物がもう一枚見つかった。案外多いのかもしれません。
そういえばこの類、以前関西のTさんが発表していたような気がしてきた。もしそうなら、何がデジャブだ、単なる物忘れじゃないか。
まあ、寶足に変な「こぶ」があるので瘤足寶(りゅうそくほう)と仮称しておきます。Tさん教えて!
特徴
1)一度写しの覆輪銭が基本。
2)寶前足が肥で靴のよう。
3)寶貝の上横引きが細い。
4)當冠のツ右に鋳だまり段差あり。
5)百横引末端がこぶ状。
銅質は本座に似ている。ただし、赤銅質、磨輪されて細縁になっているものもある。
ひとり言・・・
今回亡くなったのは姉なんですけど、不思議な人でした。男女を問わず恐ろしく人気があり日本全国から弔問客が来た。普通、自宅でマッサージ師を趣味的にやっている専業主婦なら弔問客は限られるのに、数回しか会ったことのない地方の人まで来ていた。高校生の頃、某プロ野球球団の追っかけをやっていて当時の主力選手ほとんどに可愛がられていた。最近はマイナー歌手の追っかけを夫婦でしていました。その結果、今回は病院がミニコンサート会場になった。絶対安静状態なのに病院スタッフが屋上まで連れて行き花見もできた。公立の病院なのに。音夢食堂という歌手も応援していた。解散したけど自宅まで弔問に来た。年金暮らしでお金がないのに、横のつながりが異様に強く、皆が放っておけない存在だったみたい。ついには葬儀場に人が入り切れなくなり入れ替え制に急遽なった。人を引き付けるパワーがすごく、男女、年代を問わない。ある意味モンスター。中学校時代から目立っていて皆に人気があったけど、最後まで人気者のままだった。身内だけどここまですごいとは思わなかった。合掌。
息子は3人いるけど、皆身長がが180㎝以上あるし超イケメンだし、性格もいい。私・・・血が繋がってないのかな。他人の空似もない。
|
| |
| 4月9日【水戸濶字退寶の怪】 |
雑銭を選っていて濶字退寶に出会うと、一瞬どきりとして、その後はなーんだ、濶字退寶かあ・・・と思う方が多いと思います。しかし、この濶字退寶は銭形は濶縁の小判型でまるで揚足寶みたいだし、書体も異様でいやが応なく目立ちます。ロットものジャンク品の呼び水的な商品(疑似餌)として良く登場します。
ところでこの濶字退寶、水戸鋳という説とともに南部鋳という説もある。
水戸藩とされた理由はこの銅母銭複数枚が昭和のはじめに短足寶の錫母10枚ほどとともに水戸方面で発見され、常陽銀行に納められたことから。発見の報告者はちょっと胡散臭い木村昌古堂師。水戸方面から出たとは彼の言葉ですけど、普通ブローカーは絶対に出所を明かさないので妖しい。短足寶と濶字退寶は同炉とみられていて、見つかった短足寶が錫母というのもポイント。錫母の技術は金座の専売特許で、銀座さえ知らなかったというのは有名なお話(このお話は誤りでした。)。その技術を使うとは、幕府に近い水戸藩あるいは冶金技術にたけた南部藩ぐらいでしょうから裏付けにもなる。
一方、南部藩説はあの新渡戸仙岳先生の書き残したメモが根拠になっています。この件は小笠原白雲や沢井師なども探求されているのですが、とるに足らない風聞だととりあわない方もいます。しかし、書体に関する記述や書体そのものの写しなどどう見ても南部藩(梁川)としか考えられない資料もある。さらに濶字退寶に八つ手極印のあるものを複数お持ちになっているというコレクターもいらっしゃいました。八つ手極印は南部小字に見られる異極印で、命名者は天保仙人様だったんじゃなかったかな。もっともこの濶字退寶には近代贋作もあり、その極印が八つ手風の可能性もある。木村の話以外では濶字退寶が水戸銭というのは短足寶の花押のヒゲが背異類に似ているということぐらいですので、濶字退寶は水戸藩銭というより称:水戸藩銭というべきなのかもしれません。遒勁や大字、接郭なんかもどうなんでしょうかね。水戸銭は古寛永でもあいまいですから。
なお、手替わりのほぼない品と言われる濶字退寶ですが、刔輪銭が雑銭掲示板で発表されています。
→ 制作日記2023/4/3
→ 制作日記2021/7/6
→ 制作日記2019/1/30
→ 制作日記2017/12/13
→ 制作日記2015/3/23
|
| |
| 4月2日【HP不掲載のB級品?】 |
| 長郭手 覆輪 |
 |
 |
長径48.7㎜ 短径32.5㎜
銭文径40.4㎜ 重量20.7g |
| 長郭手 鋳写 |
 |
 |
長径48.55㎜ 短径32.0㎜
銭文径41.1㎜ 重量23.0g |
覆輪写しの長郭手。机の上に転がっていました。とらさんなどには見向きもされない品だと思いますがどうしてこいつがほったらかしになっていたのかがわからない。それともどこかに掲載していたか、数年分振り返ったけど見つからない。誰か探して教えてください。本当に未掲載かもしれませんが、平凡ながら奇麗な方なのでこのクラスでも私は普通話題にしますので。覆輪で横太りで郭内べったりヤスリ・・・私にとってはAクラスと言っても良い品です。
2枚目は正真正銘のCクラスと言っても良いかな。長郭手の直写しで穿内べったりやすりでちょっと重い・・・あとはなし。以上。
最近の私の感覚・・・壊れてますか?
| クラス |
目安 |
| 超S級 |
30万円以上 |
| S級 |
30万円未満 |
| A-1級 |
15万円未満 |
| A-2級 |
10万円未満 |
| A-3級 |
5万円未満 |
| B級 |
2.5万円未満 |
| C級 |
1万円未満 |
|
| |
| 3月29日【胡散臭い異製作の者たち2】 |
| ❶長郭手覆輪陰起文(無極印) |
 |
 |
長径49.0㎜ 短径32.5㎜
銭文径40.9㎜ 重量22.7g |
| ❷長郭手覆輪肥頭通(鋳割れ) |
 |
 |
長径49.45㎜ 短径32.25㎜
銭文径41.2㎜ 重量17.8g |
❸長郭手鋳写厚肉楔形
天側肉厚3.6㎜ 寶側肉厚2.3㎜ |
 |
 |
長径49.25㎜ 短径32.4㎜
銭文径41.0㎜ 重量26.1g |
| ❹細郭手強刔輪削字削花押 |
 |
 |
長径48.4㎜ 短径31.8㎜
銭文径40.2㎜ 重量19.0g |
【無極印】
極印のない天保通寶は流通銭としては失格だと言われます。極印の持つ意味は文盲の多かった時代において私たちが考える以上に重要な意味を持っていたと考えられます。桐極印は品質の証で、それがない天保通寶は贋物であると見なされ受け取り拒否の対象にもなったようです。しかし・・・幕府が力を失い、粗悪な密鋳鉄銭(銑銭)が大量横行した結果、インフレが昂進した幕末においては銅の天保通寶は極印がなくても受け入れ拒否されずに流通できたのかもしれません。
❶の天保通寶は湯圧が足らず文字貧弱で地肌も波うちます。しかし、地金の規格は充分で鋳造のでき以外はむしろ立派。できの悪さに密鋳銭座の棟梁が極印を打たなかったのかも・・・なんてね。
【鋳割れ】
これはエラーと言いますか偶然の傷ですね。覆輪の幅広銭形ですけど、かなり薄肉。そのせいか鋳型にひび割れができてしまい鋳割れが稲妻のように走っています。天保通寶は砂笵による鋳造なので、こうした失敗はつきものです。ただし、本来は失敗のほとんどは市場に出てこないものなのです。この天保通寶は文字も濶字気味になっていますので、あるいは母銭を延展したのかとも考えちゃいます。天保銭の場合、面文が大きく、こういった傷は目立つし、不吉なので鋳割れは意外に少ないです。
【楔型】
一枚の天保銭でも部分によって極端に厚みが異なる変なものが稀にあります。多くは上下で厚みが異なるものですが、中には左右で異なるものもあり、楔型と命名されています。もちろん、母銭がこのような形であるはずもありません。
原因として考えられるのは鋳型から母銭を外す工程の際に指などで母銭を砂笵に押し込んでしまうこと。その結果、押し込まれた側がとくに肉厚になります。加えて鋳造時の型〆作業の不良や、鋳砂の踏み固め不十分も厚みが不均一になる原因と考えられています。
手作りである天保銭は、実は多少の厚みの差があるのがむしろ普通なのですが、❸の天保銭は最高肉厚3.6㎜、最低肉厚2.3㎜と、約1.3㎜もの差がある有名品です。秋田の村上師の愛蔵品。
不知分類譜下巻P194の10
英泉分類譜1032 原品
【削字】
削字は多くの不知銭で、文字抜けを良くし、鋳造上のミスを最小限に抑える目的で行われています。文盲が多かった時代ですので、多少の文字変形は目をつむったのでしょうけど、中にはどうしてこんなことになったのかと首をひねるようなものもあります。
❹はそこまでのものではありませんが輪際と背の文字周囲に強い加刀痕跡が残されています。前所有者はたしか暴々鶏師でこのぐりぐりッとした刀跡を気に入られていたと思います。面側は細字。寶後足は輪から離れ、跛寶になり、背は鋳浚い痕跡が強く残り、當百、花押の形が歪むほど加刀されています。花押の強い削字は珍しいと思います。
|
| |
| 3月28日【胡散臭い異製作の者たち】 |
| ❶長郭手白銅質天上削輪 |
 |
 |
長径48.5㎜ 短径31.8㎜
銭文径41.6㎜ 重量20.9g |
| ❷長郭手鋳写細縁赤銅捻形 |
 |
 |
長径48.0㎜ 短径31.45㎜
銭文径41.15㎜ 重量20.1g |
長郭手異書覆輪撫角楕円銭
不知天保通寶分類譜
英泉天保通寶研究分類譜第四巻 原品 |
 |
 |
長径48.6㎜ 短径32.3㎜
銭文径40.45㎜ 重量22.9g |
❶白銀~白黄色の天保通寶です。側面の仕上のやすり目は不規則で細かく、幾分時代が降る雰囲気があるものの極印も不鮮明ながら残り、全体の印象としてはさほど悪くありません。
文字変化はほとんどありませんが、加刀痕跡が文字周囲に残り、細字気味に仕上がっています。鋳写天保なのに計測するとなぜか銭文径が大きく出ます。拡大してみると天上の輪に沿って強い加刀が見られ、天の第一画上部が盛り上がり太く一体化していることが分かります。
刔輪というより、母銭の鋳だまりを取り除くため加刀したのではないでしょうか。拡大画像は荒々しく見えますが、切り口はギザつきながらも切り立って案外滑らかです。
❷は雑銭掲示板で最近話題になった面ズレ天保。この天保は右下から左上に向かって立体的にずれています。そのためスキャナー画像に郭の内側や輪の側面がわずかに写りこんでいます。
左右は銭を裏返すときに縦軸回転なので位置が置換されるので銭を裏返しても表裏の傾斜の位置向きは変わりませんが、上下は縦軸回転では位置が置換されないので、傾斜の位置が異なって見えるようになります。画像では面は左と上の穿内傾斜が見えますが、背は左と下の穿内傾斜が見えています。
輪の太さで見ると向かって右側が太くなっていますが、上下に関しては面側は上が細く下が太いものの、裏返すと上がやや太くなっています。少し不思議な感覚ですけどよく考えてみてください。小さいけれど重みを感じる銅質です。
❸は通称:撫角銭。各種泉譜を飾った品でありますが、いまのところ一品ものの雰囲気です。小さいのに重いし、文字は変だし、鋳肌も形もいびつ。撫角とは仙台通寶鉄銭にもついていた愛称で、四角形の四隅が丸い形のこと。
表面が砥石で丁寧に磨き上げられているので絵銭的な雰囲気が漂い、大量生産風ではありません。
その昔、この天保銭を暴々鶏師に見て頂いていたところ「ふふふ・・・」としか返ってこなかった。一見、深淵風の傾斜があるのですが文字の周囲が深く彫り込まれているつくり。ところが側面のつくりはいたってまじめ・・・この中では抜群。胡散臭度50%珍品度50%の天下一品ものです。類品をお持ちの方、いらっしゃいますか? |
| |
| 3月27日【これぞ宏足寶:細縁大字大様の宏足寶】 |
長郭手
覆輪強刔輪宏足寶白銅銭 |
長郭手
覆輪強刔輪宏足寶背強刔輪 |
長径49.6㎜ 短径32.7㎜
銭文径41.15㎜ 重量25.0g |
長径49.8㎜ 短径33.0㎜
銭文径41.2㎜ 重量26.4g |
 |
 |
 |
 |
| |
當上の刔輪強い |
 |
髭先端跳ねる
袋下角に凹穴 |
下髭鋳切れる
袋の中に小星 |
| ※ブラウザによっては右の天保通寶の赤みが濃く見えることがあるかもしれませんが実物は淡黄褐色です。 |
前日の制作日記の天保通寶も宏足寶としても良いのですがこの2枚を見てしまうと、やっぱね~と思ってしまいます。迫力が段違いでしょう?
3月26日の❶が長径49.0㎜、❷が49.2㎜ですから長径的には0.8~0.4㎜ほどの差。銭文径も0.7~0.6㎜ほど・・・つまり1㎜にも満たないのですが、目視でも風格が違いますよね。当然、重さも立派。
実はこの下に少し濶縁縮字になる次鋳銭が存在し、泉譜では長宏足寶の名称がつけられていることが多いのですが、ここに掲示する品より足が長いわけではないので私は宏足寶(濶縁)縮字ともしくは宏足寶次鋳(濶縁)とすべきかと思います。
なお、この宏足寶(濶縁)縮字のタイプには人偏のノ画の下に小星が縦に2個並ぶ特徴があります。(このことは関西のTさんからご指摘を受けてました。)すべてそうだとは限りませんが詳しくは
に掲載してありますので是非ご一読ください。
このコーナーは天保仙人様の自宅を訪問して、絶対的珍品の数々を取材させていただいたもの。「縮字宏足寶」は宏足寶(濶縁)縮字とはまったく別種の天下無双の大珍品です。この画像が見られるのはこのコーナーだけですよ。
さて、細縁大字になるこの宏足寶2種ですけど、宏足寶の原種・元祖というべき存在ながら、泉譜の評価は6~8万円とそれほど高くありません。ちょっと奮発すれば駆け出しの収集家でも買えないことはないレベルの品。とはいえ人気は抜群・見た目は十分ですので美銭に出会ったら絶対逃さないことです。花押の髭や袋に分類のポイントがありますので覚えておくと便利ですよ。
泉譜を紐解くといろいろな宏足寶が掲載されています。私も張足寶や宏足寶の名称が好きで、つい甘くなってこれらの名称を使用してしまっていますが、本来の宏足寶はこの書体の系統がすべて・・・他は亜種・別種・もどきなのでご注意ください。 |
| |
| 3月26日【埋もれた収集品】 |
| ❶長郭手 覆輪(強)刔輪深彫 |
 |
 |
長径49.0㎜ 短径32.3㎜
銭文径40.55㎜ 重量19.3g |
| 長郭手 覆輪(強)刔輪 |
 |
 |
長径49.2㎜ 短径32.55㎜
銭文径40.5㎜ 重量19.1g |
アルバムに入ってはいるものの制作日記に記事が見いだせない(どこに書いたか分からなくなっている)ものがあります。画像番号の若い比較的初期の入手品に多く見られます。最近は新規入手品がないので当面こういったものでお茶を濁そうかと思います。
❶は雑銭の会のボイスオークションで、最後はじゃんけんになって購入できた品じゃなかったかな。深字で輪に向かって地に傾斜があり、最初は深淵様と名付けていたと思います。強刔輪としていますが天側にはほとんど刔輪がありません。本座に近い純黄色で宏足寶としても良い形状で高頭通。この頃はまだ天保通寶が再加熱していなかったので2万円ちょっとぐらいしかしなかったと思うのです。
❷こいつはもうどうやって入手したのかさっぱりわからない。多分上の品と同じ系統ですね。宏足寶と張足寶の中間風で、かつ地に深淵のような傾斜がある。ただし、こちらはそれほど深字ではなく通頭は嘴のように先端が尖っています。❶❷とも當上に刔輪があり❷のほうが背全体的に少し強い刔輪が入っていると思います。寶足の間に朱点が入っている。三上香哉辺りの収集符丁じゃなかったかしら?どこかの泉譜に掲載されているかもしれない。ご存知の方、お教えください。 |
| |
| 3月25日【五十肩になったぞ、目出度い!】 |
| 長郭手赤銅質覆輪(再写小足寶) |
 |
 |
長径48.15㎜ 短径31.65㎜
銭文径40.25㎜ 重量17.0g |
| 長郭手覆輪再写異極印(UFO型) |
 |
 |
 長径48.9㎜ 短径32.5㎜ 長径48.9㎜ 短径32.5㎜
銭文径40.65㎜ 重量18.4g |
突然左肩の付け根に激痛が走った。筋肉痛というより骨がすれるような神経系の痛み。鎖骨の接合部が痛い。熱感はあまりない。病院に行ったら五十肩だろうと言われた。ちょっと違うんでないかいと思いながらも、何であれ結果としてやることは変わらない。姿勢を正しく、そして安静に・・・なのである。診断名が実年齢より若返ったのは微笑ましいが、親父様の怪我(右肩峰部脱臼)と出現症状があまり変わらない。元々痛みには強い(鈍い)ほうなのですが、神経的な痛みは別。身の置き所がなく痛くて眠れない。そういう時は古銭が薬、とはいえ新規入手がないので昨年の獲物を再観察。首が前に出てしまうパソコン作業は最悪なんですけどね・・・。
長郭手赤銅質覆輪(再写小足寶)は駿河の落札品。赤黒い再写しの覆輪銭。
こういった覆輪銭は刔輪で長足法になるのが普通なんですけど、寶足が削られて短くなる小足寶になっています。このような変化はありそうで意外に少ない。圧倒的に寶足は長く変化するものが多いからです。
長郭手覆輪再写異極印(UFO型)
はCCFの落札品で出品名は不知長郭手強覆輪2次写しでした。特徴は覆輪であることに加えて、半月型の異極印であること。普通、こんなふざけた異極印は、贋だとしたものなんですけど、こいつはまとも。よく観察すると、半月を貫くように縦方向の細い筋が残っているので半月は極太に変化した葉脈形状らしいことが判ります。つまりこれでも桐極印のつもりらしい。洋傘型極印というべきか?この極印はこれで2枚目の確認です。 |
| |
3月23日【同炉銭は誰がどうやって確定したのか?】
奇天、奇天手、張点保は風貌、製作などから同炉だと判断するのは容易だと思われます。
長郭手塞頭通と異頭通はスタート時は仰天、仰頭通と別々でしたが、拓本は隣り合わせの泉譜が多く早くから同炉であると言われていたようです。しかし、そこに中郭手小点尓が同炉とされた経緯は不明。中郭手小点尓は本座に似た黄色い銅色で、尨字類とはかなり異なるのでこれを同炉と判断するには相当の知識と考察力が必要だからです。少なくとも画像じゃわからない。
同様に細郭手短尾通細字と抱冠寶、崩字にも共通点を見出すのはかなり難しいと思います。これに気づいた人はすごい眼力の持ち主ですね。
| 張点保・奇天手 |
 |
| 短尾通細字系 |
 |
花桐極印(細郭手)
長郭手もある |
 |
一方、書体はそっくりなのに別炉とされているのが小字の長人偏と短人偏の類。はじめは短人偏を薩摩小字としていたのが長人偏の出現により薩摩小字(短人偏)と不知小字(長人偏)に分けられ、現在は不知小字短人偏・長人偏になっています。後世の写しもかなり混じっていることが予測されますが、これだけ個性的な書体が他人の空似というはずもなく、どこかで合流が必要だと私は思っています。
もっと劇的に変化したのは平通で、昔は土佐平通でしたが今は萩平通です。これについては3月2日の製作日記をお読み頂ければ、私が抱いているもやもやした気持ちがお分かり頂けると思います。書体の類似性を採るのか、製作の類似性を採るのか・・・これには土佐通寶を見出したSE氏の関与を疑う(平通に似せて土佐通寶を創作した)・・・なんて恐ろしい私の妄想もあるのですが、たぶん違うでしょう。
互いに異なる書体の天保銭を同炉であることを証明するのに役立つのが極印の同一性。
奇天手と張天保の極印が同じだったときは感動しました。また、短尾通細字と抱冠寶にも同じような個性的極印が使われていることも確認できました。さらにその極印とそっくりな極印が打たれている覆輪の長郭手も発見したのですが、今のところ確認は1枚のみなので何とも言えません。
私が「花桐極印」と呼んでいる一群の覆輪写しの不知銭も、長郭と細郭の書体があり、製作・銅質もほぼ同じであることが判っています。この一群は製作も安定していて数量も結構多いと思います。
誰も触れませんが水戸藩銭には大きな疑問が付いて回ります。面は奔字と呼ばれるオリジナルな雄大書体、背は一転してこじんまり書体の大字、覆輪刔輪技法の接郭、硬い金質で個性的な書体の濶字退寶と短足寶、本座に酷似した背異、繊字。銅質が異なり石持桐極印系とみられる正字~背異の類と深字、藩鋳銭きっての稀品の揚足寶など、何でもありです。もともと古寛永が水戸銭は寄せ集め的で、古銭界でも新発見は水戸から出る・・・という妖しい話がちらほら。新寛永や地方銭の水戸銭は私は怖くて手が出せません。
短尾通細字と同じ極印の長郭手
他人の空似かなあ? |
 |
というわけで私の意見と疑問
❶中郭手小点尓が尨字の類とされたきっかけと理由が知りたい!
❷短尾通細字と抱冠寶、崩字が同類と見出した人とその理由が知りたい!
❸不知小字は起源書体が同一なのでひとまず統合すべきではないのか?
❹平通は本当に萩藩のままで良いのだろうか?
❺水戸藩銭と石持桐極印銭・・・もう一度整理しなおすべきではないのか?
②の謎が解ければこの長郭手の謎も解けるかもしれない。 |
| |
3月22日【不接培の塞頭通?】
不知長郭手の塞頭通の類は通頭の中央が盛り上がって三角形を描く「塞頭通」とフのように口が開く「異頭通」がある超有名不知銭です。(その他に中郭手の小天尓寶が同類とされています。)天保仙人様はこの稀品を天保通寶五大奉行の一員として取り上げていました。
昭和10年版の天保銭図譜(青寶樓著)で塞頭通は「仰天」、異頭通は「仰頭通」として掲載されたのが始まりのようです。本座長郭はもともと仰天気味なので、それを模した長郭手もその傾向を引くものが多いのですけど、塞頭通は保の口が若干左下がりなので、とくに強調されて仰天に見えるのかもしれません。文字を拡大して見ますとロクロ錐等で加刀・加工された痕跡が随所に残っています。
異頭通は昭和泉譜において「尨字:ぼうじ」と名付けられたようで、やや小様の濶縁肥字の異頭通のみが掲載されています。「尨」の文字は「むくいぬ」を意味する漢字で、独特の書体がころころした巻き毛の犬を連想させる意味らしく、やや肥字のものが多い異頭通のための源氏名だとか。
さらに天保泉譜の前身である大橋譜では塞頭通を「仰天」、異頭通を「仰天仰頭通」として、その他に當字の田の中央横引きが左縦画から離れる「仰天仰頭通不接培」の3種が掲載されています。
天保泉譜(勢陽譜1974年・原本は1956年)では異頭通を「尨字」として、「尨字不接培」の2手のみ掲載され、塞頭通は掲載されていません。さらに新訂天保銭図譜(小川譜1975年)では「塞頭通」の他に、濶縁肥字のものを「異頭通」として掲載されていてこれが現在の分類の主流になっています。これは天保銭事典(1976年)でも同様であり、當百銭カタログ(1995年)では「塞頭通」と「異頭通(尨字)」と表示されていて、尨字の名前が復活しています。ところが一番新しい天保通寶と類似貨幣カタログ(2007年)では「塞頭通」と「尨字」と・・・なんと「異頭通」の名前が消えてしまいました。ちなみに2007年版の類似貨幣カタログにおいて、「尨字」の背の拓が間違えられているような気がします。ご確認ください。花押の形が違うと思うのですが印刷上の変化かなあ。(重版で訂正されているかもしれません。)
「塞頭通」と「異頭通」の違いは通頭の他に「異頭通」の方が広郭気味とか、文字が太く大きいとの表記が泉譜にありますが「異頭通」の方が拓本では濶縁で次鋳っぽい雰囲気もあります。私には砥ぎの強さの差じゃないかとも思えますが異頭通は持っていないので良く分かりません。
なお、「不接培」は當の田の左端が削られて縦画に接しない物を言います。造語のようですけど若干意味不明。接ぎ木がうまくいかなかった、根付いていないという意味でしょうか?
ところで私所有の塞頭通は打ち瑕なのか鋳不足なのか良く分からないのですが、通頭はわずかに開いていますし、「不接培」にもなっています。書風は間違いなく塞頭通ですけど、拓本に採ると微妙な感じにきっとなります。「尨字」と言い「不接培」と言い、必ずしも分かりやすく適切な命名ではないので、良い名称はないでしょうか?
また、當百銭カタログにおける塞頭通の価格は60万円、異頭通は80万円で、奇天手65万円に勝るとも劣らない別格評価だったんですよ。薩摩小字や広穿大字、張点保なんて足元にも及ばないです。時代ですね。 |
| |
3月21日【最近の贋作事情】
隣国の経済的混乱と自由奔放な考え方、技術の向上と昔のコレクターの引退から最近新たな贋作の流入が増えています。ここのところ私もかなり痛手をこうむりました。以下は私の雑感です。
1.大陸発の贋作
主に母銭からの正確な写しが大量流入しています。
真鍮色の鉄母銭類、水戸系、幕末地方貨は特に要注意。近代のコピー技術が使われています。琉球通寶は新作・写しとも花盛りです。大きさや書体、製作はもちろん、色味にも注意が必要です。
天保通寶母銭、小菅、十字寛など画像ではまずわからない。こうしたものが狙われるのは、側面のやすり掛けがないから、不自然さが出にくいのです。こういった類のものは状態表示鑑定格付のプラスチックケース(スラブ)に入っているものも多く見られます。奇麗すぎる物は怖いんです。
高額の物より、比較的安価な数万円クラスのものが増えています。
2.引退収集者からの流出
コレクターが引退し、あるいは鬼籍に入ることで今まで雑銭箱に放り込まれて出てこなかった過去の贋作・変造品の流出が始まっています。中には鑑定書が添付されているものがありますが当てになりません。
少し前に流行したドリル変造、川口和同、中国地方発の二水永、美大生作の鋳ざらい銭、銀座古銭堂作の遒勁、昭和浄法寺、ラムスデン、加賀千代など名作も多い。私が少し前に引っ掛かった会津の大濶縁は、往時の収集家そのものがだまされた名作ですね。遒勁、筑前、盛岡銅山、仙台大濶縁なんて怖くて(高くて?)手が出せない。中には本物としてすでに認定されてしまったものもあるから困りものです。
4.ネット販売者の暗躍
ネットは贋作販売の温床ですね。そこから古銭店店頭に流れてます。自浄能力がないですね。同じ商品を何度も出品する業者、途中で入札をやめてもう一度出してくる業者には要注意。ばれないか見極めをしている場合もあります。営業妨害・画像著作権の問題もありますので、批判記事はうかつに書けないのですが・・・。画像マジックも良くありますのでぬか喜びはしないように・・・。金銀貨、近代貨幣、エラー貨は魑魅魍魎の世界です。
おまけ・・・贋作にしか見えない本物もある!
室場天保(石ノ巻反玉寶)鋳放しは見た目も出現経緯もOUTだと思った。しかし、実際に流通している仕上銭はまったく自然で、それが同一品にはとても見えないのです。しかし、このことから室場天保(石ノ巻反玉寶)鋳放しは真品であることが判っています。この天保銭にヒントを得て生まれたと思われるのがいわゆる昭和浄法寺。浄法寺には流通を目的に作られたもの、絵銭としてつくられたもの、コレクター目当てに作られたものがあるようです。
もちろん本物にしか見えない贋作はたくさんあります。少し前にはやった円銀のダイヤ光、穴ずれ・無孔50円などは金型技術の応用から刻印のコピー技術まで駆使しているのではないかしら。雑銭掲示板にHさんが載せた遒勁などは画像ではほとんど判別できない。金質が硬い・・・これは仙人様のような達人クラスじゃないと判らないですね。その昔、日本橋にあった賞山堂の店頭に、真っ二つに切断された享保大判がありましたっけ。あれも店主が「硬い」と贋作判断して確認のために切断したとありました。恐らく福西作でしょう。私が奇天手を入手したとき、あまりの美しさに本物に見えないと仙人様に打ち明けたところ「極印をみてごらん」と仙人様に品物を見ずに口頭指導されました。そこには私が学生時代に偶然掘り出した張点保と同じ極印がありました。まさに神の眼です。やはり、有識者には師事するもの、古銭会参加は重要だなあと感じた出来事でした。
|
| |
❶長郭手覆輪強刔輪宏足寶背上辺削郭
長径49.1㎜ 短径33.2㎜
銭文径40.6㎜ 重量27.6g |
 |
 |
| |
TMI指数1.14 肉厚3.0㎜ |
❷長郭手覆輪強刔輪厚肉
長径48.94㎜ 短径33.1㎜
銭文径40.4㎜ 重量28.3g |
 |
 |
| |
TMI指数1.18 肉厚3.1㎜ |
❸縮形美制厚肉異極印
長径47.7㎜ 短径31.8㎜
銭文径40.7㎜ 重量26.2g |
 |
 |
| |
TMI指数1.15 肉厚3.15㎜ |
❹細郭手覆輪厚肉重量銭(覆輪存痕)
長径49.5㎜ 短径33.3㎜
銭文径41.1㎜ 重量29.6g |
 |
 |
|
TMI指数1.21 肉厚3.2㎜ |
❺長郭手肥点保厚肉縮形銭(関西T氏蔵)
長径47.65㎜ 短径31.60㎜
銭文径40.06㎜ 重量28.3g TMI指数1.25
制作日記2020/10/31・2022/1/14 参照 |
 |
 |
| 表示の厚みは厚めの部分を手動計測した参考値です。3/15の深淵類との肉厚とご比較ください。 |
 |
| ❶ |
❷ |
❸ |
❹ |
|
3月18日【肉厚3㎜の世界】
人間の眼は意外に精密なもので、通常と異なる物に対してはきちんと違和感を覚えてくれます。天保通寶の標準的な重さは21g前後、厚みは2.5㎜前後が多いでしょうか。厚みが2.2㎜を切るとかなり薄く感じます(私だけかな?)。標準とたった0.3㎜しか違いはありませんから精密機械ですね。
一方、厚肉については滅多に3㎜を超えることはありません。こちらについては厚さというより重さの違いの方が敏感に反応できるようでして、個人差はあると思いますがある程度の天保銭マニアなら25gを超えると違和感を感じるのではないかと思います。(違いますか?)
さて、ここにあるものは厚みが部分的に3㎜を超える不知銭で、手にするとみなずっしりした幸せの重みを感じます。
TMI指数とは私がボディマス指数(BMI)を応用して勝ったに作った天保銭の肥厚度指数(参考値)のことで下記に計算方法を記しますのでご参考までに。この数値が大きいほど肉厚もしくは幅広で、つまりずっしり感が強くなります。
ちなみに3/15の記事に出てきた深淵系の❶❷❸❹のTMI指数は❶0.94❷0.97❸0.84❹0.87と標準~少し重い方なのでどちらかと言えば薄肉ではありません。
❶❷は代表的な厚肉天保銭で、地肌の雰囲気などは同じに見えなかったのですけど、こうやって並べて規格・極印等を比較すると同炉でもおかしくない気がしてきました。両銭ともものすごく横太りの長足寶で刔輪の強い大型厚肉銭です。
一方❸❹は細郭手の重量銭ですけど、❸は鋳写磨輪の小様銭であり、❹は覆輪の大様銭。❸はこの中では最軽量ですけどそれでも48㎜を切る小ささで26gは異常としかいえません。極印も変わっています。
❹は極小極桐極印で私の所持品中の最重量銭。(薩摩広郭と後鋳疑問品を除く)
なお、縮形の極厚肉銭は関西のT氏が47.7㎜で28.3gという異常な厚肉小様不知銭❺を所持されております。T氏は小さいのに重くて当初贋作だと思われたようですけど、製作そのものは実に素直で、銅質も決して新しい真鍮質でもなく、何よりこのようなパッとしないものを手間暇かけて贋作する理由が見当たらないので、私は問題ないと感じています。
ただし、久々に2022年の記事を読むと、内容をすっかり忘れていましたので改めて自分の眼の節穴ポンコツと妻を失ってからの記憶力の低下を感じます。制作日記2022年、2020年の記事・・・新鮮ですね。もう一度読み直さなくちゃ。皆さん大丈夫ですか?
【TMI指数と目安】
重量g÷(長径×長径㎜)×100
超薄肉 0.60
極薄肉 0.65
薄肉 0.75
標準値 0.85
厚肉 0.95
極厚肉 1.05
超厚肉 1.10
関連記事
制作日記2022/8/11 |
| |
 銅質が全く異なるので断定はできませんがやや大きな幅広極印と側面仕上げにはかなり共通性が見られます。 銅質が全く異なるので断定はできませんがやや大きな幅広極印と側面仕上げにはかなり共通性が見られます。 |
|
|
| 天保泉譜(勢陽譜)189番 長郭手覆輪深淵 |
 |
 |
❶長郭手覆輪深淵(白銅質)
長径48.6㎜ 短径32.5㎜
銭文径40.5㎜ 重量22.1g
|
 |
 |
❷長郭手覆輪深淵
長径48.9㎜ 短径32.5㎜
銭文径40.6㎜ 重量23.2g
|
 |
 |
❸長郭手深淵手額輪強刔輪(面背逆製)
長径48.7㎜ 短径32.5㎜
銭文径40.5㎜ 重量20.0g |
 |
 |
❹長郭手深淵手額輪(純赤銅質)
長径48.9㎜ 短径32.4㎜
銭文径40.7㎜ 重量20.7g
|
 |
 |
3月15日【長郭手覆輪深淵】
長郭手覆輪深淵はとても面白い不知銭です。画像では判らないのですが、地肌部分を2本の指でつまむと碁石のような曲線が指先感覚で伝わってきます。とはいえ、深淵は固有種の独占名称になり切ってなく、形状の表示の一つでもあるので、泉譜の色々なところで出会います。ですので、ここでは勢陽譜189番の覆輪で刔輪が少ない一群の類品を深淵の代表として解説します。
左の拓本は勢陽譜189番そのもので、明らかな覆輪銭。刔輪はありますが寶下など部分的で個体差があります。銅色は天保泉譜(勢陽譜)では灰黄色とありますが、実際は様々で、そのため深淵と気が付かず所持されている方々も多いと思われます。
書体的な特徴ですが、大頭通・高頭通気味で寶王と寶貝が離れる離貝寶です。また、寶貝底が左あがりの斜底寶。背當はわずかに離輪し、百の横引き先端の爪がわずかに上向きに尖る癖があります。これらの特徴はあくまでも拓本から読み取れるもので絶対というわけではありません。
❶は銅質が白黄色であり天保泉譜(勢陽譜)にほぼ正合すると思われるもの。新橋のウィンダム・ネクストで購入したもので名称の元になった深淵の特徴は文字の直下ほど肉厚で、外輪に近づくほど曲線を描くように彫が深くなる独特の作り。つまむと碁石や蛤を持っているような触感がある・・・は私の感想。実はこの特徴も個体差があり、さほど傾斜を感じないものもあるのですが輪際ほど深く抉られているのは共通です。このつくりのため、文字が浅くなりがちで「額輪」気味に見える物も多々存在すると考えています。
肥字気味に見えますが実物はそうでもないですね。寶王と寶貝の間は鋳づまっていますが離貝寶です。
❷が初めて出会った深淵で、ヤフオクでロットもののなかにこの深淵と狭足寶が入っていましたので実に興奮しました。
銅色こそ灰黄色ではないものの天保泉譜の拓本の特徴とかなり合致します。もちろんつまんだ時の感触もばっちり。指で味わう不知銭代表です。ただしこの品は天と當上の刔輪はほとんどありません。
画像で見てもはっきりわかる離貝寶。そのため、初めて見た瞬間は斜珍じゃないかと思いました。
❸は橙色に発色したもの。細字で離貝寶にはなっていません。実は面背逆製で、背が細郭広穿になっています。そのせいか深淵のつくりですが指でつまんでみても感触はあまり感じません。
そのため名称も深淵手額輪と、少しいじりました。
泉譜の深淵と正合するとは言い切れませんが、極印などにも共通性があります。良く見ると刔輪が他の物とは異なってかなり強くなっています。
❹は画像では明るく写っていますが実物はこれでもかというほど真赤なもので純赤銅銭。銅替わり大好きな私は熱狂しました。その後、❸を入手して製作がよく似ていることから類品であることに気が付きました。ただし、この品も寶王が離貝しません。また、地の傾斜もあまり感じません。さらに輪際には他にはない溝状の深い加刀も見られます。❹とは異なり天上當上の刔輪もほぼないものですが、穿内はべったりヤスリなので面背逆製的な雰囲気もあります。❸と❹は色彩的にもいわゆる異彩を放っています。
以上、4枚を挙げましたが実はこれ以外にも深淵らしきつくりの不知銭は何枚かあります。他人の空似の可能性はありますが、ポイントは似ています。
強いて言え❶と❷は間違いなく覆輪深淵、赤銅系の❸と❹は亜種もしくは別種かもしれませんが❸と❹は同炉でしょう。ただし、❸は刔輪も強く実に興味深いつくりです。
|
| |
| ❶広郭手粗造細縁薄肉 |
 |
 |
長径48.3㎜ 短径31.35㎜
銭文径40.65㎜ 重量12.6g |
【胡散度 45%】 |
|
| ❷広郭手薄肉参考銭 |
 |
 |
長径48.4㎜ 短径32.2㎜
銭文径41.1㎜ 重量16.6g |
【胡散度 95%】 |
|
| ❸長郭手異形歪曲 |
 |
 |
長径48.8㎜ 短径31.8㎜
銭文径41.2㎜ 重量17.9g |
【胡散度 49%】 |
|
| ❹広郭手細字薄肉白銅銭 |
 |
 |
 |
長径48.7㎜ 短径32.35㎜
銭文径41.05㎜ 重量15.6g |
【胡散度 20%】 |
|
| ❺萩藩銭 方字極薄肉白銅銭 |
 |
 |
長径48.5㎜ 短径32.1㎜
銭文径40.7㎜ 重量13.4g |
【胡散度 5%】 |
|
3月13日【胡散臭選手権2】
胡散臭い不知品は見ての通り広郭に多くあります。胡散臭さを数値にしていますがこれはご愛敬。お遊びです。
❶広郭手粗造細縁薄肉
マニア垂涎という言葉に呼応すれば、マニア以外絶対見向きもしない品。こういった粗造薄肉の品の多くは不知銭とは断定できない疑問品ばかりになりますので、掲示の品のように銭文径があきらかに縮み、重量も軽いという2つの特徴があるものはむしろ少ないのです。
12.6gはペラペラの薄さ。世の中重量のある天保銭は珍重されますけど、こんなみすぼらしいものに価値があるかどうかは貴方がご判断ください。本当の胡散臭さは90%はあると思う。欲しいと思う人・・・います?
❷広郭手薄肉参考銭
これを不知銭とする人は多いと思います。駆け出しのコレクターがこういった品をじゃらじゃら見せてくれることが時々ありますが、みんなには苦い顔をして見られていますよ。胡散臭さはコレクターにも伝染しますから。まだ染まるのは早い。駆け出しのうちは状態の良いものを拾いましょう。これは摩耗、焼け、薬品変造の疑いが晴れない。まともな品ではないのは分かりますが重量以外は妖しいなんて物じゃないです。本来は雑銭箱行きの品です。こんなの好きになっちゃいけません。まったく変態です。もう一つ何かが欲しい。それが私の見解。
❸長郭手異形歪曲
こりゃ火事場の熱変形じゃないの。胡散臭さは120%ですね・・・本来は。銭形だけでなく文字の配列まで歪んで乱れています。とくに穿はひし形に変形してますので目立ちます。郭の変形はときどき見られますがこりゃあ酷い。何じゃこれです。実はこの品、短尾寛方寛寶通用銭発見者のIさんからの分譲品。Iさん自身も良く分からない品として出品したのですが、仙人様曰く、鋳造工程で鋳型に強い衝撃を与えるとこんな物が出来上がることがあるとか。へぇ~ということで買っちゃった。たしかに銭文径も小さく重量も軽い。磨輪でもないのに短径が小さいのが特異。でもね~胡散臭~。
❹広郭手細字薄肉白銅銭
制作良く明らかに白銅質。銭文径は本座に近い。驚きは側面の拡大画像をご覧ください。月面のようなぼっこぼこの穴ぼこだらけ。銭内部から気泡が噴出したみたい。そして、もう一つの驚き・・・手にすると極めて軽く、叩くとものすごく安っぽい音がぺちゃんと響いてくる。まるで銭の中に空洞があるみたいな音なんだよね~。雰囲気的には3月5日の石持桐極印銭正字白銅質銭に極めて似ているのですけど、極印がはっきりしないし、この変態さは類を見ない・・・いや、ひとつありました。
❺萩藩の方字の極薄肉の白銅質銭です。製作はかなり異なりますが、こいつを机の上に落したときの音はほぼ❹と同じ。ものすごく安っぽい音なのです。
方字極薄肉白銅銭はヤフオクで数枚の組み物として入手したものなのですが、あまりの安っぽい音と軽いつくりに前所有者は玩具(レプリカ)だと誤認されており、1000円未満で入手できました。音の原因は白銅という特殊な材質が原因なのかもしれません。なお、方字は別名「薄天保」と昭和泉譜では呼称されています。18g以下のものが多く23gを超えるものは滅多にないようです。
|
| |
| 水戸背異反足寶小様(赤銅) |
 |
 |
長径47.9㎜ 短径31.75㎜
銭文径39.8㎜ 重量20.6g |
【胡散度 0%】 |
|
| 長郭手細縁薄肉小様(磨輪無極印) |
 |
 |
長径46.85㎜ 短径30.8㎜
銭文径40.2㎜ 重量18.6g |
【胡散度 55%】 |
|
3月13日【大和文庫】
衝動買いをしてしまった。水戸背異反足寶小様です。水戸背異反足寶が10000円の初値・・・誰がこんな価格の買うの?馬鹿じゃないの、こんな値段で買って・・・と、お思いになられた方・・・私がその馬鹿野郎です。普通4000~6000円止まりですね。 でも、実に美しい鮮紅色で、傷も少なく、背の文字抜けも抜群。背異反足寶でこの色で小様なんて皆無なんじゃなかろうか。これで石持桐極印だったらもう笑いが止まらない・・・という妄想が暴走してしまいました。玉がありそうに見えますが普通桐でした・・・残念。 でも、実に美しい鮮紅色で、傷も少なく、背の文字抜けも抜群。背異反足寶でこの色で小様なんて皆無なんじゃなかろうか。これで石持桐極印だったらもう笑いが止まらない・・・という妄想が暴走してしまいました。玉がありそうに見えますが普通桐でした・・・残念。
長郭手細縁小様・・・真っ黒、変造品だよ、異常すぎるよね、あぶないよ・・・とお感じの方・・・正しいです。良い子は手を出すのはためらいましょう。一度立ち止まることが必要です。
百聞は一見に如かず、虎穴に入らずんば虎子を得ず、毒食らわば皿まで、と呪文を唱えながら入札してしまった方は反省しましょう。それは私です。銭文径は2回写しレベル、寶足もちょっぴり長い・・・これは画像比較である程度分かりました。改造母銭からの写しで穿内べったりヤスリです。銅質も問題なし。(セ~フ!)ただ、磨輪はいつの段階でなされたかがわからない。無極印ですし。まあ、46㎜台は異常ですね。胡散臭いけど。
あと・・・ヤフオクで組み物の天保銭を4000円ほどで購入。私には会津濶縁に見えてしまったのですが久留米正字濶縁の背異替でした。立派な濶縁でしたので問題はないのですが磨きが入っていてちょっと残念。安物買いの銭失い。 |
| |
❶中郭手覆輪赤銅無極印
平成8年江戸コインオークション原品 |
 |
 |
長径49.75㎜ 短径33.25㎜
銭文径40.4㎜ 重量25.9g |
【胡散度 51%】 |
|
| ❷広郭手厚肉異極印白銅質 |
 |
 |
長径48.5㎜ 短径31.8㎜
銭文径41.35㎜ 重量30.6g |
【胡散度 90%】 |
|
❸広郭手縮形異極印銭
月刊天保銭53号入札品原品 |
 |
 |
長径47.9㎜ 短径31.5㎜
銭文径40.4㎜ 重量21.2g |
【胡散度 15%】 |
|
| ❹広郭手長頭辵異極印 |
 |
 |
長径48.05㎜ 短径31.8㎜
銭文径40.3㎜ 重量20.5g |
【胡散度 95%】 |
|
| ❺広郭手肥字細縁厚肉異極印 |
 |
 |
長径48.35㎜ 短径31.85㎜
銭文径41.5㎜ 重量26.6g |
【胡散度 25%】 |
|
| ❻長郭手痘痕肌 |
 |
 |
長径48.7㎜ 短径32.3㎜
銭文径40.7㎜ 重量22.0g |
【胡散度 90%】 |
|
3月10日【胡散臭選手権】
白状するとHPの中に胡散臭いと思いながらそのまま放置掲載しているものがたくさんあります。心配性の私は、もともとは厳しい判定をしていました。銭文径を重視し、理に合わないものは切り捨てる。欲目を捨てろ・・・とよく言ったものです。しかし、どうしても説明の付かない品にぶつかり、妖しい品の買取という失敗を重ねた結果、最近はいかがわしいものにまで愛着持ち、一抹の望みを捨てられないあさましい人間になり下がりました。どうぞ笑ってやってください。
分譲して頂いた方への批判になりかねませんのであまり強いことも書けなくなりHPにも玉虫色の解説が増えていますので、皆様ご注意ください。
今日はそんな胡散臭そうなものを並べてみました。
❶は平成8年江戸コインオークションに出品された後、入札誌横浜に出品されたたもの。一品もので中郭手としましたが面を見ると細郭。穿に鋳ばりが残っているので細郭手とすべきかもしれません。側面が未仕上げのままで覆輪の超重量銭。きちんと片見切りになっているし、鋳造技術は昔のもの。銅質や出来は良いので仙人様なども問題ないと言ってくださったのですが、側面未仕上げというのがどうにも引っ掛かる。そんなこと言うと「室場(石ノ巻)なんてどうするんだ」と言われそうですけど見れば見るほど妖しいなあと未だに思っている私です。
※ちなみに室場の鋳放しも妖しく見えてしょうがないのですが、流通していた仕上銭は実に自然で、あんなごつごつした鋳放し銭が仕上げられるとごく自然な雰囲気になるんだ・・・と感心しています。
❷はかつて入札誌横浜に出て10万円以上の値が付いた品。購入者は知人のHさん。このHPによく出てくる剛腕コレクターの関東のHさんではありませんが、結構な収集家です。その方が入札誌に再放出したので私が3万円で買っちゃった。極印はクローバーのような穴ぼこだし、異様に重いし、ヤスリ目はほぼないし・・・さすがに明治大正期の後鋳品じゃないかなと思う。でもかすかな望みが捨てられない。3万円が捨てられない根性なし。とても江戸時代ものじゃなさそうだけど良く分からない。
❸は多分収集誌上で落札した1枚。真っ黒でみすぼらしいほど小さな広郭。元の持ち主は香泉師ことM師。しかも月刊天保銭53号の落札品という。極印は穴ぼこが三つ固まっているようなもの。パッとしないし変な天保銭だけど、一応自然な不知銭に見える。久留米の破損極印という線も捨てきれないけど・・・とりあえず不知広郭手かなあ。
❹は多分雑銭の会の暴々鶏師からおまけで分譲頂いたものだと思います。赤くてきれい。
背の花押を見ると久留米の背異替じゃないのと思っちゃう。たぶんそうだ。
でも極印がね~変なんです。破損極印じゃないかなあ、それでもって長頭辵は偶然の鋳だまりだよね~と、私の中では半分結論づいています。でも極印形状が違い過ぎるよなあ。と、かすかに不知銭の望みありと思ってウジウジしています。
❺は困った。銭文径が大きい。それに超重い。極印も本座とは全く違う。初めて手にしたときは書体もべたッとしていたのでこりゃ昭和の後鋳だよ、まるでグリコ天保だね・・・と思ってしまったぐらい。書体も微妙に違う。薩摩広郭の写しかもしれない。たぶんそう。穿内はべったりやすりですけど側面仕上げは好感が持てます。謎は多いけどこれはやはり江戸期の作に見えます。
❻はひと目ダメと思える品。たまご型で文字周囲がぐりぐり加刀されていて、まるで作られた砂目のようにぼっこぼこの痘痕面(あばたづら)の天保銭。
天保仙人様か暴々鶏師から分譲頂いたんじゃないかと思うんですけど・・・良く分からない。覚えてないや。暴々鶏師から類似品の細郭手を分譲頂いているのは間違いなく、それは三陸方面から良く出ると仰っておられたので、疑似三陸天保とも呼んでも良い品。ただしこいつはいかにも出来過ぎだし、極印も穴ぼこ状だし・・・。天の前足が伸びているように見えるけど、それは意識して作ったものでもないと思う。加刀だらけなんだけどどうなんだろう。意外に素直かも。妖しいけど絶対だめの決定打がない。でも妖しいです。90%だめだと思うけど・・・断定はできない。弱虫。 |
| |
| 本座広郭細縁銭 |
 |
 |
| 長径48.05㎜ 短径31.6㎜ 銭文径41.4㎜ 重量19.2g |
石持桐極印銭 正字白銅質銭
※地が滑らかで墨染めされています。銭文径も大きめ。
文字周囲の彫り込みもあります。書体は本座とほぼ同じ。
極印は玉が確認できないけど石持桐の類です。 |
 |
 |
| 長径49.05㎜ 短径32.6㎜ 銭文径41.1㎜ 重量21.4g |
石持桐極印 正字白銅質銭 不知かもしれないが・・・
※2023年4月15日制作日記に掲載。地染めあり。 |
 |
 |
| 長径48.85㎜ 短径32.75㎜ 銭文径40.6㎜ 重量22.9g |
3月5日【細縁銭・石持桐白銅銭】
電子ノギスの調子がおかしい。数字が何もしなくても動く。と、いうわけで手動計測。
見ての通り限界に近い細縁銭です。先日の大量落札品のなかにあり、不知広郭手細縁美銭とありましたが本座の範疇です。
ただ、後天的な磨輪・摩耗のない品としてはこれぐらいが限界じゃないかしら。ここまで細縁はは少ないと思うのですが、評価は3000円ぐらい?悲しいなあ。
続いての品はすごい説明が付いていました。「秋田広郭本座様 白銅地金現色ノマゝ産出 装身具ニ當用サル 鋳潰サレテ残存少シ」
秋田の阿仁鉱山ではときどき天然の白銅塊が産出したため、主に母銭に使用されていました。そのため、かつて泉界では白銅質の天保銭を片っ端から秋田鋳に所属させていた時期がありました。例えば薩摩広郭白銅、称佐渡本座写しなど。秋田本座写は本来はこのような白銅質銭を充てていたはずなのですが、いつの間にか砂磨きの粗い広郭(本座異制)が割り当てられるようになっていきました。 (2010/5/15 2019/11/24制作日記)これらの考えは現在は否定されています。(私のHPではそのままになっていると思います。ごめんなさい。) (2010/5/15 2019/11/24制作日記)これらの考えは現在は否定されています。(私のHPではそのままになっていると思います。ごめんなさい。)
現在の認識では・・・黄白色の白銅質銭は主に関西以西の鉱山で産出された銅(土呂久や長門)でつくられたものに多く見られ、それ以外では主に幕末期、鏡や仏具を鋳潰して作られたものに白銅質になるものが多いと考えられています。一般的に東北産の銅は鉛分が高く、赤味が強い傾向にありますが前述の理由で白銅銭が絶対にないわけではありません。
ではこの天保銭の素性はというと玉ははっきり見えませんが石持桐極印銭であろうことは極印形状からほぼ間違いないと思います。石持桐極印銭は本当に謎で、大量に存在すること(九州に多いと言います。)、亜鉛の含有が報告されていること、深字については稟議銭ともいわれる謎の大様銭が存在し、それには目立つ鍍銀痕跡もあり、おおよそ密鋳銭らしからぬことなどなど不思議だらけ。(夏の古銭会参照)
水戸藩説と久留米藩説があり、どちらも可能性があると思っていますが、どうなんでしょうか。なお、石持桐極印銭の白銅質銭は、もっと称揚されて地位が確立されても良い気がします。私のHPにや制作日記にも不知銭として数枚載せてしまっていると思います。
|
| |
| 長径48.68㎜ 短径32.6㎜ 銭文径41.15㎜ 重量24.7g |
 |
 |
| 長径48.18㎜ 短径32.3㎜ 銭文径40.95㎜ 重量19.2g |
 |
 |
3月4日【銅山手】
銅山手は東北では中字と呼ばれていますが、この独特の通の大きな書体・・・やっぱり銅山手ですよね。これを見る限り平通はやはり土佐に戻すべきなんじゃないかと感じてしまいます。それはさておいて・・・
銅山手は書体こそ一手ですけど、製作や銅質、大きさは実にバラバラ。右の画像の2枚、おそらく南部藩としては比較的初期に近いものだと思う。上の品は画像では褐色に見えますけど、地色はかなり赤い。クレーターのような凹穴が月面のように随所に開いています。これは鋳砂の質が悪く砂目が上手く形成されていないように感じます。側面はテーパーが強く、大きな桐極印が深く打ち込まれています。
下の銅山手は少し製作技術は上がっていますが、やはり砂目はあまり感じません。磨輪されて小さくなっていますが銭文径は大きい方です。極印は大きく深く打たれているのは上の物と同じ。
銅山手は書体は同じでも顔がみんな違う感じで、飽きません。ただ、製作が良い品はかなり少ない気がします。製作違いを集めてみると何かが見えてくるかもしれません。 |
| |
| 長径49.26㎜ 短径32.31㎜ 銭文径40.86㎜ 重量20.2g |
 |
 |
3月3日【進二天】
進二天とは良い名称だと思います。天の二引と寶足が前に進んでいるような書体で、天保通寶の文字全体が緩やかな弧を描くように配置されています。有名品なのですが美銭の入手にはなかなかてこずります。
掲示の品は進二天にしては美銭の方。側面のヤスリ目はものすごく粗い。そういえば平通に似ていますね。平通が萩藩のものであるとしたらこの類似は大きいですね。
それにしてもこの進二天、平通ほどではないものの意外に大きいですね。
進二天と縮通の違いは花押の左下、くちばしの突き出し方を観察しろ・・・とは仙人様の教え。短いのが進二天、長いのが縮通。ただし、中には例外(進二天強刔輪など)もありますのでご注意を。それだけ個体変化が多いのもこの類の特徴です。 |
| |
| 長径49.7mm 短径32.3㎜ 銭文径41.3㎜ 21.3g |
 |
 |
| 長径49.7mm 短径32.6㎜ 銭文径41.15㎜ 21.5g |
 |
 |
3月2日【平通】
入手しっぱなしで整理していなかった平通2枚です。
青寶樓師、天保仙人様とも萩藩説を支持しており、この説に異を唱えた人は穴カタ日本等で土佐藩説を表明した元方泉處の石川師ぐらいかもしれません。
かくいう私も実は平通萩藩説には未だモヤモヤがありまして・・・。
平通が萩藩とされた根拠
❶平通の鋳ざらい母銭が曳尾、進二天、方字などの鋳ざらい母銭とともに山口方面から出現している。
❷背の筆法に類似性が見られること。
❸曳尾、平通とも50mmを超える大型銭が見られること。
❹テーパーが比較的きついつくりの共通点があること。
などなのですが、❶については2品あるというものの実物の直接確認がされておらず、その他の出現した萩母銭と併せて変造の可能性が極めて高いこと。
❷については土佐通寶により強い類似性があり、根拠としては極めて弱いこと。
❸❹についても決定打に欠けること。
何より、平通については他の萩藩銭のような文字の鋳ざらい変化が皆無で、砂目、極印、銅質、製作においても必ずしも一致しないこと・・・などから萩と断定するのは無理があるんじゃないかなあと思っています。そもそも❶の根拠が崩れた段階で平通=萩藩説は撤回されても良い気がするのですが・・・これ以上泉界を混乱させてはいけないので大勢に従うことにしていますが・・・筆法は土佐通寶だよ、これ。通だけじゃ無くて寶や百も見てね。
こんなに大きくて、文字変化がない天保通寶は(関西方面では)「琉球通寶広郭」ぐらいじゃないかしら。そう考えて平通の極印を眺めていると、コンパクトにまとまっていて薩摩広郭(=琉球小字)の極印に似ているような気がしてきましたが、それは他人の空似でしょうかね。
銅質はあきらかに関西方面の色で、九州の土呂久鉱山もしくは長門鉱山の銅色です。これは異論のないところです。
なお、手替わりはほぼないと書きましたが泉譜等によると
1)広郭 広穿 大様 がある。(天保銭の鑑定と分類)・・・大同小異?
2)小様がある。(天保銭の鑑定と分類)・・・48.7㎜ぐらい。私は見たことがありません。
3)白銅銭がある。(天保銭の鑑定と分類・大橋譜)・・・私は見たことがありませんがあるみたい。
4)滑肌と粗肌がある。(新訂天保銭図譜)・・・今ひとつわかりません。上は滑らか肌なのかしら。
このうち大橋譜には「乳白色に近い」平通が(萩藩銭として)採拓されていますが、拓本なので色が分からない。小様とともに実見したいのですが、どなたか投稿していただけませんか?
|
|
| |
2月23日【長点保奇品館】
人のふんどしで相撲を取ることになりますが、雑銭掲示板に最近不思議な品物が続々と現れていまして改めて取り上げたくなりました。いずれも剛腕収集家の関東のHさん・選銭職人の四国のKさん、卓越観察眼の関西のTさんの逸品ものです。本来は命名の権利は所有者にあるのですが、一般公開掲示をするうえで名称を変えたり、仮称として表示していますがお許しください。(変更いたしますので連絡ください。)
最近、計測に自信がなくなってきました。先日の大量落札で不知広郭手とされたものをデジタルノギスで計測して見たのですが、何度測っても銭文径が41.5㎜以上に出てしまう。疑心暗鬼で画像比較すると本座と同じ。ノギスがおかしいのか私の眼がおかしいのか、測り方が悪いのかが分からない。それとも本座広郭は41.5mmなの?私は本座広郭や細郭は41.2~41.3㎜だと思い込んでいたのか?41.5mmは薩摩広郭サイズd差と思っていたんだけどなあ。たかが0.2㎜、されど0.2mm。
結局、不知広郭手はほぼ本座の異製作品ではないかということになりそうですけど、まだ銭文径の謎が分からない。卓上整理が進まない!誰か教えて! |
| |
(関東H氏蔵) |
長郭手ペン書様
画像だけだとピンとこないかもしれませんが、分厚く雄大な銭形の上に、極細の文字が極めて浅く乗っかっている異製作銭です。これは類似カタログの原品で一品ものかと思ったらヤフオクに稲陽さんがポロっと出品したから大変。でも、私は手を出せなかった。正直垢ぬけない雰囲気だったのですが、実物はまるで重厚な銅の塊そのもの。(私の印象です。)
ペン書手は安南銭では奇怪な記号のような文字の一類なのですが、この天保はボールペンで書いたような太細のない書体という意味では、本家の安南銭より的を射ているかもしれません。とにかく浅字細字厚肉大様なのです。今の古泉界で確認されているのはひょっとしたらこの2品ぐらいじゃないかしら。下段のものは火を被ったのか面側が少し乱れています。実物を触るとすぐにこの類は分かります。 |
 |
 |
類似カタログ原品
長径49.92mm 短径33.32mm 銭文径41.0mm 重量26.44g |
 |
 |
| 長径49.97mm 短径33.4mm 銭文径41.1mm 重量27.0g |
|
 |
(四国K氏蔵) |
長郭手細字長点保長貝内反足寳
細字で張点保、異足寶ながら寶貝長く変化し、俯二貝寶で寶足が短く見えます。 異足寶ながら短足寶にも見えるので内反足(O脚)寶と名付けました。側面はヤスリ目がほぼない感じで異極印。今のところ確認一品です。類品出てきませんかね。 異足寶ながら短足寶にも見えるので内反足(O脚)寶と名付けました。側面はヤスリ目がほぼない感じで異極印。今のところ確認一品です。類品出てきませんかね。
|
|
|
| 長径48.6㎜ 短径32.8㎜ 銭文径40.7㎜ 重量20.3g |
削字・滑肌側面仕上異極印銭
適切な名称がつけられない!でも製作と側面を見たら同炉にしか見えません。関西のTさんの慧眼全開の品。長点保で寶下の刔輪が特に強い品。 |
 |
下の画像だと同炉に見えなかったので記事を訂正しました。
加刀痕跡が明瞭でこうやって並べるとまったく同炉ですね。失礼しました。 |
 |
長郭手覆輪刔輪長点保延貝寳
(仮称)
足は短いものの寶貝が長く伸び俯二貝です。製作は全く異なるものの、下のアスタリスク型極印銭の長貝宏足寶と筆法はとても似ているように見えます。寶貝が伸びているので銭文径は本座と同じ。
Tさんは延展ではないかと推定されましたが寶字が明らかに長く伸びているので長貝寶とすべきなんでしょうが、差別化を図り延貝寶としてみました。延展の線は確証が取れないのですけど、延の字を残しました。銭形も縦方向に伸びていますね。本品は粗削りという言葉がぴったりな珍銭です。 |
| |
(関西T氏蔵) |
 |
 |
長径49.35mm 短径32.95mm 銭文径41.60mm 重量20.9g
長内径43.95mm 短内径27.60mm
|
| |
(関西T氏蔵) |
さあ、皆様お悩みください。上掲の天保通寶とそっくりな側面仕上げの天保通寶がこちらでございます。困ったことにこちらはいたって普通の不知銭書体。前足が突き出るような張足寶であり、覆輪刔輪銭です。
長郭手刔輪延貝寳手張足寶(仮称)
地に鋳ざらい痕跡のある覆輪刔輪銭。寶足が伸びて張足寶と宏足寶の中間のような形状。側面製作の画像を見る限りは上と同炉銭。 |
 |
 |
| 長径48.6mm 短径32.35mm 銭文径41.1mm 重量20.6g |
アスタリスク型極印銭2枚
アスタリスク(*)型としましたが、突起は5つ。これは桜、梅、桔梗など代表的な日本の花を表している可能性が高いと思われます。ただ2枚の製作の差は説明がつかないほど違う。似て非なるものなのか、試行錯誤の結果なのか・・・なんじゃこりゃの世界。 |
| |
(関西T氏蔵) |
長郭手覆輪強刔輪削字長貝宏足寶異極印(仮称)
長径の49.6mmって不知銭にしても大きな方です。天保通寶の島銭的存在で変態感満載の異書体。私に言わせればこれこそ異貝寶異當百・・・狭長貝寶で狭當百なのです。中国の集末期に作られた寶化という珍銭は別名「わらじむしの寶化」と呼ばれています。この天保銭を見るとなぜか思い出してしまったのは私だけかな?形からすると「ハサミムシの天保」と呼ぼうかしら・・・なんてね。これで異極印・・・できすぎじゃないの?でも、すごい!
|
 |
 |
| 長径49.6mm 短径33.1mm 銭文径41.2mm 重量20.7g |
 |
長郭手強覆輪異極印(仮称)
長径49.5mmの大きな不知銭。ただしこちらは立派過ぎるほどの覆輪銭です。しかも極印は見事なアスタリスク型。上のものと良く似ていますが、製作を見るとちょっと違うような気がします。
かなり薄いつくりなので延展のような、焼け伸びのような雰囲気もありますが、銭文径が大きくなっていませんのでその線の可能性はほとんどありません。このような丸っこいべたッとした覆輪銭は肥足寶の類、見た目は鋳放しの反玉寶も思い浮かびますけど違うなあ。本座銭に均等な覆輪をして鋳写しするとこんなものができるという典型かも。状態は良くないけどありそうでない品。 |
| |
(関西T氏蔵) |
 |
 |
| 長径49.5mm 短径33.35mm 銭文径40.6mm 重量18.1g |
|
| |
2月22日【卓上整理中にて徒然なるままに】
昨年からの入手品にラベルをつけないと、もう大変なことになる(なっている)状況です。一度ラベルをつけても再撮影のためにアルバムから出して行方不明になっている品多数。会津濶縁などまとまって散乱中です。私は整理する才能はあると思うのですが、片付ける才能と言いますか気力がない。「まだ、本気出してないだけ」の状況が続いています。
子供のころから落ち着きがないと言われ続けておりましたが、大人(おやじ)になってもその本質は変わりません。集中力を発揮すると徹底してやるくせに飽きっぽいところもあります。学内試験は教科書丸暗記でほぼ臨んでいましたが、連戦連勝でした・・・すごいでしょ。それが今は覚えるそばから忘れてゆくほど全くダメになってきました。
先日、Hさんから「Kさんは私の10倍は運動しているのに、腹が出ている。」と言われましたが、残念ながらその通りで痩せる才能もなくなっています。ついでに言うと水曜日にも山を歩きましたが、後から昇ってきた若い人に道を教えたら「ありがとうおじさん」と大声で言われて「ああ、俺はやっぱりおじさんなんだ」と遅ればせながら自覚した次第。もっとも海外の娘たちにとっては「おじいさん」なんですよね。
亡き妻は天然な人でものすごく地頭が良く才能があったと思います。文章を書かせれば上手だし、語学はペラペラ、絶対音感の持ち主で一度聞いた音はピアノで直ぐ再現できる人でした。音が音符で見えてくるというからすごいのですが、「自分には努力する才能がない」と言い切っていました。彼女に言わせると私は才能は大したことないけど「努力する才能はある」とのことで・・・そうなんでしょうかね。ものすごく「心配性で先回りする」ともよく言われました。今は面倒くさくなって先回りすることも忘れてます。
関西のTさんの才能は実に興味深く、一度見た古銭の特徴を画像的に記憶しているとしか思えない。感性ではなく実態として物を見ているので、ブレがないですね。雑銭掲示板の四国のKさん、とらさんとのやりとりが面白いです。でもついてゆくのが大変。みんな愛すべき才能・個性(変態)の塊集団です。
整理やりたくないなあ、面倒くさい・・・才能ないなあ、明日も山に行っちゃおう。逃避の日々です。
|
| |
2月21日【タジさんの入手品】
細郭手狭反足寳 長径48.4㎜ 短径31.7㎜ 銭文径40.8㎜
投稿記事から。細郭の寶下部分を刔輪して成型していると思います。よって覆輪はわずかにあると思うのですがそうは見えませんね。このメカニズムは 覆輪刔輪マニアック講座 をご一読ください。抜粋記事は2月13日の制作日記にもあります。
郭は切り出しが荒々しく、一方側面は砥石仕上げらしくヤスリ目がほとんど残っていません。極印は破損しているのか穴ぼこ状です。こうした側面の仕上形状は時代の降った物に多いのですが、面背の様子を見る限りきちんとした?不知銭であろうことが分かります。
命名はご本人によるもの。手を加えるとしたら”狭”の代わりに”肥”をいれて「肥反足寶」としたらどうかしら。 |
|
|
| |
2月14日【大当たり!今夜は眠れない!】
今回の落札品は九州のM師のコレクションではないかのこと。確証はありません。百田米美
| 長郭手覆輪強刔輪厚肉 |
【評価 珍】 |
 |
 |
長径が短く、短径はたっぷりある横広銭径。天上、當上、寶下ともに強い刔輪が見られます。何より重量が28gを超えるので手にした瞬間に銘品だと直感できます。メモに大橋師の所有が記載されており、調べたところ大橋譜と天保泉譜の原品でもあるようです。状態も非常によく肉厚は3㎜を超えます。これは私から見てS級の天保通寶です。
天保泉譜195
大橋譜P182-2
|
| 長径48.94mm 短径33.1㎜ 銭文径40.4㎜ 重量28.3g |
| 長郭手覆輪天上強刔輪肥足仰貝寶(肥尾天) |
【評価 少】 |
 |
 |
文字の山が丸く全体に肥字気味になっています。真鍮銭のメモが付いていましたが間違いなく未使用級の青銅銭です。宏足寶の次鋳と見て良いつくりで、以前に肥尾天としたものと同系統でもあるようです。寶足は肥足寶気味ですが・・・。肥尾天の他に寶の二引きが仰ぎ、寶底が後ろ足の前で切れています。
状態が良いので昔の鋳肌が残っていますが砂目はあまり感じません。なお、美品にまちがいないものの、画像の方がきれいに写っています。 |
| 長径48.23mm 短径32.77㎜ 銭文径40.1㎜ 重量18.8g |
| 長郭手強覆輪刔輪鋭楕円形 |
【評価 少】 |
 |
 |
ヤフオクの画像で妙に細長く見えた品ですけど、届いてみたらやっぱり変な形だった。立派な覆輪銭なのですけど、普通はここまでの覆輪ならもっと短径が全体に広がって、いわゆる横広銭形になるはずなのです。しかし、計測値的にはわずかな差なので、この縦長の形状に強い違和感を感じるのは私だけなのかもしれません。名称は前所有者が鋭楕円形と名付けたものをそのまま頂戴しました。 |
| 長径49.31mm 短径32.4㎜ 銭文径41.1㎜ 重量20.4g |
| 謎品 本座長郭白銅銭 |
【評価 謎】 |
 |
 |
初めて見た瞬間、不知長郭手の白銅だと小躍りしました。しかし、撮影すると変な色。計測値は本座を示しています。うーん、着色かもしれない。こんな古いコレクションにもあるのか・・・仙人様に聞いてみよう。
※これはこれで良いとのお話でした。ただし、引き続き検討が必要だと思います。 |
| 長径49.10mm 短径32.3㎜ 銭文径41.6㎜ 重量21.7g |
| 薩摩広郭白銅質 |
【評価 5】 |
 |
 |
薩摩広郭白銅銭というようにラベリングされていました。見た目は白銀色ながら撮影すると黄色くなるのはこの類に良くあること。つまりこれが真の地金の色で白くなるのは乱反射の要素が入るから。もちろんもっと白いものもあるし、着色もある。これは真面目な白銅質銭だということです。上には上があるけどそこそこ価値はあります。 |
| 長径49.0mm 短径32.5㎜ 銭文径41.45㎜ 重量21.9g |
| 薩摩広郭白銅質 |
【評価 5】 |
 |
 |
こちらは純白と書かれてました。確かに白っぽいし、見た目は白銀色に見えますが地色は黄色っぽいのでこれが正しい色なのかもしれません。 |
| 長径49.0mm 短径32.6㎜ 銭文径41.4㎜ 重量25.4g |
| 細郭手刔輪陰起文 |
【評価 2】 |
 |
 |
良くあるタイプの細郭手。本来は覆輪刔輪銭なのですが、覆輪らしさはほとんどありません。刔輪も寶下にらしき痕跡がある程度です。 |
| 長径48.2mm 短径32.15㎜ 銭文径41.6㎜ 重量18.5g |
| 細郭手張足寶 |
【評価 1】 |
 |
 |
言わずと知れた不知細郭手の中の再有名品。これぞ張足寶という寶足形状で書体的には一手です。本品は残念ながら変色していますが、本来は本座以上に製作が良いものが多く見られます。
張足寶は「はりあしほう」と発音し、長足寶「ちょうそくほう」とは区別されます。寶足が弓張状に力強く長いもの。新規銭文の母銭によるもので、あまりの製作の良さから雄藩の作ではないかとも言われています。 |
| 長径48.8mm 短径32.0㎜ 銭文径41.6㎜ 重量20.4g |
| 長郭手當上刔輪反玉寶 |
【評価 1】 |
 |
 |
1回写しの不知銭で。本座に酷似しています。前所有のラベルには反玉寶美制銭と記されていました。たしかに反玉寶ですけど石ノ巻銭とは製作が異なります。これがもし石ノ巻銭だったら今回の収支は大黒字でしたが残念。 |
| 長径48.5mm 短径32.2㎜ 銭文径41.2㎜ 重量19.5g |
|
八厘会出席者
日馬 目黒 岡田 小川 遠藤 中嶋 奥富 山田 浜本 安達 増沢 中村 林 吉田 下藤 武藤 |
| |
2月13日【覆輪銭形の秘密】
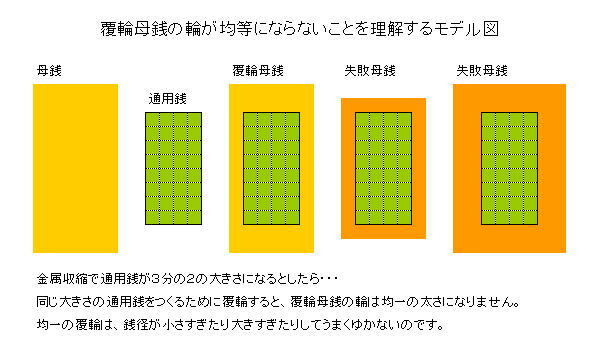 収集初心の方は覆輪、刔輪と言っても良く分からないかもしれませんので、ここでおさらい。 収集初心の方は覆輪、刔輪と言っても良く分からないかもしれませんので、ここでおさらい。
天保銭を鋳写すと、一回り小さくなります。1月28日の制作日記の鐚永楽を見ればわかりますが、鋳写しを繰り返すとおもちゃのように小さくなる。秋田小様は2~3回写しがメインなのですけど、通常の天保銭より長径が2㎜以上小さくなります。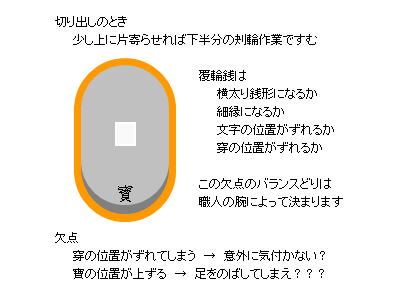
密鋳天保銭は幕府に見つからずに流通させることが一番の使命です。そのためには撰銭されて受け取り拒否されないことが大切。したがって本座なみに大きく重いことがある意味重要なんです。ところが鋳写すとどうしても小さくなる。鋳造の条件にもよりますが本座銭を鋳写すと長径で0.6~0.7㎜程度は鋳縮みします。天保通寶も多くは挿しの状態で流通しています。挿しに入ると大きさの違いは非常に目立ちます。その差を補うために覆輪をしたのだと考えられます。
しかし、天保通寶は円形ではありません。縦長です。鋳造時の収縮は縦方向の方が(距離的に長いため)大きいので、覆輪幅を縦横均 等にするなら、鋳写されたものはずんぐりむっくりの横広銭形になる。これは物体はより安定した形状に近づこうとする自然の摂理です。 等にするなら、鋳写されたものはずんぐりむっくりの横広銭形になる。これは物体はより安定した形状に近づこうとする自然の摂理です。
このずんぐりむっくり銭形化を避けるために、母銭そのものを縦方向に引き伸ばそうとすれば、当然ながら輪の幅が上下に広く、左右に狭くと、いびつになります。たかだか0.6~0.7㎜の違いと思うでしょうが、人間は輪の不均衡の太細に関しては敏感に見抜きます。そこで登場したのが刔輪技法・・・と、いうのが私の仮説。詳しくは覆輪刔輪マニアック講座をご一読ください。
分かりやすい事例として、仙台長足寶をお考え下さい。この天保銭こそ覆輪によるずんぐりむっくり銭形を修正しようとした涙ぐましい逸品・・・芸術品なのです。この天保銭は天上と寶下の輪の太さを修正するため、上下の輪を激しく刔輪しています。その結果、元の銭形(スタイル)を維持し+輪幅を一定に保ちながら覆輪する(銭形と大きさを復元する)ことに成功しています。(砂目と言いい銭座職人の美意識の高さを感じませんか?)穿の位置はほぼ中央。不自然さを隠すため寶足は長く、天上は天の第一画横引きを太くすることでごまかしています。昔は文盲率が高かったので、文字の変形は実はさほど重要ではなく、銭形の維持を優先的に図る・・・すごい職人の技なのです。ついでに言うと広郭になっているのも嵌郭だと私は考えています。ただし、上下の輪を刔輪加工するのは効率が悪い。片側を加工すれば工程は楽になるし、見た目もそれほど変わらない。
この仮説に至ったのは、覆輪刔輪の不知天保通寶の穿が中心点より上に位置するものが意外に多いと気づいたことにはじまります。右の長反足寶の画像をご覧ください。天上の刔輪はほとんどなく、寶下のみ強烈に刔輪されています。その結果、穿の中心が1mm近く上方にずれています。穿を偏らせることで刔輪するのは寶下だけで済みます。つまり天上側の刔輪工程を省いたんですね。不知天保通寶の刔輪は圧倒的に寶下が多い。穿の偏りは案外気が付かないものなのです。
※覆輪は金属の薄い板を銭の周囲に巻くのではなく、銭を分厚い金属の板に嵌め込んだ後に切り出すのが一般的。仮説として和紙を銭の周囲に巻くというものも泉界にあります。手法としては私はあると思います。なお、覆輪のみの加工はあり得ますが、刔輪と覆輪は必ずセットで行われるのが通常です。
※天保通寶を収集するなら仙台長足寶は必須の品。なぜこんな加工をしたのか考える良きサンプルです。仙台長足寶に手が届かない方は水戸接郭を入手してください。古の金属加工技術が良く分かります。
|
|
| |
| ❶細郭手張足寶(斜穿) |
 |
 |
| ❷長郭手覆輪強刔輪肥尾天(天上刔輪) |
 |
 |
| ❸細郭手覆輪刔輪削字 |
 |
 |
| ❹長郭手強覆輪 |
 |
 |
| ❺長郭手覆輪刔輪(當上刔輪) |
 |
 |
| ❻長郭手覆輪強刔輪大頭通張足寶 |
 |
 |
| ❼長郭手削字反玉寶 |
 |
 |
2月12日【不知銭がいっぱい】
収集品らしきヤフオクのロットに皆さんくぎ付けだったと思います。かなり熱心なコレクターの放出品でしたね。張点保嵌郭はどなたが落としたのかしら。私はてっきりHさんが落したと思ってましたのでウォッチリストにも入れそこなってました。
まだ落札品が届いていませんが画像を編集して楽しんでいます。
❶細郭手張足寶
細郭手不知銭の必携品。状態は普通だけど拓本墨でずいぶん汚れちゃってます。この類は黄色い美銭が多いのでちょっと残念ですね。持ち主が入手を喜んで拓本を採りまくったんじゃないかな。
❷長郭手覆輪強刔輪(天上刔輪肥尾天)
ものすごく幅広銭形に見えるけど、後でがっかりしないように魚眼レンズ効果だと自分に言い聞かせてます。
覆輪刔輪銭で天上、當上の刔輪が強い不知銭。寶下刔輪は寶足が伸びるから一般的に人気があるけれどその逆は地味。でも、圧倒的に存在数は少ないのです。宏足寶としても良い雰囲気もありますがいまいちかな。この天保銭は私が肥尾天としているものと同じ系統かもしれません。
❸細郭手覆輪刔輪削字
よくある連玉尓の類かなあとも思うのですが、覆輪刔輪がしっかりあり、文字も削字で陰起文気味。変形しています。この雰囲気の細郭手は変形極印が打たれたものが多いので落札品の到着が楽しみです。
❹長郭手強覆輪
こいつはヤフオクの画像も大きかったのでものすごく目立っていました。集合写真では妙に縦長に見えましたが、多分画像マジックでしょう。そう自分に言い聞かせながらも踊らされていたと思います。画像通りだとしたら、輪の太細もあってものすごく楽しい不知銭です。そうあって欲しいなあ。
❺長郭手覆輪刔輪(當上刔輪)
皆さんならB級不知銭とするのかなあ。當上の輪がはっきり刔輪されています。それ以外は文字変化もあまりなく平凡ですね。寶尓の第一画が削られて寶冠から離れています。寶足もちょっぴり長い。B級じゃちょっと可哀そうなんだけど・・・B級かなあ。
❻長郭手覆輪強刔輪大頭通張足寶
これまたずんぐりむっくりの銭形で天上當上の刔輪がとても強い。しかも寶足も長いのでこの通りの見た目ならA級以上は間違いない品。古い朱書きは「長郭手 フクリン ケツリン」だと思います。
❼長郭手削字反玉寶
真っ黒。でも、よく見たら反玉寶でしたけど、背上部の刔輪が見られず石巻ではないと思いますけど実物見ないと何とも言えない気がしてきた。それならB級じゃなんですけどねー。
山歩きをしようと早朝に家を出たのですが、連日の寝不足がたたり眠たいのなんの。就寝2時、起床5時ですから・・・登山口までたどり着きましたがふらふらしていて、そのまま登ったら倒れると思い勇気ある?撤退。途中のサービスエリアで30分ほど居眠りしてたらサイドブレーキ引いてなくて車が少し動いていた。あぶねー。
山歩きやめて正解です。
先週、誰もいない鋸山の裏側を一人で歩いていたら職場のペアが颯爽と走り寄ってきた。(2分前立ち小便してた、あぶねー。)夫婦でトレイルランをやってた。旦那がトレイルランやってたのは知っていたけど奥さんまでとは恐れ入りました。あんな足場の悪い道を1.5時間で駆けるだと・・・信じられない。私は3時間半はかかります。
その話を昨日職場でしたら女子職員が地場のマラソン大会に2年連続参加していることを自慢してきた。(挑発?)その職員は5年前は腰痛で苦しんでいたんだけど、一念発起して運動をはじめてダイエット。ものすごく痩せて(多分15㎏は痩せている)きれいになった。悔しいから俺だって◯◯㌔ぐらい毎週歩いているんだぞと言ったら鼻で笑われた。勝てない自慢話で対抗してしまった自分が情けない。いつか痩せて驚かせてやる。でも、私の「いつか」はいつ来るんだろう。古銭じゃ痩せないな。
|
|
| |
| |
| 広郭手異制無極印(側面斜めヤスリ) |
 |
 |
長径48.35㎜ 短径31.35㎜
銭文径40.7㎜ 重量22.5g |
 |
| 長郭手鋳写し浅字 |
 |
 |
長径48.95㎜ 短径32.3㎜
銭文径41.2㎜ 重量20.4g |
| 長郭手覆輪強刔輪 |
 |
 |
長径48.6㎜ 短径33.0㎜
銭文径40.25㎜ 重量25.5g |
| 萩藩銭 曳尾拡穿(面細郭) |
 |
 |
長径49.15㎜ 短径32.15㎜
銭文径41.4㎜ 重量20.7g |
| 鐚永楽斜穿小様(木楽?) |
 |
 |
| 22.98×22.83㎜ |
|
1月28日【何とも言えない品】
ネットで購入した不知広郭手です。色調整をやりすぎて真鍮銭みたいになってますが本来はほぼ本座の色です。ただ、無極印なんですね。こうしたものはたいていダメとすべきなんですけど側面の仕上げは斜めやすりながらヤスリ目はいたってまともな手仕上げ。鋳肌に違和感が残るものの近代作とは言い切れません。背側の研ぎが強い一方で、面側の文字や郭の表面が泡立つ感じ。郭の表面がひび割れているし、重量もほんの少し重いけど、普通の広郭の一度写しとしか言いようがない品です。
2枚目は鋳写しの長郭手。寶足がほんの少し長いだけで計測してかろうじて写しだと判断できますが本座の変色だと言われてもおかしくないほど特徴がない・・・というか状態が悪い。こんなもの集めちゃいけませんぜ・・・旦那。極印も本座っぽくないけど断定材料にはならない。もう、こんなものばかり買って・・・反省してください。はい。
3枚目、長径は寸詰まりで横幅のある覆輪で刔輪がかなり強く天・當が隔輪し寶足も長い。地に砂目をあまり感じさせない雰囲気から覆輪強刔輪宏足寶背上辺削郭としたものに良く似ています。重量は25.5gもあり、肉厚感、重量感もある。背の上部には錯笵痕跡もあるし、拓本墨で汚れているからさぞかし銘品だと思うでしょ。確かに銘品ですよ・・・状態さえよければね。
実はこの品は強い磨きのある品です。私のスキャナー、どうもピントが甘いので気に入らなかったんですが、この磨きの入った品に対してはテカリを抑えて未使用のような肌を再現してくれる。画像マジック爆裂です。これでヤフオク出したら5万は軽く超える美人になりましたが、詐欺師の汚名がついちゃうかも。出したらクレーム必死の品。土台は珍品なんですけど・・・実にもったいない。
この余りの画像変貌に私自身が驚いていますが・・・スキャナーを良いものに変えたい。育てれば銘品かなあ。
次は曳尾。私が生まれて初めてリサイクルショップで見つけた品。古銭店を含み曳尾を拾ったのは初めてです。たまたま自転車のパンク修理に立ち寄ったら菓子箱の中にざらっとあった雑銭に混じっていました。800円なり。こいつはご機嫌です。曳尾は面が広郭の物が多いのですけど、こいつは極端に面側が細郭になっています。そのため穿内の傾斜がきつくなってます。これはこれで面白い。広穿の背まで細郭の曳尾があったらもっと面白いんですけどね。
おまけは八厘会の盆廻しでMさんから購入した鐚の小さな永楽。永楽は収集対象じゃないけど可愛すぎてつい買っちゃいました。私、病気ですかね?・・・そうですか。
|
| |
 1月25日【餅鉄:八厘会にて】 1月25日【餅鉄:八厘会にて】
八厘会に参加しました。親父様のこともあり、前日に準備できず早朝に画像編集してギリギリ参加とあわただしい。
会場に到着すると、本日の展示「自慢の品」は古銭以外だった・・・がーん。 でもせっかく作ったので資料展示。古銭以外だと土器の破片とか鉄腕アトムの弁当箱ぐらいしかない。欅看板数枚と日本刀(登録済み)が一振りあるけど重いし物騒なので持っていけないですね。親父所蔵の絵が何枚かあるけど、僕の物じゃない。貧乏徳利がひとつあったかな。じい様の胸像が二つあるんですけど・・・誰もいらないよね。さて、オープニング談議で「最強の漢字」というお題がありました。私は「妻」だと思ったのですが、この字を書いて「そしじ」と読むそうです。霊的PWに満ちている文字で、枕の下に敷けば安眠をもたらし、痛いところに貼れば和らいだり、植物の下に置けば良く育ったり・・・信じるか信じないかはあなた次第。 でもせっかく作ったので資料展示。古銭以外だと土器の破片とか鉄腕アトムの弁当箱ぐらいしかない。欅看板数枚と日本刀(登録済み)が一振りあるけど重いし物騒なので持っていけないですね。親父所蔵の絵が何枚かあるけど、僕の物じゃない。貧乏徳利がひとつあったかな。じい様の胸像が二つあるんですけど・・・誰もいらないよね。さて、オープニング談議で「最強の漢字」というお題がありました。私は「妻」だと思ったのですが、この字を書いて「そしじ」と読むそうです。霊的PWに満ちている文字で、枕の下に敷けば安眠をもたらし、痛いところに貼れば和らいだり、植物の下に置けば良く育ったり・・・信じるか信じないかはあなた次第。
楽笑会の骨董品オークションで東北のEさんから「餅鉄:べいてつ」なるものを購入。餅鉄は釜石の語源になった鉄鉱石(磁鉄鉱)で、釜石の甲子川産が有名なんだそうですけど、これは八戸産(新井田川?産)らしい。そのほか拡大鏡も買ってしまった。まあ、お遊びです。(遠藤)
O氏の象牙細工の印籠やキセルは見事、O氏の水石コレクションは奇麗に画像整理されていてこれまたすごい。石は好きだなあ。(岡田・小川)
仙人の銭談は平尾麗悳荘こと平尾賛平のお話。三上香哉が平尾の元に走った真相・・・三上は武士の家柄だったんだ・・・と、詳しくは書けないので、例会にご参加ください。展示解説では薩摩小字の黄銅、長郭手嵌郭、広穿大字、中郭手小点尓、広郭手原母銭の「五大奉行」展示。広郭手原母銭はたしか画像持っていたはずですが、方泉處11号掲載原品とは気が付きませんでした。中郭手小点尓は仙人自慢の逸品で現存4品程度。Hさんもお持ちですね・・・そういえばヤフオクの美品の草点保・・・Hさんが落されたそうでお見せいただきましたが美しい。長郭手嵌郭も複数お持ちで・・・かないません。さらに秋田の村上師の旧蔵品の改造母銭類を拝見。この類の真贋は全く分からないのですが、とても美しく見えたのでいいんじゃないかな。ここら辺は感性ですね。しかしHさんはすごいです。
会場でMさんに声をかけられました。なんでも秋田小様の49mmある大様と厚肉、2mm以下の極薄肉をコレクションされているそうで、45mmクラスの小様がそろえばコンプリートだとか。え、私の小様が欲しいんですか?(目黒)
45mmクラスの小様は私の他、鉄人と私が分譲したNさんがお持ちだと思いますけど・・・どなたかMさんに分譲してくださらないかなあ。私、おねだり攻撃に弱いので・・・。(西尾)
盆廻しでは鐚永楽と接郭の大きな奴、赤い広郭を入手。鐚永楽は各抜けでかわいかったので買い。接郭は見た目が大きかったので買い。好きですね。49.55㎜、39.2㎜ありました。赤い広郭は痩通寶で極印が穴ぼこ状に見えるので買いましたが、計測上は本座の変色かなあ。微妙。
なお、関東のAさんに折二様などの寛永銭類をお見せしましたがお褒め頂きました。ありがたいことです。盛り上げるため今度、盆廻しに天保銭でも少し出そうかなあ。なかなか思い切れないけど・・・。
※大事なお知らせ
八厘会の2月例会は会場の都合で2月15日(土)12:30になります。
|
| |
1月19日【幻の寛永通寶】
関東のAさんから連絡が入りました。昨日の古寛永、直径は25.65㎜だそうで、しかも白銅母・・・母の母かもということ。元方泉處の石川氏にきいたところもしかすると一品ものかも・・・ですって。
(画像は加工していますが縮尺が狂ってますのであしからず。。)
明暦駿河銭の多く(称鳥越銭は雑銭)扱いされていますがこんな品が潜んでいるんですね。南さん、探してみてください。真の濶縁は少ないですよ。
それと、今月号の駿河に噂の背盛無背が出るらしい。なんというタイミング・・・出来過ぎじゃないか・・・と思いながらも好奇心がとまらない。
1.南部泉志(第一輯)、2.北海道と東北の貨幣、3.穴銭入門の古拓、4.穴カタ、5.新寛永通寶拓影集にも拓を確認。他にも出てきそうです。銅質製作色々あるのかもしれませんがみんな大きい。Kさんの選りだした1枚は穿内仕上げが雑で赤い銅質でもないのですけど、むしろ見た感じに違和感はないですね。大化けしそうです。黄金の一発でました?
|
| |
湧泉堂(関東A)氏
古寛永明暦駿河銭(称:鳥越銭)
|
東北S氏
密鋳文政正字写 削字 |
1月18日【年賀状ギャラリー】
湧泉堂(関東A)氏
古寛永明暦駿河銭(称:鳥越銭)
生拓本ですけど25mmを超える外径。高濶縁の母銭なんでしょうが、もしかして彫母なんてことありますか?サイズや由来などお教えください。
東北S氏
密鋳文政正字写 削字
表面のぶつぶつまで写された密鋳銭。これは貴重ですね。昨年の6月28日の制作日記記事をご覧ください。密鋳銭愛が過ぎるとこんな醜い銭でも愛おしく、恋しくなります。アバタもえくぼ。恋は盲目・・・いえ、ただの病気です。
|
 |
 |
 |
金幣塔氏
仙台広郭母銭
仙台広郭はただでさえ希少な品なのですが、その系譜正しき母銭なので全く非のうちどころない銘品です。
背の花押の嘴先端から伸びる加刀痕が背輪の内側にわずかに小瑕をつけているのも伝承通り。この特徴大濶縁にもあるんですよね。
こんな品、普通は画像でも一生拝めないです。ありがたや~。
|
 |
鳳凰山氏
ペルー8レアル銀貨MR刻印
(モザンビーク)
外国コインにはときおりこういった刻印が残るものがあります。両替商刻印だ・・・傷物だと思うと大魚を逃します。メキシコ8レアルに打たれた改三分定印銀は有名ですけど安政六年に函館奉行所が洋銀に漢数字を打刻したものはあまり知られていません。こういったものはそのエピソードを知っているかいないかが大きい。鳳凰山氏の博学ぶりは私の知ったかぶりのはるか上を行きます。当然この銀貨のことは初めて知りました。ゼネラルコレクターですねー。 |
ネット収集画像(参考比較)
中正永楽 鼎足寶 |
四国O氏
改造鐚 中正永楽刔輪
24.75㎜ 2.4g |
 |
 |
 |
中正永楽はひと目美しいです。参考画像として左の画像をとっておいたぐらい私も魅入られています。鼎足寶って分類正式なんですか?
ほれぼれするとはこれらの銭のことで、わび寂び枯れ・・・う~ん、それを超えて魅力的。洗練されて気品があるんですよね。美しい。
永楽は収集対象にはしていないのですけど、これには食指が動いちゃう。でもない袖は振れないから理性を強くして耐える。でも、これって母銭じゃないのかなあ。誰か教えて。 |
|
| |
1月15日【長反足寶】
オークションワールドのHPを見ていたら、何となく記憶のある品の画像がありました。「天保通寳 不知長郭手.覆輪強刔輪.長反足宝.(不知天保通寳分類譜原品)」とあります。打ち瑕の位置が同じなんですね。
兄弟銭かな~と思いまじまじと見つめてしまいました。いや、打ち瑕が兄弟なんて事は断じてないですよね。落札価格が24万3100円・・・う~ん、オークションワールドに参加したことなんかないし、私の長反足寶はそんなに高いお金は払ってない。落札日が2007年12月となっている。あれ、古いやと思ったらオークションがオークションネットとなっています。そこで改めて記憶を紐解くと、この画像の品は2007年12月にたしかHさんが落として、その後に重品になったからHさんが売却して・・・それを私がオークションで落としたとHさん自らが語っていたと思います。私が落としたのは2009年6月で、価格は19万円とあります。謎が解けてちょっとほっとしました。
HPの不具合の方はかなり解明。スマホのGoogleアプリの問題か、私のHPのGoogleのサイトマップ登録の問題らしい。Google Chromにブラウザを切り替えたらあっさり改善しましたが、皆様はどうでしょうか? |
| |
| 不知長郭手覆輪強刔輪跛寶(寄郭) |
 |
 |
| 長径49.4㎜ 短径33.1㎜ 銭文径41.0㎜ |
1月11日【タジさんから】
タジさんから名称に迷っているとのことで画像が送られてきました。痺れましたね・・・名品館に掲載している離足寶に似ているとのことですが、似ているのは銭形でしょうけどこっちの方が断然すごい。私の離足寶は大したことがないのですが、こちらは刔輪が強烈で背が細縁になっています。寶前足は鋳走りで接していて後足が離輪しているので離足寶とは名付けられないので跛寶としましたが、寄郭と称しても良いほど強烈な刔輪。銭文径の縮小は1回写しなのにこんなに銭形が変形している覆輪刔輪銭なんて・・・絶句。赤黄色の色調もかわいいです。 |
| |
1月6日【駻字:かんじ】
昭和泉譜にあったのは「旱字」ではなく「駻字」でしかも水戸遒勁につけられた名前でした。つまり、昨日書いたことは大間違い。うろ覚えでした。あ~はずかしい。
ちなみに「駻」は「旱」と同じく「かん」と読んで暴れ馬のことだそうです。「旱」はひでり・・・とも読みます。今は「干ばつ」と書くのが普通ですが、かつては「旱魃」と書いたようです。「魃」の文字は訓読みでは「ひでり」もしくは「ひでりがみ」。中国神話に出てくる旱魃の神(妖怪?)「ひでり」だそうで・・・。昔の人はよく漢字や故事を知っていますね。「尨」(むくいぬ・ぼう)→「尨字」なんて読めません。
昭和泉譜の頃の天保銭の分類はまだ手探り状態で、分類の方向性が定まらずに迷走している時代。
下記に例をあげます。
仿鋳とされているものが多数ありますが、名づけ方が極めて不安定なので省きました。(本座以外の全部が仿鋳と考えて良いかも。)また、見ての通り、藩名(地名)が冠されているものは少なく、しかもかなりいい加減です。この当時、今でいう薩摩広郭は秋田鋳とされていたのですが、理由は秋田天保に天然の白銅を使った母銭が見つかって、それがきっかけで白銅銭のある天保銭はこぞって秋田に移されていた時期なのです。薩摩のガマ口天保まで秋田に移籍されたようなのですが、さすがに阿仁の名前はつけられていません。阿仁は赤土を意味する語で、秋田鋳天保には白銅系の「秋田」と赤銅質の「秋田 阿仁」の2つができたみたいですけど・・・変です。
| 現在分類名 |
昭和泉譜 |
|
現在分類名 |
昭和泉譜 |
| 会津短貝寶 |
小郭 |
|
会津長貝寶 |
小頭甬 |
| 水戸大字 |
奔字 |
|
水戸深字 |
秋田額輪細字 |
| 水戸揚足寶 |
濶縁小字 |
|
水戸遒勁 |
駻字 |
| 水戸短足寶 |
福岡天保 |
|
水戸濶字退寶 |
別炉斜天 |
| 水戸接郭強刔輪 |
広郭手再刔輪 |
|
福岡離郭 |
小郭降通 |
| 薩摩広郭 |
秋田阿仁美制 |
|
薩摩横長郭 |
秋田広穿 |
| 萩方字 |
薄天保 |
|
萩平通 |
別炉仰天 |
| 萩曳尾 |
佐渡天保 |
|
萩縮通仰天 |
小頭通仰寶 |
1/5からの大腸検査に備えて食事制限中。毎日、素麺もしくは卵かけご飯。腸内をきれいに。
1/7 朝昼おかゆ・・・夕はコーンスープのみ。痩せそう。
1/8 下剤2リットル・・・死ぬ。
※起床5時前の生活が定着。就寝(居眠り)が早くなってます。5:30には親父様の朝ごはん。眠い。
|
| |
1月4日【蛇年】
古銭の関係でヘビはこの蛇の目と永楽の蛇尾永、あとは浄法寺天保の通称:蛇口ぐらいしか思いつきません。寛永通寶をさかんに収集していた頃、この蛇の目はあこがれの的でした。蛇の目が蛇の目傘だということは分かっていましたが、本物の蛇の目傘に触れたことは1~2度しかなく、いえ、むしろある方がすごいかもしれませんね。私は旅先の旅館で貸して頂いた記憶がかすかにあり
ます。もし、蛇の名をつけるとしたらこの天保通寶でしょうか。異貝寶異當百の名称で知られている奇品で、私は延尾通と勝手に名付けておりますが蛇尾通も候補でした。ただ蛇尾(だび)は竜頭蛇尾に通じ、勢いがなくなるイメージにとられかねないし、荼毘(だび:火葬)を思い起こすのが難点ですね。ならば竜尾通?気負い過ぎかな。
とはいえまるで日照り(旱:ひでり)にあった骸骨みたいな書体・・・そういえば昭和泉譜あたりで方字を旱字(かんじ)と称していたような気が。旱は日照りを意味する字ですからこれこそ旱字なんでしょうけど。とにかく、この天保は名前が決まらない。奇書蛇尾通窄貝寶・・・今年はこれ? |
| |
1月3日【祝HP復旧】
正月早々お騒がせをしました。それにしても原因が全く分からなかったので一時期はどうなるかと思いました。はじめ更新が不能になったので転送設定の不具合化と思ったのですが、まさかのサーバー料金未納・・・自動更新になっているから大丈夫かと思っていました。
もとさんから水戸短足寶の外径内径に縮小はないかとのことですが・・・雑銭掲示板の10/15の記事に掲載しています。
| 計測値 |
長径 |
短径 |
銭文径 |
重量 |
| 比較用の短足寶の計測値 |
49.50㎜ |
33.10㎜ |
40.55㎜ |
20.7g |
| 水戸短足寶写の計測値 |
48.25㎜ |
32.10㎜ |
39.65㎜ |
21.5g |
この品は天保通寶と類似貨幣カタログでは(村)の印が確認できますので秋田の村上師の蔵品であったようです。銅色は東北特有の鉛分の多そうな赤色で小ぶりなのに重い。極印ははっきり確認できません。
以下の泉譜で掲載が確認できます。
當百銭カタログ No.378(奇書体)
不知天保通寶分類譜 下巻P209(奇書)
天保通寶研究分類譜 第5巻No.1614
天保通寶と類似貨幣カタログ No.156
一生懸命更新しようと頑張りましたが、昨年は介護疲れもあり息切れでした。机の上が全く整理できていません。94歳の親父様・・・驚異の身体能力はありますが、行動制御不能。記憶機能、時間割がぶっ飛んでますので24時間行動に排泄機能の故障がきつい。正月の食べ過ぎで下痢ピー状態で嗚呼・・・。とがめちゃいけないんですけど・・・お願いだからやめて~と心で叫んで追いかけてます。本人曰く、俺はボケてないから多分100歳まで頑張れる・・・いけると思います。
|
| |
|
|
|





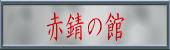










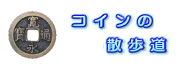






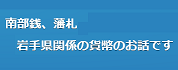













 外径25.6㎜
外径25.6㎜









































 松前通◯・・・最後の一文字が長らく判読できなかったのですが、用の草書体のようです。「松前通用」・・・よくできた空想貨幣でしょう。
松前通◯・・・最後の一文字が長らく判読できなかったのですが、用の草書体のようです。「松前通用」・・・よくできた空想貨幣でしょう。















 冷えたばかりの溶岩の肌みたい。未使用で摩耗のない仙台銭はこういう肌なのかもしれません。大様は面左側に雲状の鋳だまりがあるのですが、これにはありませんが、大ぶりです。なお、この品は寶前足先端に陰起と鋳だまりがあり、短く見えますが長足寶です。
冷えたばかりの溶岩の肌みたい。未使用で摩耗のない仙台銭はこういう肌なのかもしれません。大様は面左側に雲状の鋳だまりがあるのですが、これにはありませんが、大ぶりです。なお、この品は寶前足先端に陰起と鋳だまりがあり、短く見えますが長足寶です。























































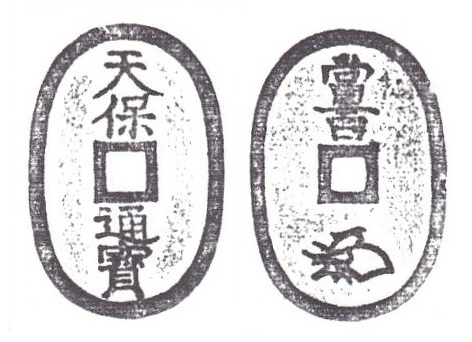








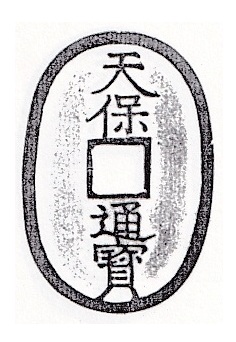
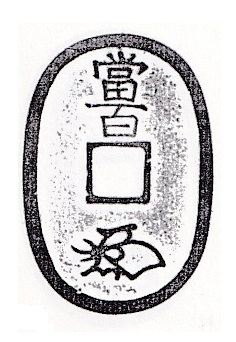





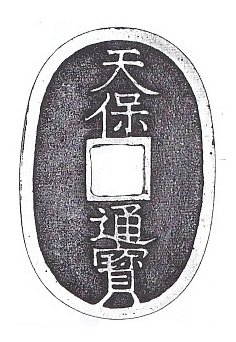
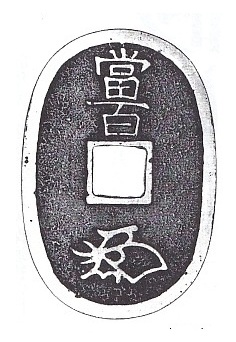






















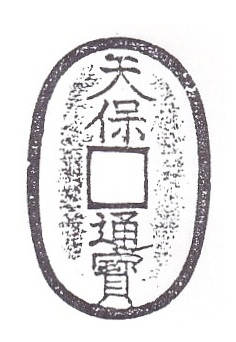















































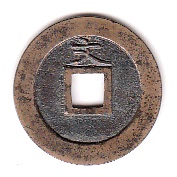





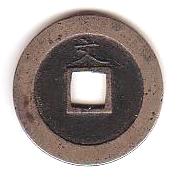


 5月4日【銀座は錫母の技術を知っていた!】
5月4日【銀座は錫母の技術を知っていた!】 一応水戸藩銭としていますが背異反足寶は間違いなく石持桐極印の系統だと思われます。それは極印の形状(右)を見れば合点がいきます。右の極印は❶の極印。頭が大きくて石持の玉が見えてきそうじゃないですか?すべての背異反足寶がこうだとは言えませんが、これは大きな証拠になります。
一応水戸藩銭としていますが背異反足寶は間違いなく石持桐極印の系統だと思われます。それは極印の形状(右)を見れば合点がいきます。右の極印は❶の極印。頭が大きくて石持の玉が見えてきそうじゃないですか?すべての背異反足寶がこうだとは言えませんが、これは大きな証拠になります。




























 旧家の屋根裏から見つかったようなすすけた風貌ながら、未使用肌の天保銭で地肌にはぼこぼこに小穴が開いています。ただし、手が切れるような切り立つ感じでありません。赤い色合いのせいか鋳ざらいの痕跡はあまり目立たなく、さらに寶前足が陰起し先端部の輪に鋳だまりがあり、後足も離輪して寶両足ともあまり長く見えないのです。本当に長足寶?と言われそう。
旧家の屋根裏から見つかったようなすすけた風貌ながら、未使用肌の天保銭で地肌にはぼこぼこに小穴が開いています。ただし、手が切れるような切り立つ感じでありません。赤い色合いのせいか鋳ざらいの痕跡はあまり目立たなく、さらに寶前足が陰起し先端部の輪に鋳だまりがあり、後足も離輪して寶両足ともあまり長く見えないのです。本当に長足寶?と言われそう。













 触れた感じはまるで紙やすりみたい。この手は恩賜手というのかも。極印は小さく深く打たれています。秋田本座写しは現在は否定されていますが、面倒なのでHPにはまだ残しています。計測したら思った以上に大きくて重かった。本座異制にはいろいろ混じっていると思う。
触れた感じはまるで紙やすりみたい。この手は恩賜手というのかも。極印は小さく深く打たれています。秋田本座写しは現在は否定されていますが、面倒なのでHPにはまだ残しています。計測したら思った以上に大きくて重かった。本座異制にはいろいろ混じっていると思う。










 左は合成画像。内径は少し小さいが銭文径は大きい。寶冠と寶貝上辺、保と天の第2画の位置はそろっているけど銭文径は大きい。これは天上、寶貝が伸びている。内径の差は書体の差なので、これは長径の上下で叩かれているのは間違いない。そう考えて上部を見ると天上が盛り上がり歪んでいる上、強い砂磨きが入っています。側面のやすりは東北独特のものではないし。
左は合成画像。内径は少し小さいが銭文径は大きい。寶冠と寶貝上辺、保と天の第2画の位置はそろっているけど銭文径は大きい。これは天上、寶貝が伸びている。内径の差は書体の差なので、これは長径の上下で叩かれているのは間違いない。そう考えて上部を見ると天上が盛り上がり歪んでいる上、強い砂磨きが入っています。側面のやすりは東北独特のものではないし。

 母銭の落下痕跡
母銭の落下痕跡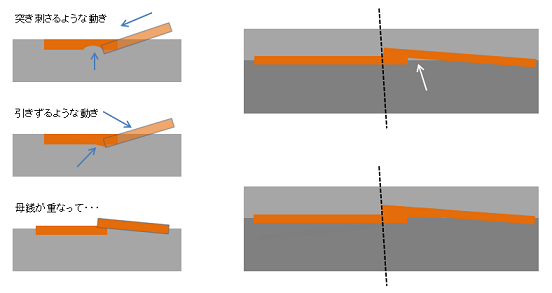





















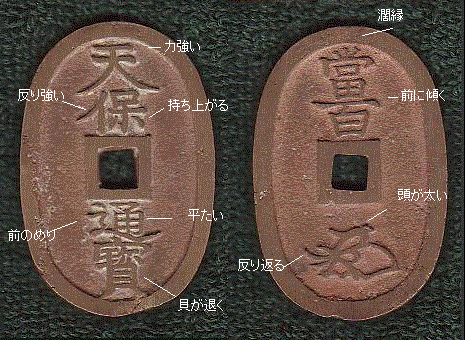































 長径48.9㎜ 短径32.5㎜
長径48.9㎜ 短径32.5㎜ 















 銅質が全く異なるので断定はできませんがやや大きな幅広極印と側面仕上げにはかなり共通性が見られます。
銅質が全く異なるので断定はできませんがやや大きな幅広極印と側面仕上げにはかなり共通性が見られます。





















 でも、実に美しい鮮紅色で、傷も少なく、背の文字抜けも抜群。背異反足寶でこの色で小様なんて皆無なんじゃなかろうか。これで石持桐極印だったらもう笑いが止まらない・・・という妄想が暴走してしまいました。玉がありそうに見えますが普通桐でした・・・残念。
でも、実に美しい鮮紅色で、傷も少なく、背の文字抜けも抜群。背異反足寶でこの色で小様なんて皆無なんじゃなかろうか。これで石持桐極印だったらもう笑いが止まらない・・・という妄想が暴走してしまいました。玉がありそうに見えますが普通桐でした・・・残念。















 (2010/5/15 2019/11/24制作日記)これらの考えは現在は否定されています。(私のHPではそのままになっていると思います。ごめんなさい。)
(2010/5/15 2019/11/24制作日記)これらの考えは現在は否定されています。(私のHPではそのままになっていると思います。ごめんなさい。)









 異足寶ながら短足寶にも見えるので内反足(O脚)寶と名付けました。側面はヤスリ目がほぼない感じで異極印。今のところ確認一品です。類品出てきませんかね。
異足寶ながら短足寶にも見えるので内反足(O脚)寶と名付けました。側面はヤスリ目がほぼない感じで異極印。今のところ確認一品です。類品出てきませんかね。

















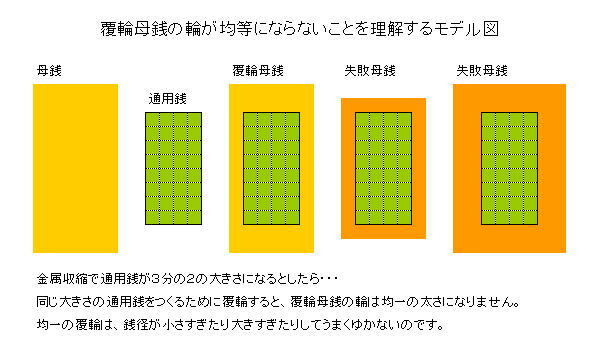 収集初心の方は覆輪、刔輪と言っても良く分からないかもしれませんので、ここでおさらい。
収集初心の方は覆輪、刔輪と言っても良く分からないかもしれませんので、ここでおさらい。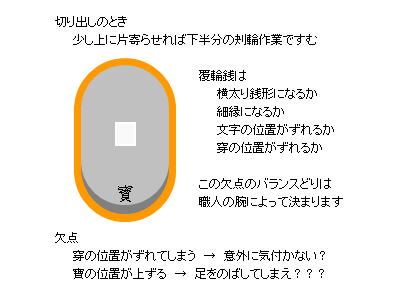



























 でもせっかく作ったので資料展示。古銭以外だと土器の破片とか鉄腕アトムの弁当箱ぐらいしかない。欅看板数枚と日本刀(登録済み)が一振りあるけど重いし物騒なので持っていけないですね。親父所蔵の絵が何枚かあるけど、僕の物じゃない。貧乏徳利がひとつあったかな。じい様の胸像が二つあるんですけど・・・誰もいらないよね。さて、オープニング談議で「最強の漢字」というお題がありました。私は「妻」だと思ったのですが、この字を書いて「そしじ」と読むそうです。霊的PWに満ちている文字で、枕の下に敷けば安眠をもたらし、痛いところに貼れば和らいだり、植物の下に置けば良く育ったり・・・信じるか信じないかはあなた次第。
でもせっかく作ったので資料展示。古銭以外だと土器の破片とか鉄腕アトムの弁当箱ぐらいしかない。欅看板数枚と日本刀(登録済み)が一振りあるけど重いし物騒なので持っていけないですね。親父所蔵の絵が何枚かあるけど、僕の物じゃない。貧乏徳利がひとつあったかな。じい様の胸像が二つあるんですけど・・・誰もいらないよね。さて、オープニング談議で「最強の漢字」というお題がありました。私は「妻」だと思ったのですが、この字を書いて「そしじ」と読むそうです。霊的PWに満ちている文字で、枕の下に敷けば安眠をもたらし、痛いところに貼れば和らいだり、植物の下に置けば良く育ったり・・・信じるか信じないかはあなた次第。