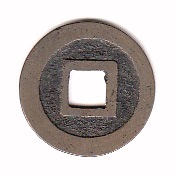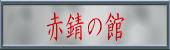|
|
| |
5.元禄期 荻原銭 元禄13年(1700年) 江戸亀戸村・京都七条鋳造 推定
元禄期に勘定奉行荻原重秀によって建議されて鋳造されたものと推定される銭貨の一群で、江戸荻原銭(元禄期亀戸銭)と京都荻原銭(京都七条銭)に大別されます。
この銭貨はその大きさから八分銭とも言われ、従来流通していた銭貨に比べかなり小型軽量になっていたため、評判はあまり良くなかったと思われますが、これによって貨幣が市中に充分行き渡り経済が好転したため元禄文化が花開いたとも言えます。
銭文筆者は長崎屋不旧とされていますが、不旧は後述のマ頭通のものの筆者としての方が有名です。個人的には元禄年間に京都で鋳造されたもの=京都荻原銭は、従来享保期七条銭、十万坪銭とされていた不旧手類のように思えます。遺跡からの出土状況、銭径が徐々に小さくなっていったという伝承などがそれを裏付けていると思いますが、現時点では旧説に従うこととします。
書体は流れるような細字体で、永柱が左側に傾く癖があります。通頭はコ頭通です。
書体、制作により、元禄期江戸荻原銭、元禄期京都荻原銭に中分類されます。 |
| |
| 元禄期荻原銭 【江戸荻原銭の類】 |
 |
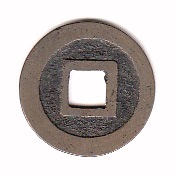 |
内跳ね寛、コ頭通、草点通、俯永などの特徴を持つ荻原銭の標準銭。厚肉の名称はついているものの、後述の京都荻原銭より背の彫りが深く背郭が大きいだけで、肉の厚さはさほど変わりません。掲示品は(古寛永の長門銭に似た)やや青味がかった白銅質で、一瞬母銭・・・と思うほどの美銭です。ただし、内径、外径とも通用銭の範囲です。荻原銭の白銅質銭は少ないと思うので、評価をあげてやっても良いと思います。
|
|
 |
 |
厚肉によく似ていますが、寛冠が小さく、寛の冠が寛字を包むように方折することから抱寛という名称がつけられています。 |
|
 |
 |
厚肉抱寛の白銅銭です。白目と同じ銅色で非常に珍しいものだと思います。各種泉譜には未掲載のもの。評価は暫定的なものですけど、少ないと思います。 |
|
 |
 |
前2銭より文字が細く、寛の足が高くなります。永字のフ画とく画の食い違いが大きいのが目立ちます。 |
|
 |
 |
やはり細字で寶字の王、尓が小さくなります。寛足寛ですけど永字のフ画とく画の食い違いがほとんどなく永柱に接しています。 |
|
| |
| |
| 元禄期荻原銭 【京都荻原銭の類】 |
 |
 |
内跳ね寛、コ頭通、草点通、俯永の特徴は江戸荻原銭と同じです。正永という名前はあるもののかなり癖の強い書体です。類品中唯一永点が跳ねません。背郭は江戸荻原銭よりかなり小さくなります。製作は前銭よりやや粗い感じで浅字。銅色は淡赤〜茶褐色が多くなります。
|
|
 |
 |
草点永という名前はあるもののこの類は正永を除きすべて草点永です。永字の左右の食い違いが著しく、とくにフ画が上にあがる癖が強くなります。やはり背郭は小さくなります。 |
|
 |
 |
永字が幅広くすそ野を広げる感じで扁平です。永柱は全体的に左側に寄っています。
|
|
 |
 |
書風は前銭と同じですけど、永字のフ画とく画の食い違いがほとんどなく永柱に接しています。
|
|
| |
 |
 |
| 拡大画像サーフィン |
|
| 荻原銭類の拡大図 |
厚肉
やや太字で洽水気味。 |
厚肉抱寛
前銭に似るが寛冠の幅が狭いがその分深くなり寛字を包み込む。 |
厚肉高寛
やや細字になる。永字は扁平で左右の画の食い違いが大きい。高足寛。 |
厚肉高寛洽水
前銭に良く似るが、永字の左右の画が一点に集中している。 |
|
 |
正永
細字で永柱長く、不草点永である。 |
草点永
細字で永柱長く、草点永になる。 |
草点永進永
やや太字。草点永で永字扁平で幅広く長く尾を引く。 |
草点永進永洽水
前銭に似るが、永字の左右の画が一点に集中している。 |
|
| |
|
| |
| 母銭について・・・ |
私は井の中のかわずでして、鑑識眼についてはまだまだアマチュアの領域です。とくに母銭の真贋判別についてはいまだにしっくりいかないものがあります。
母銭の判別法ですが
1.銭径が大きく 2.文字の立ち上がりが良くて 3.とくに背の仕上げが美しい ことが条件で、4.内径が一般のものより大きく 5.外輪や郭の隅まで丁寧なやすりがけがあり 6.湯圧(押し湯)が強く肌がきめ細かく 7.材質も異なることがある とここまでくると完璧です。
ところが世の中には例外があるもので、すべてを兼ね備えた母銭ばかりではありません。したがって各ポイントを見て判断することになりますが、文銭の母銭などはノギスで計測しない限り通用銭の美しいものとの区別ができない場合があります。
上記ポイントのうち重要なのが3.4.5あたりですが、プロでも間違うことが多く、仙台石ノ巻銭の大型銭らしきものをを母銭として扱っているケースなどがよくあります。(私も未だに良く判りません。)
古銭商の売り物を見ていて、どうしてこれが母銭なの・・・と思い悩むことがしばしばあり、私が母銭を収集の主役にしない理由のひとつになっています。(高くて手が届かないのが本音ですが。)
数を見ること、そして判定は厳しく、疑問が少しでも残れば母銭と判断しない・・・そんな心構えが必要だと思います。
以下に母銭あるいはそれに準ずる規格、仕上げの銭貨群を並べてみます。その雰囲気を感じ取って下さい。 |
| |
様々な顔を持つ
母銭仕上げの銭貨群・・・ |
| 元文期小梅手 俯永母銭 |
元文期山城横大路銭 進永大様母銭 |
元文期不知銭 膳所額輪母銭 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 鋳肌が滑らか、材質も少し違うもの |
材質、内外径が異なるもの |
材質、仕上げが異なるもの |
|
| |
| 元文期不知銭 膳所額輪縮寶母銭 |
寛保期高津銭 細字背元未仕立母銭 |
仙台石ノ巻銭 異書進冠白銅銭 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 母銭だが不完全な出来のもの(背郭) |
母銭だが仕上げ不完全なもの(郭内) |
母銭か大様銭か迷っているもの |
|
| |
| 寛文期亀戸銭 正字背文母銭 |
寛文期亀戸銭 繊字背小文母銭 |
寛文期亀戸銭 島屋文小頭通細縁 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 内外径、背郭から総合的に母銭と判断 |
内外径、郭内やすりなどから母銭と判断 |
廃棄母銭あるいは特別な通用銭か? |
|
| |
| 元文期十万坪銭 母銭式背十 |
古寛永長門銭 奇永垂寛手本銭 |
古寛永御蔵銭 正字母銭 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 母銭式しか存在しないもの |
毛利家伝来の手本銭 |
鋳ざらいが美しい古寛永母銭 |
|
| |
| 元文期不知銭 内跳寛縮永母銭 |
安政期小菅銭 薄肉母銭 |
万延期仙台石ノ巻銭 大字背千母銭 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 鉄銭の母銭 |
非常に美しい鉄銭の母銭 |
鉄銭の母銭 |
|
| |
| 慶応期南部藩銭 仰寶ござすれ母銭 |
 |
 |
| 鉄四文銭の母銭(輪ござすれ) |
| |
|
| 本座広郭母銭 |
 |
 |
| 天保通寶の母銭 |
|
| 明和期 正字母銭 |
 |
 |
| 銅四文銭の母銭 |
| |
|
| 慶応期南部藩銭 仰寶母銭 |
 |
 |
| 鉄四文銭の母銭 |
| |
|
| 密鋳 明和俯永改造母銭 |
 |
 |
| 改造母銭と推定されるもの |
| |
|
| 慶応期南部藩仰寶次鋳母銭 |
 |
 |
| 通常のものより小さいもの |
|
| 密鋳 日光銭改造母銭 |
 |
 |
| 改造母銭と推定されるもの |
|
|
| |
| 七条銭退永小通母銭 |
八戸藩 葛巻目寛母銭 |
元隆手 背左元 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 材質も制作も異なるもの |
密鋳鉄銭の母銭 |
安南寛永の母銭 |
|
| |
 |
 |
 |
 |
貼り合わせ改造母銭?
インターネットで購入したもの。面背の状態の良い物を磨耗させて張り合わせた改造母銭と推定されますが、なぜこんな手の込んだものを作ったのかは不明です。
貼り合わせタイプの改造母銭はときおり見つかるそうで、本来は肉厚になりがちなこのような改造は原材料の節約や手間の面から敬遠されるべきなのですが、材質不良や溶銅の温度が上がらないことからくる湯回り不良を防ぐ意味でも、このような手法がとられたのではないかと・・・勝手に推定しています。
ただし、この銭原品は非常に薄い!ここまで密鋳でやるのかとかんぐってしまいます。あるいは本炉でこんなことをした?まさかねぇ? |
|
改造母にご注意を!
私はいまだに改造母というものが良く分かりません・・・と、いうより母銭そのものがよく分かっていません。
明らかに銅質、製作が異なるものはわかります。とくに内径が大きいという特徴はなにより説得力があり、これに穿内やすりがあれば鬼に金棒です。ところが、たとえ文銭の母については俗説に『文銭に母銭なし』と揶揄されるように、多くが初出の大様を母と市場認定しているように感じます。古寛永などは通用銭を鋳ざらって使用したため、明らかに母銭とわかる称:仙台銭や御蔵銭、竹田銭などは別として市場にあるものの多くが『なんでこれが母?』と思うものがほとんどです。
ましてや改造母となると、もとが通用銭ですから後加工が可能なだけに判断はかなり困難です。
1枚10円以下の雑銭がちょっとやすり目を入れるだけで3000円以上に化ける・・・これはおいしい事業です。また、昔は盗銅といって材料の銅を削り取ることも横行していましたし、ストッパーやクサビの代用で銭を使用したこともあって輪側が磨耗した寛永銭は良く見つかります。このようなものを『改造母』としてしまうこともままあり、そのため改造母については(達人研究者はともかく素人は)あくまでも参考収集にとどめるべきであると思います。それでも収集癖がやめられない方・・・覚悟して下さいね、絶対損しますから。 |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|